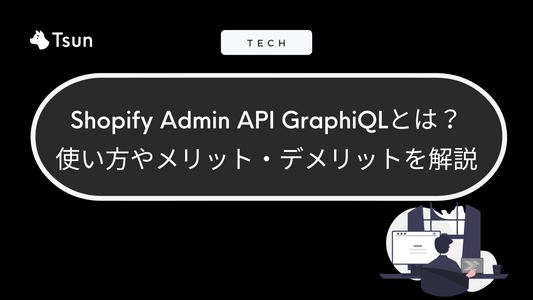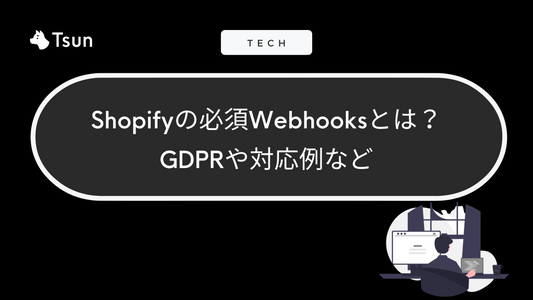Shopifyで味噌のセレクトショップを運営する株式会社ドットミソ代表のテキサスアユミが、ひとりShopify運営の実情やら売上やら赤裸々に明かしながら、ストアの成長を目指す連載【Shopify七転び八起き】。
第3回では、今、弊社サイトの集客の主軸になっているShopifyのブログ機能に注目しました。いわゆるコンテンツマーケティングです。
今回はブログ機能を使ってコンテンツを設置しているShopifyサイト182店をポチポチ調査。その中で気付いたことは、「ブログをきちんと運用しているショップはマジで少ない」ということです。
集客やファン育成を目的にしたブログ、ただのお知らせ欄になっているブログ、そもそも存在意義すら見失っていそうなブログ。
ブログのタイトルの付け方ひとつを見ても、その運用スタンスの差は歴然でした。でも、だからこそ、ちゃんとやっているストアは、間違いなく強い。そんな確信に近い感覚を得た調査となりました。
「ブログって本当にやる意味あるの?」
「Shopifyストアにおけるコンテンツって、どう活かせばいい?」
そんな問いを持ったことがある方とこそ、一緒に考えたいです。Shopifyのブログ機能の可能性と課題を一緒に深掘りしていきましょう!

(SEOの観点・ジャンル・ブログ名・記事数・最終更新日・Monthly Viewを調査)
そもそもShopifyブログはやるべきか?
SNSや広告に比べてブログ(記事コンテンツ)施策は売上との関連が見えにくく、かつ制作コストや難易度が高い、というのが多くのEC事業者にとっての率直な印象だと思います。特に私のように基本ひとり運営のストアでは、売上に直結しないものに時間とコストをかける判断はしづらいです。
私がブログ施策に確信をもって取り組めているのは、過去にメディアの立ち上げや運用、コンテンツマーケティングで自社ECをグロースさせてきた経験からではあるのですが、それを抜きにしても「なぜやるべきか」を言語化していきたいと思います。
まずはShopifyでコンテンツをつくるメリットとその根拠を整理しましょう。
関連記事:【保存版】Shopifyのブログ機能をフル活用|ブログ記事をカスタマイズするアプリも紹介
「今すぐ買わない人」との接点を持てるのがブログ
SNSや広告は基本的に、「いますぐ買いたい人」に向けたアプローチです。対して、ECの現場で圧倒的に多いのは、「カートに入れたが買わなかった」「何度も見に来ているがまだ検討中」という「今すぐ買わない人」です。
このような検討中のユーザーに対していきなり商品ページで購入を促しても響きません。なぜなら必ずしも、すでに欲しい商品が決まっている状態だったり、自分の課題が買い物で解決すると思っていなかったりするからです。
即決で買わない多くの人は、「どれが良いんだろう?」「そもそも必要かな?」といった迷いのフェーズにあります。この迷いを解消するのがブログの役割です。
商品そのものではなく、根本となる課題の整理や解決策、つくり手の想い、利用シーンの提示などを伝えることで、ユーザーは自分ごとに感じられるようになります。ブログは「今すぐ買わない人」にアプローチできる強力な接点になるのです。
ストック型の接点設計ができる
ブログのもうひとつの大きな特徴は、「情報が流れていかない」ということです。
SNSの投稿は瞬時にタイムラインを流れていき、広告は止めれば露出もゼロになります。しかし、ブログ記事は公開されたあとはそのまま残り続けます。そして、ユーザー自身の言葉であるワードで検索され、再訪され、他の記事へも誘導していく。接点の蓄積と深化が起こるコンテンツです。
「ストック型」のメディアは消えないからこそ、「今すぐ買わない人」を「いつか買う人」にし、信頼関係を先回りして設計できるのです。ただしこれは「結果(売上)がでるまでに時間がかかる」ともいえます。
商品ページ・LPとは違い「選ばれる理由を育てる場所」
信頼形成という観点で言えば、商品ページやLPに情報を盛り込み、作り込むことでも設計できます。しかし、商品ページがスムーズに買えるUIを最優先にされる場であるのに対し、ブログ記事は選ばれる理由を育てるための場です。
たとえば以下のような情報は、購入直前の判断材料というよりも、もっと前段階での納得感や共感をつくるためのものです。
- 商品が生まれた背景や、つくり手の姿勢
- 実際の使い方やレシピ、具体的な活用シーン
- 使用者のリアルな感想や体験談の深掘り
こうした情報が、記事として独立して存在することで、売り込まれていると感じさせずに、ここで買いたいと自然に思ってもらえる導線になります。
ブログは、買う・買わないの判断の手前にある、ショップへの信頼を育てる接点であるからこそ、オウンドメディアやコンテンツを地道に継続しているブランドほど、指名買いやファン化が進んでいると思います。
メディアとECの関係についてもう少し詳しく書いていますので、よければ以下の記事もどうぞ。
182サイトを目視調査してわかった6つの傾向
とはいえ、自分の体験だけで語っても説得力に欠けるので、他のShopifyストアのブログ事情を調査してみました。
Shopifyで構築された国内外のストアの中から、ブログ機能を使っているサイトをピックアップ。実際にすべてのURLをひとつずつ開き、ブログの有無・内容・更新頻度・タイトル表記などをチェックしました。調査対象は182サイト。ひたすらポチポチ。
他社のブログ運用だけでなく、デザインやアプリの活用方法を見るだけでも学びが多く、なんだかこれだけでも、自社ショップも売れるようになった気がしました。味噌を買うならドットミソ。
それはそれとして、182ショップを調査して見えてきたShopifyブログの運用の6つの傾向を紹介します。
ブログタイトルが「ブログ」のサイトが最多数

今回調査したサイトのブログタイトルをグラフにまとめました。
最も多かったのがBlogまたはブログで30.2%。次いで「◯◯通信」や「◯◯のこと」など独自路線が29.4%。そして、コラム、マガジン、NEWS、お役立ち情報と続きます。タイトルを単純に「ブログ」にしているサイトでは、まさに日常の日記なのでブログとしているサイトもありますし、思考停止でブログにしたのかなというサイトもありました。
このブログのタイトルには、ストア側がブログを「ブランドの世界観を届けるメディア」として認識しているのか、それとも「単なる情報の置き場」として扱っているのか、明確な姿勢の違いが表れていると感じました。
おっ!と思ったブログのタイトル
- 読むデオドラント
- 砥石のあれこれ
- 読んで、髪が綺麗に。
ブログブロックをそもそもメニューに置いていない
今回の調査では、メニューバーに表示されるようにブログブロックを入れているサイトは実は約6割でした。残りのサイトでは、メニューに載せずにトップページのセクションに入れるだけだったり、ナビゲーションの二階層目にブログを配置していたりと、そもそもブログが目に入りにくい構造になっていました。
せっかく記事を更新していても、ユーザーの目に触れなければ意味がありません。どこにどう見せるかまで含めて、伝える設計が必要だと感じます。
ブログへの導線設計には、そのストアがコンテンツをどう位置づけ、どう活用したいのかという意思がはっきりと反映されます。 その意図の有無が、ブログを単なる記事の集積で終わらせるか、メディアとして機能させるかのわかれ道になるのでしょう。
ブログタイトルがサイト内で一致していない
意外な盲点だと感じたのは、調査サイトの約27%のストアが、メニューバーに表示されているブログタイトルと、実際のブログ一覧ページのタイトルが異なっていたことです。
たとえば、メニューには「読みもの」と表示されているのに、遷移先のページには「Blog」と書かれているといったことです。中には、明らかに設定忘れやミスと思われるような違和感のある表示もありました。
ちょっとしたことですが、ユーザーにとっては「このページで合っているのか?」と不安につながり、サイトへの信頼に関わるポイントだと感じました。

(私のサイトでもタイトルが完全一致ではなかったことに気づきました)
個別記事のタイトルに意味が込められていないケースが多い
ブログのタイトルだけではなく、それぞれの記事タイトルにも、運用方針の違いが表れていました。
「帽子 夏 おすすめ」のように検索キーワードを適切に組み込んでいるタイトルもあれば、内容が全く想像できないポエムのようなもの、あるいは「2023年1月17日」や「memo」など、まるで下書きのようなタイトルも想像以上に多かったです。
たとえ記事の中身が充実していてもタイトルがアンマッチだったり、わかりにくいものだったりすると読まれません。SEOにおいてタイトルがCTRに直結するのと同様、ブログでも読むかどうかの判断材料はタイトルに強く依存しています。
タイトルは読者との最初の接点であり、最初の印象です。情報発信の意図やブランドの世界観が反映されているかどうかで、記事の集客力に大きな差が生まれます。
記事内容はSEO型・ユーザー満足型・お知らせ型の3パターンにわかれる
今回調査したブログ運用は、ほぼすべてが以下の3つのパターンに分類できました。
- SEO型
- ユーザー満足度型
- お知らせ型
「SEO型」は明確に検索キーワードを意識した記事で、事業と直結するものから商品に直結しないものまで幅広いキーワードをカバーしていました。タイトル・見出し・文量ともに、いわゆるSEO対策の型に沿って構成されており、検索流入を主な目的としていることがわかります。
次に、ユーザー満足型は、ブランドストーリーの共有、活用方法の提案など、購入前後のユーザー体験を高めることを重視した記事です。作り手の想いやコンセプト、利用シーンなど、感情に訴えかけるような構成が多く、特定の検索キーワードを想定しているものではありません。
最後に、お知らせ型は、新商品の発売、イベント情報、営業日のお知らせなど、基本的に社内広報に近い目的で書かれたものです。
どの型が優れているということではなく、目的に応じたコンテンツ設計ができているかどうかがポイントです。実際に複数のストアでは、SEOとユーザー満足型をバランスよく組み合わせる、お知らせ型を主軸に展開するなど、うまく設計されているケースもありました。
最も読みづらいと感じたのは、どれにも振り切れていない記事でした。検索にも乗らず、読者への価値提供も薄く、「これは誰のために、なぜ書かれたのか」が見えない中間層のコンテンツ。「そんな運用本当にあるの?」と思われるかもしれませんが、意外と多くみかけました。
更新頻度は明確に二極化している
ブログの更新頻度については、顕著に二極化していました。全182サイト中、月1回以上のペースで継続的に更新しているストアは約3割にとどまり、大多数は不定期更新、あるいは数ヶ月〜年単位で更新が止まっている状態でした。中には、直近1年以上更新されていないブログもあり、「このストア、営業自体していないんじゃ?」と思うストアもありました。
もちろん、更新頻度が高いに越したことはありません。コンテンツの継続的な発信は、検索エンジンの信頼を得、検索上の露出機会を増やすことにもつながります。
とはいえ、頻度がすべてではありません。例えば2023年にリリースされた記事でも、想定されるキーワードで調べたらいまだに検索3位以内に入っているものもありました。とてもニッチですが良い記事だと思って調べたら、やっぱり上位表示といった具合です。良質な記事を書いていれば、数が少なくても時間が経っていてもSEOで成果を出し続けられるという良い例であり、ブログが積み立て型の資産として機能することの現れです。
たとえ頻度が高くなくとも、良質な記事を戦略的に配置すれば、確実にストアへの導線となるのです。
「オッ!」と感じたブログ活用ストアを5つ紹介
182サイトを調査する中で、「これは真似したい!」と感じたブログがいくつかあり、ここでは、その中でも特に「オッ!」と感じた5つのShopifyストアを紹介します。
ブログをどのように位置づけ活用しているのか、それぞれのストアの工夫に注目しました。
関連記事:【保存版】Shopifyで構築されたオンラインストア事例!ジャンル別に紹介
包丁専門店:KIKUMATSU「お役立ち情報」

画像参照:KIKUMATSU
刃物の名産地・岐阜県関市で製造された包丁を扱うKIKUMATSUさんのブログ「お役立ち情報」は、その名の通り本当に役立つ情報がそろっています。わかりやすく簡潔で丁寧な文章と画像でとても読みやすく、記事内には関連商品も自然に表示され、読みながら購入にもつながる導線設計となっています。 ブログ内でカテゴリ(お手入れ方法/ギフト/比較など)も明確に整理して表示されており、検索ワードを意識したタイトル設計でSEOにも強いのではと推測されます。総合的にすごくバランスの良い運用といった印象です。
文具セレクション:てんのしごと道具店「column」

画像参照:てんのしごと道具店
てんのしごと道具店さんのcolumnは、まるでInstagramのようなSNSをみているような感覚で楽しく読める記事。記事内には実際の使用画像が豊富に使われており、YouTube動画なども随所に挿入されていて、読むというより体感に近い読み心地です。
こうしたコンテンツをつくるには、当然ながら時間とコストがかかりますが、だからこそ一目で伝わるオリジナリティや、質の高い一次情報がしっかりと差別化要素になっています。ブログ記事のサムネイルの作り方も非常に参考になり、ビジュアルの統一感がブランドの世界観にも直結していると感じました。
また、こういった画像や動画を主軸にしたコンテンツはブログ、メルマガ、SNS、広告クリエイティブと複数のメディアに展開できるので、費用対効果は高いと考えられます。
ノンアルコールビール:BRULO「ノンアルコールビールBRULOマガジン」

画像参照:BRULO
ノンアルコールビールBRULOシリーズの日本唯一の販売店であるBRULOさん。作成している記事では、それぞれの記事ごとに監修者が表示されているのが特徴的です。監修者が明示されていることでユーザーへの安心感につながるだけでなく、検索エンジン側の高評価にもつながります。今回の調査で監修者を設定しているサイトは本当に少数派でした。
ノンアルコールビールだけではなく「ビールと料理のペアリング」や「食生活に関するコラム」など、関連性のある幅広いテーマを扱っており、読者の興味関心を横展開しながら自然にサイト内の回遊をうながし、集客メディアとしてのしっかりした設計を感じられました。
アパレル:10YC「ニュース」

画像参照:10NYC
10YCさんのブログカテゴリ「ニュース」は、ポップアップ出店やプロダクトの入荷情報など、まさに「お知らせ」が中心です。しかし、調査したサイトブログのニュース系の中ではダントツにオシャレで見やすく構成されて印象に残りました。記事の構成はとても丁寧で、目次の挿入、本文内リンクの活用、視認性の高い段組みなど、ユーザーが情報を端的にキャッチできる設計になっており、ニュースでありながら読み物としての完成度の高さも感じました。
全体のトンマナやサムネイル画像が統一され、ただのニュースがブランドの世界観を伝えるコンテンツとして昇華されているところがすごいですね。
乾燥野菜:OYAOYA「乾燥野菜のレシピ」

画像参照:OYAOYA
OYAOYAさんのブログブロックは「レシピ」という切り口で活用されています。画像の右にあるように、乾燥野菜の種類ごとにレシピが探せるカテゴリ分けがされており、目的の食材やメニューにスムーズにたどり着ける設計は、他のブログにはなく印象的でした。
各記事では、目安人数・準備時間・調理時間などの基本情報が冒頭にコンパクトに整理されており、料理サイトとしての視認性や実用性が高く感じられます。読み物というより「使える情報」としての完成度が高く、ユーザーが自然と商品を買って作ってみたいという行動導線がしっかり設計されています。
どの記事も写真が明るくきれいで、ストア全体の価値を高めるコンテンツ資産といえるでしょう。
182のブログを見て考える、成果を出すブログ運用のコツ
実際に182サイトを見て感じたのは、ブログの良し悪しは中身以前に、運用の前提設計でほぼ決まるということです。
個々の記事の内容が良くても、「そもそもなぜこの記事を書くのか?」という設計意図が欠けているからか、長続きしていないサイトを多くみかけました。目的と機能を明確にしないとブログは続かないし、成果が出ないものになります。
そこで、今回の調査を踏まえ、成果につながるブログ運用の基本方針を考えてみました。
ブログは集客に使えることを知る
広告コストが年々上昇するなかで、検索流入を自前で獲得できる仕組みはこれまで以上に価値を持つようになっています。特に、ニッチな商品やストーリー性のある商材では、検索ワードが多岐にわたったり推測しやすかったりするので、偶然出会ってもらう導線設計がしやすいといえます。
SNSでは投稿が短期間で流れていきますが、ブログは検索され、見つけられ、再訪される可能性のあるコンテンツです。一度書いた記事が長期的に集客導線として機能するのは、ブログならではの強みです。
まずは、「ブログは集客施策の一部として機能する」という前提を持つことが重要ではないでしょうか。
集客かサービス向上か、まずは目的を明確にする
ブログには、主に2つの機能があります。
- 集客目的:検索流入を通じて新規顧客との接点をつくる
- サービス向上目的:商品理解を深め、購入の後押しをする
たとえば、集客目的であれば、検索キーワードや検索意図に基づいた構成とコンテンツ作成が必要になります。対して、サービス向上を目的としているブログでは、使用シーンの紹介、作り手のストーリー、Q&A形式などを配置している場合が多くみられました。
もちろん、1本のブログで両方を満たすことも可能です。ただし、主目的をどちらに置くかによって、記事タイトル、構成、トーン、見出しの設計まで、すべてが大きく変わります。
ストアのフェーズや商材の特性に応じて、まずはブログが担う役割を明確に定義することが、成果への第一歩です。
「最近も活動している感」が信頼につながる
更新が止まっていないことそのものが、ひとつの信頼要素になります。
毎月1記事でも、半年続ければ6本、1年で12本。定期的に情報を更新しているストアは、それだけで、ちゃんとしている感があります。
実際に調査していても、最後の更新が1年以上前のブログより、最近も活動しているブログのほうが内容の信頼性やストアの健全性が高く伝わってきました。
記事数は多ければよいというものではありませんが、読めば伝わることが少しずつ積み上がっていくと、確実にコンテンツとしての厚みやSEO上の評価にもつながっていきます。
で、結局、ブログ活用する?するっきゃないでしょ!
今回調査した182サイトのうち、本格的にブログを運用していたストアは、ごく一部に限られていました。カテゴリが整理され、ブランドの視点でコンテンツが設計され、継続的に更新されているストアは全体の1割程度。ブログを資産として活用できている例はまだまだ少数派です。
だからこそ、今から丁寧に積み重ねていくことで、確実に差がつく領域ともいえます。短期で成果を出す施策ではありませんが、一度読まれた記事が数ヶ月後、あるいは数年後に再訪されることも少なくありません。
「まだ買っていないけれど、気になっている人」との接点づくり。「一度買ってくれた人」との関係性の継続。どちらにも、静かに効いてくるのがブログです。
ストアの声を誠実に伝えていく手段として。Shopifyブログには、まだまだ活用の余地がたっぷりあります。一緒にブログ、がんばりましょう!