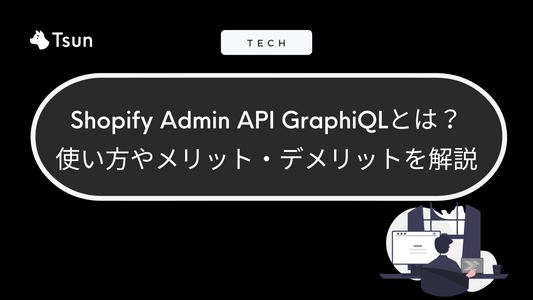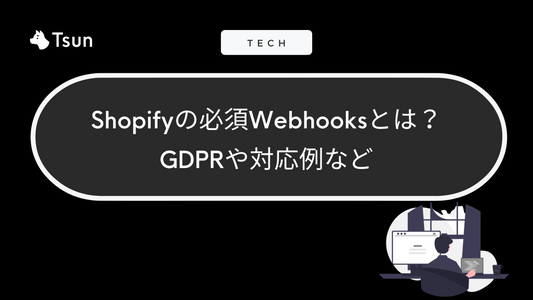大阪にある1927年創業の老舗ニット工場「ノグチニット」は、長年OEMを手がける裏方として事業を続けてきました。そんな同社が自社ブランドを立ち上げ、D2Cブランドへと変化していくまでには、多くの試行錯誤と製造現場との葛藤、そして強い危機感がありました。
現代表の妻、上坪裕子さんが「アトツギの嫁」として工場に入り、製造から販売、そしてブランディングやShopifyへの移行に至るまでのリアルな歩みをお伺いしました。

(株式会社ノグチニット 上坪 徹也さん(左)裕子さん(右))
下請け一筋の工場からの脱却
―― 最初に、ノグチニットの事業の変遷についてお聞かせください。
上坪さん ノグチニットは1927年創業で、長年ニット製品を手がける下請け工場でした。自社名義の商品を持たず、名前が出ることもない完全な裏方の立ち位置です。
以前はセーターをOEMで製造しており、特にスキーアパレルのセーターを請け負っていました。しかしスキー用にセーターを着る文化がなくなってきて、新素材の登場とともに、工場もニット帽づくりへと方向転換。規模を縮小しながら、売上を落としながら、何とか生き残っていたという状況でした。
そんな中、私が嫁として会社に入りました。当時はまだ売上もそこそこありましたが、夫から「毛糸を仕入れて商品が出ていく」と聞いたときに、「だったら自分たちの商品を作って売ればいいじゃん」と思ったんです。完全に素人発想ですけどね(笑)。
―― 最初から「下請けではなく自社商品を」と考えていたんですか?
上坪さん はい。入社の時点から、自社販売をやりたいという気持ちがありました。でも、何を売るかも決まっていなかったし、最初は本当に手探りでした。結婚を機に事務職を退職して、ミシンの使い方から覚えて。1日8時間ミシンを踏み続ける仕事を何年もやって、たまたま手先が器用だったこともあり、製造もそれなりにできました。下請け業務をこなす日々でしたが、ずっと「自社販売がしたい」と思っていました。
でも、製造がちゃんとできなければ社内で信用されない。だからこそ、自分の時間は製造にあてながら、少しずつ準備を進めていましたね。

アパレル経験ゼロで挑んだ自社ブランド事業
―― 未経験からのアパレル参入ですが、アパレル事業には特別な関心や思い入れがあったのでしょうか?
上坪さん 正直、自己表現とかブランドを立ち上げたいという気持ちはまったくなかったんです。ただ、「このまま下請けだけだと危ない」という危機感がありました。仕事を1社に依存していたら、何かあったときに立ち行かなくなると感じていたので、自社ブランドをやるしかない、と。
―― アトツギとして新しい事業に取り組むことに難しさはありましたか?
上坪さん ありました。新しいことを始めても、社内の認識はなかなか変わらず、「嫁が勝手にやってる」と思われ続けていたので。どれだけ売上が立っても、スタッフの認識が変わるわけではないですから。
休みの日に工場の機械を借りて、自分で作った商品を売っていましたが、社内では「嫁が勝手にやっているだけ」「趣味だろう」という空気感で、スタッフも巻き込めず、応援もされていませんでした。スタッフを使ってもいいと言われるまでに数年はかかりましたし、「なぜ嫁の趣味に巻き込まれなきゃいけないんだ」という反発もありました。だから、最初は本当に夫婦でバタバタやっていた感じです。
特に工場の現場は、SNSやマーケティングとは無縁の世界です。動画を撮ろうとしても「映りたくない」と言われたり、工場の様子を発信しようにもなかなか難しい。でも、製造に特化した人たちなので、それは仕方ないとも思っています。だから無理に変えようとはせず、自分たちでできる範囲で取り組むようにしています。
テント出店から始まった手探りの販売
―― いつから自社ブランドが始まったのでしょうか?
上坪さん 2011年に結婚して入社し、翌年の2012年の冬には商品を用意して初めて販売しました。最初は手作り市に出店して、お客さんの反応を見ながら「これ売れるかな?」と試していました。アパレルの経験も販売スキルもゼロだったので、現場で学ぶしかなかったですね。
最初はテントを張って出店しましたが、これが全然売れなかった(笑)。でも、リアルな場でお客さんの声を聞くこと、売れている他の作家さんの商品を見ることは大きな学びになりました。
ただ、「興味のない人には売れない」という現実も痛感しました。イベントには観光客も多く、そもそも買い物目的ではない人たちが多かった。立ち止まってもらうだけでも大変でしたね。
―― そこからECはどう入っていったのでしょうか?
上坪さん 2014年頃、minneやCreemaなどハンドメイド販売サイトが盛り上がり始めて、私たちもminneでの販売を始めました。最初は期待していなかったんですが、ある時期からサイトのピックアップに取り上げられて、売れ始めたんです。広告費ゼロで、冬の3か月間だけで300万円の売上が出たこともあります。
でも、この時点では完全な「プラットフォーム頼み」で、運営に取り上げられないと売れないし、自分たちで売上をコントロールできない。これが「自社サイトを持つべきだ」という発想につながっていきました。
―― minneで販売が伸び始めたとき、どんな変化がありましたか?
上坪さん ピックアップされたことで注目されて、「写真の力ってすごいな」と実感しました。そこからは「どう撮れば魅力的か」を自分なりに考えて学びました。
撮影場所も工場の隅に壁紙を貼って、スマホでトルソーに商品を被せて撮る。今思うと全部素人だったけど、必死でしたね。でもminneやCreemaでもピックアップで紹介されれば売れる時代だったんです。

(ノグチニット minneのショップ)
ECサイトの第一歩はSTORES
上坪さん minneで売れながらも、「これは一時的なものかもしれない」という不安は常にありました。ピックアップされるかどうかが運次第で、自分たちで売上をコントロールできない。「これでは続かない」と思っていたら、2019年の夏に知人を通じて靴下ブランドの先輩経営者に話を聞けたんです。
その方に「これからは自社サイトを持たないとダメだよ」と言われたことがすごく響いて。「メルマガが出せないのは致命的」「顧客データが溜まらないのはビジネスではない」と言われ、初めて顧客リストの大切さに気づかされました。
その方から自社ECを育てるアドバイスをもらい、自分で30個くらいチェックリストを作って何年もかけて一つずつ実践していきました。「同梱したチラシにQRコードをつけよう」「手紙を同封しよう」「サイトにブログをつけよう」……とにかく全部試しました。
―― その時点ではまだ自社サイトはなかったんですね。
上坪さん はい。いくつかサービスを比較していて、最初はカラーミーショップに契約して5000円払ったんですが、希望のデザインをするためにはフルスクラッチでカスタマイズしなければならなくて。BASEやSTORESが登場し始めていたんですが、シンプルに始められそうだったSTORESを選びました。無料で開設できたのも大きなポイントでしたね。
―― STORESではどのように販売されていたのでしょうか?
上坪さん 最初の数ヶ月は全然売れなかったです。でも「売れないことに慣れていた」ので気にせず続けていました(笑)。
そんな中、2020年のコロナ禍がきて、たまたま作っていた花粉対策用のマスクに突然アクセスが集中して、広告費ゼロで何千万円もの売上が出たんです。
ただ、製造が追いつかずクレームも増えたりで、現場がどんどん疲弊していきました。それでも、その売上があったからこそ「思い通りのデザインのサイトを作ろう」と思えたんです。
Shopifyで再構築するサイトとブランド
―― なぜShopifyを選んだのですか?
上坪さん いくつかのカートを比較してShopifyが一番かっこよかったんです。事例として紹介されているサイトのデザインが圧倒的で、「こんなサイトが作れるなら」と思って決めました。管理画面もシンプルで使いやすいですし。2020年の秋頃から準備して、2021年の4月にShopifyでリニューアルオープンしました。
Shopifyに移行してすごく良かったです。特に、広告やSNSとの相性がすごくいい。管理画面も使いやすいし、アプリもいろいろあるけど自分たちに必要なものだけを選んで、シンプルに構築することができました。
ただ、Shopifyへの移行は一大プロジェクトでした。ブランドとしてどう見せるか、ビジュアルやコンセプトも含めて全部見直すことになって、チームを組んで撮影やデザインの方向性まで半年以上かけて詰めていきました。
このタイミングでブランディングも一気に強化しました。それまで何となくやっていたことを、ちゃんと言語化して、「私たちはこういう商品を、こういう人に届けたいんだ」という軸を明確にしたんです。

上坪さん テーマはPrestigeという有料テーマで、実はほとんどカスタマイズしていません。テンプレートの完成度が高いから、自分たちでも運用しやすいんです。外部の制作パートナーからも、「下手にいじるより、このままの方が管理しやすいし、見た目も整っている」と言われて。
私たちのように社内にエンジニアがいない場合、なるべく手をかけすぎない構築が一番だと思います。画像や文章でどこまで世界観を伝えられるか、に注力しました。
―― 管理側のシンプル運用を徹底しているんですね。
上坪さん 年齢層が高いお客様が多いので、あまり情報が多すぎると迷わせてしまう。ギフトカードひとつ追加するにも慎重に考えています。「このボタンでお客さんが迷わないか?」といった視点で細かく検討しています。
「売れすぎが怖い」から見えたブランドの軸
ーー Shopifyに移行して一番よかったと思う点は何ですか?
上坪さん 一番意識したのは、「自分たちでコントロールできる範囲でやる」ことですね。たとえば、Instagramでバズったり、テレビに取り上げられたりすることって、もちろん嬉しいんです。でも、それがありがたいことばかりとも限らないんです。
うちは大量生産の工場じゃなくて、自社で一枚ずつ編んでいます。1日に作れる数には限界があるし、機械も限られているから、「この週はこの商品」と割り振って動かしています。その中で、急に予想外の注文が殺到したら、現場がパンクしてしまうんですよね。
―― 注文が増えすぎることが恐怖になることもあるんですね。
上坪さん はい、嬉しいんだけど、正直怖い(笑)。だからSNSでも、なんとなくバズりたいではなく、「ちゃんと届く人に、ちゃんと届ける」ことを意識してきました。誰かの心にちゃんと届く言葉や写真を考えて、それが売上につながる形にしていく。それが、私たちの“地に足のついた”やり方です。
OEMから自社ブランドへと転換していく過程で、社内の理解を得ること、販売チャネルを整えること、限られたリソースの中でやれる方法を探ることなど、さまざまな葛藤と工夫をお伺いしました。無理に大きく見せようとせず、自分たちのペースで続けられるやり方を模索してきた積み重ねと、日々の現場との向き合い方が、今のノグチニットのブランドを形づくっています。派手さよりも確かさを大切にするその姿勢は、多くのものづくりの現場にも通じるものがあると感じました。
インタビュー後編【“売れすぎない“ことで、顔が見えるものづくりを積み上げる】はこちら