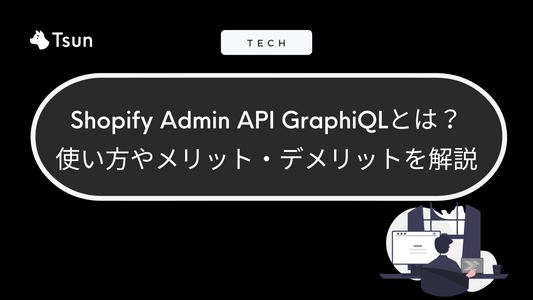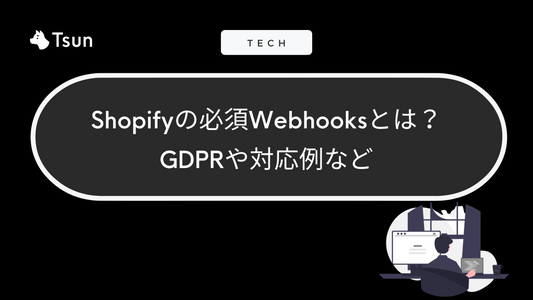<Shopify事業者のインタビュー特集>今年5周年を迎えた指輪型決済端末・EVERING(エブリング)。通信キャリアを始めとしたさまざまなパートナーとの連携や万博への協賛など、潤沢な広告費に頼らず、独自のアプローチでユーザーとの接点をつくり、未知の体験を少しずつ世の中に届けてきました。
市場に明確な正解がない時代において、どんな視点でブランドは価値を定義し、どう尖っていくべきなのか。インタビュー後編では、EVERINGが見据えるこれからの展望と、ブランドのあり方について、株式会社EVERING代表取締役 川田健さんにお話を伺いました。

(株式会社EVERING 代表取締役 川田健さん)
インタビュー前編はこちらからご覧ください。
【ストアインタビュー前編】未知のEC体験を届ける指輪型決済 EVERING|株式会社EVERING 川田 健さん
つながりで広がるブランド認知。5周年で見えた現在地

(指輪を象徴するEVERINGのブランドロゴ)
ーー コロナ禍以降、オンラインでも無数のブランドが立ち上がっては消えていった中、ゼロから市場を作り出し5周年を迎えられたことは本当にすばらしいことだと思います。この5年で変化させてきたことがあれば教えてください。
川田健さん(以下川田さん) メッセージやクリエイティブはブランドの軸に合わせて何回か大きく変えてきました。しかしそれ以上に、さまざまなパートナーの方々とつながりながら、EVERINGというブランドを広げてきた5年間でした。
1年前にはNTTドコモさんと業務提携して、ドコモショップで販売を開始したことだったり、今年の4月からはauショップでも全国展開が始まりましたし、万博にもゴールドパートナーとしてリングを無償提供させていただきました。
まだまだ小さな会社なので、大手企業の様に莫大なマーケティング資金を投入できるわけではないので、そういう一つひとつの関係性の積み重ねがあったからこそ、結果としてEVERINGの認知につながってきたと思います。
ーー 顧客やパートナーの方々との関係性が今につながっているのですね。
川田さん EVERINGという名前には、「Everything×Ring=すべてにつながるリング」という意味が込められています。機能としてのリングであると同時に、パートナーとのつながりも象徴するコンセプトです。
まだ表には出ていないパートナーシップもたくさんあります。どれだけ表に見えるかは関係なく、つながりを大事にしてきました。

(指輪型の決済端末 EVERING)
伝える体験に合わせて変える、チャネル戦略
川田さん この5年間、いろんな売り方にチャレンジしてきました。商品の販売ではなく、最新技術だけを見せるようなショールーム形式のショップや、百貨店での販売にもトライしましたし、最近では全国展開している家電量販店とも取引を再開しています。
EVERINGは、ふらっと来てパッと買うような商材ではなく、説明が必要な商品です。腰を据えて話を聞いてもらえる場所でこそ伝えたいことが届く商品なので、キャリアショップとのパートナーシップはすごく合っていました。
とはいえ、Amazonでパッと買う人もいるし、自社サイトをじっくり読んでから買う方もいらっしゃいます。「近くのドコモショップでサイズだけ測ってみよう」と店舗に行く方もいます。
そういう複層的な動線が機能していて、結果的にどこかで買える状態を作るという意味で、いまはキャリアショップさんがコアな販売チャネルになっています。
世代もチャネルも越えて広がる、EVERINGの届け方

(EVERINGを端末にかざすだけで決済が完了)
ーー キャッシュレス化が進み、決済方法もこの5年でずいぶん多様化したように思いますが、EVERINGのユーザー層にも変化はありましたか?
川田さん ユーザー層は確実に広がってきた実感があります。
もともとは30〜40代で、ガジェットが好きで面白いものや新しいものを試して、「便利だし、自分の生活に合ってる」と感じて買ってくださるような方々がメインユーザーでした。
そこから、ドコモさんとの連携が始まったことで、一気に年齢層が広がりました。30代半ばぐらいのお子さんがいる世代から、60代から70代まで、幅広く来られます。どちらかというとITや金融に保守的で、ネットで検索して自分で調べるよりも誰かに聞きながら決めたいタイプの方が多いです。
ーー 一見、未知の決済端末には手を出しにくい層というイメージがありましたが、それは面白い広がりですね。
川田さん EVERINGは、事前に専用アプリでセットアップをしてしまえば、日常の利用時にスマホやアプリを操作する必要はありません。決済時にBluetoothなどでスマホと接続する必要もなく、リングをかざすだけで完了します。プリペイド方式のため「気づいたら使いすぎていた」という心配も少なく、万が一リングを落としてしまった場合も、アプリからワンタップで利用を停止できます。
今までキャッシュレスを使ってこなかった方が、安心して使えるという文脈でEVERINGで決済する。そんなケースが増えています。

(シンプルでわかりやすいUI設計のEVERINGアプリ)
―― キャッシュレスやオンラインに抵抗感がある方に、オフラインならではで寄り添って信頼関係を築いているのですね。最近は、オンラインとオフラインの導線をどうつなぐかに悩むブランドも多い中で、チャネルやユーザー層ごとに最適な伝え方を使いわけていらっしゃるのはすごく新しい視点でした。
川田さん ありがとうございます。実際、ECでは「安心」という文脈は打ち出していません。それはあくまでキャリアショップでの販売時に重視している軸です。
他にも若い世代に向けて、「NEON BUZZ」という低価格の若者向けの新しいラインを立ち上げました。ファッションやストリートに寄せた商品を展開したかったんです。
決済を越えて広がる、EVERINGの未来設計
―― この先の未来で、川田さんご自身やEVERINGが見据えてらっしゃる目標を伺えますか?
川田さん 「Everything×Ring=すべてにつながるリング」という構想を、より機能面でもサービス面でも拡大していくことが今後も変わらない戦略になると思います。
決済としてのチャネルだけではなくて、EVERINGで家の鍵を開け閉めできたり、社員証システムの一部で使っていただいていたりしています。
もうひとつは、いろいろなファンコミュニティとつながることです。
スポーツやエンタメだったり、チームのようなコミュニティと組んで、EVERINGを専用にデザインして、コミュニティを通じてさまざまな体験をご提供していく。世の中のさまざまな人たちが、さまざまな形でEVERINGを使ってつながれる範囲がまだまだあると思っています。

(決済端末以外の可能性も広がっていく)
刺さる価値を磨く時代に、尖ることを恐れないブランドへ
決済端末とD2Cという、従来の枠組みでは捉えきれない領域を開拓してきたEVERING。機能や利便性だけでなく、ブランドとして何を届けていくのかに向き合ってきました。明確な正解が存在しない今の時代に、事業者が向き合うべき価値とは。ニッチで尖ったコンセプトを持つことの意味と、ファンとの接点をどう築いていくか。ブランドづくりに求められる視点を伺いました。
―― 今、ノーコードで使えるECカートやプラットフォームの普及により、個人や小さなチームでもブランドを立ち上げやすくなっています。そうした環境の中で、これからのブランドやEC事業者に必要な視点とはどのようなものでしょうか?
川田さん 今はさまざまな価値や考え方が生まれている時代だと思っています。
決済に限らず、何か一つの機能を提供するにしても、そこにはさまざまな側面があります。その最適解を探るうえで、最大公約数を取りにいってしまうと、どうしても全体がぼやけてしまいます。なので、今の時代に合っているのは、一部の人に究極的に刺さるものではないでしょうか。
合わない人には見向きもされないかもしれない。でも、刺さる人には深く響く。そういうブランドやサービスが、これからますます増えていくべきですし、それができる時代になってきていると思います。
Shopifyというプラットフォームの中で、メーカーだけではなくサービスやコンテンツもいろいろな立ち位置が作れるようになりました。そうした多様性の中でこそユーザーは自分に合ったものを選べるようになる。それはすごく健全で幸せな状況だと思うんです。
必ずしも王道だけではなく、むしろニッチで尖ったものがもっといろんなジャンルで出てきたら、面白い時代になるのではないかと思います。
EVERINGが描く在り方は、決済という機能を超えて、体験そのものに価値を見出す姿勢にあります。未知のプロダクトだからこそ丁寧に届け、使い心地や導線設計に細やかな気配りを重ねる。誰かの生活に気持ちよく馴染む体験をどうつくるかを起点に、パートナーとのつながりを大切にブランドを育ててきました。
王道でなくてもいい。だからこそ、尖っていける。 EVERINGの見据える先には、決済だけにとどまらない、テクノロジーと生活がつながる、ワクワクするような未来のかたちが浮かび上がっていました。