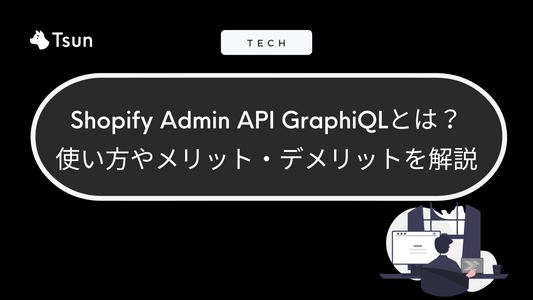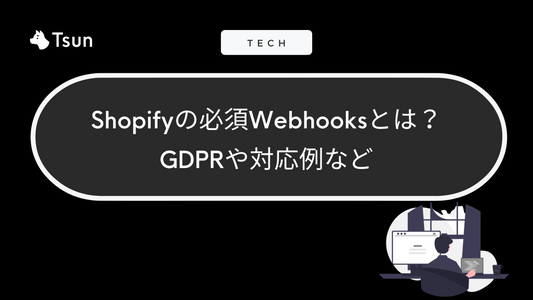<Shopify事業者のインタビュー特集>「指輪型の決済端末」という未知の体験を届けるプロダクトを展開するD2Cブランド・EVERING(エブリング)。
競合のいない独自のプロダクトだからこそ、欠かせないのが丁寧な機能説明と使用体験の設計。単なるEC構築にとどまらず、「どう見せて、どう伝え、理解してもらうか」というブランドの思想が、一貫して貫かれています。
2021年のサービス開始から約5年。オンラインとオフラインを横断しながらユーザーとの接点を築き、気持ちよさや理解しやすさといった価値を重視してきました。テクノロジー、金融、そしてデザインが交差するプロダクトを、どのようにECで表現し届けてきたのか。株式会社EVERING 代表取締役 川田健さんにお話を伺いました。

株式会社EVERING 代表取締役 川田健さん
伝わらない前提から始める、EVERINGの構造と思考

(指輪型決済端末 EVERING)
ーー EVERINGとはどのようなプロダクトなのでしょうか?
川田健さん(以下川田さん) EVERING(エブリング)は決済機能を持った指輪型のスマートデバイスです。充電不要で、アプリ操作も最小限。装着してかざすだけで支払いが完了します。世の中にまだない設計を形にし、誰もが直感的に体験できることを目指し、EVERINGをつくりました。
市場に存在しない商品は、便利そうというだけでは選ばれません。だからこそ私たちは、機能ではなく体験そのものにこだわり、「どう使われるか」「どう感じられるか」といった体験の部分に深くこだわっています。
決済体験に寄り添う、気配りを大事にするブランド
川田さん ユーザーの使い心地も含めて提供しないといけない。今で言えば、世界観も含めてしっかりと伝えていくことが大事なんです。
私たちが重視しているのは「気配りのある体験」です。カスタマーサポートはあえて電話窓口は設けず、メールでの対応をさせて頂いております。リングの不具合なのか、お店の端末の問題なのか、システムの問題なのか、などまずは事実を確認・記録・分析し、それに対して最適な解をお届けするということを心がけております。決済という少し緊張感のある場面だからこそ、安心感やスムーズさ、温度感がすごく大事だと思っています。
アプリのUIも同じです。多機能化するのではなく、誰でも直感的に使えるシンプルさを徹底しています。
ーー 「わかってもらえた」という安心感は、決済端末というセンシティブな商品の特性とも関係していそうですね。
川田さん 感覚的に使い方がわかるように、アプリもすごくシンプルにしています。決済機能のあるアプリでも、無数のボタンが並んでいて、正直どこを押せばいいかわからないものがあります。
私達は、それをもっとシンプルに感覚的にわかるようにしています。

(直感的に操作がしやすいシンプルなアプリ画面)
ゼロイチで挑む、前例のないプロダクトの伝え方
ーー 市場にいままでなかったプロダクトを立ち上げたことで、最も苦労された点はどんなことでしょうか?
川田さん 立ち上げから今に至るまで一番の課題は、説明しなければ伝わらない商材であることです。
たとえば、Visaのタッチ決済をかざすだけでできるという行為自体が、まだ100%浸透していません。その段階を飛び越えて、いきなり「Visaのタッチ決済が搭載されたリングです。プリペイド式で安心ですよ。充電も不要です。」と言っても、知らない方には疑問符が3つも4つも浮かんでしまう。だからこそ、まずは認知もセットで取っていかなければなりません。

(スーパーでの買い物など、さまざまなシーンの決済で利用できる)
川田さん 「スマートリング」という言葉自体も、創業当時はまだ定着していませんでした。今でも、「スマートリング=ヘルスケア」という認識が強く、決済リングとしての存在を理解してもらう必要もあります。
EVERINGは「Visaのプリペイドカード」として発行しています。お手持ちのクレジットカードからチャージして使う、という方式です。「Visaしかチャージできません」といった制限は設けておらず、EVERINGのリングと連携するアプリでは、Visa、Mastercard、JCB、American Express、Diners Clubと、ほとんどのカードでチャージができるように設計しています。
プロダクトの課題を解決できるShopifyという選択
EVERINGのように、多くの選択肢や条件を踏まえて購入してもらうプロダクトにとって、ECカートでもユーザーが迷わず進める導線設計が求められます。そうした複雑な要件を満たすために選ばれたのが、柔軟性と機動力に優れたShopifyでした。
プロダクトの特性に合わせて情報や構成をすばやく変えられること、拡張性の高いアプリが揃っていることなどが選定理由の背景にありました。

(EVERINGのECサイト)
ーー ECカートにShopifyを選んだ理由はなんですか?
川田さん EVERINGには、決済型リングという認知がない中でユーザーが感覚的に理解して買っていただける動線を作る必要があるという、独自の課題があります。
たとえば購入時には、一括購入か継続支払いか、リングのサイズ選びや紛失保証の有無、刻印の有無など、決めて頂かないといけないことが多いです。
そういった設計を実現するには、オプションの多さや融通が利くことが重要でした。アプリが豊富に展開されていたり、必要に応じて自分たちでコーディングできる柔軟性があるのが、Shopifyを選んだ一番の理由です。
ーー プロダクトの特性上、ユーザー導線を設計するためにも、Shopifyの柔軟性が適していたのですね。
川田さん EVERINGは商品自体の理解から始まるからこそ、どういう素材や画像、クリエイティブを出せばより魅力的に伝わるか、そういったテストを今も引き続きやり続けています。そして、必要があればどんどん入れ替えていかなきゃいけないフェーズです。
そのたびに、開発パートナーに修正をお願いしていると機動力がなくなってしまうので、Shopifyのフレキシブルな点もEVERINGの思想と直結しています。

(新しいブランドシリーズ NEON BUZZ)
ーー Shopifyのサイトは現在どのように運用されていますか?
川田さん 今のサイトはフルスクラッチで作成したものではなく、基本的にはテーマベースで構築しています。商品数やバリエーションがあるので、UIも見やすく、回遊しやすいように工夫しています。作り込んで運用が重くなるよりは、将来的な改修や展開も見据えて、ある程度やりやすさを優先しました。
Shopifyはある程度知見があれば誰でも動かせるようになるところもすごく良いです。最初の設計やこだわる部分はしっかり作り込む必要はありますが、日々の運用で「文言を変えたい」とか「バナーを差し替えたい」とか、そういうところがスムーズにできるのは助かってますね。
Shopifyはグローバルでも導入企業が多いですし、対応しているテーマやアプリもすごく多いので、運用面も含めてEVERINGにとってすごくフィットした選択肢だったと思います。
プロダクトの思想を形にするアプリの選択
ーー EVERINGのサイトでは弊社アプリ「RuffRuff 注文制限」も使っていただいていますが、使用感はいかがでしょうか。
川田さん EVERINGは、現時点ではまだ、1ユーザー当たり一つまでしか購入ができない仕組みになっているので、一人の方が複数リングを持つことができません。なので、「一人一個」というところに、まず制限を設ける必要がありました。
さまざまなアプリがある中で、実際アプリをいれてみて、RuffRuffさんが一番使い勝手が良いなと感じているところです。コストパフォーマンスもしかり、制限できるカスタマイズの幅広さも柔軟だなと感じています。
ーー ありがとうございます。「一人一個」の制限以外にも、紛失交換保証や刻印などのオプションはリングと一緒じゃないと購入できないような同梱制限もされていますが、この機能は他のアプリではなかなか実現しづらいので、EVERINGで実現したいことにマッチしたのではと思います。

(プラン、色、サイズと、必須選択肢がわかりやすく表示されている)
EC設計より先にある「体験を届ける」思想へ
ーー ここまでのお話からも、EVERING独自の課題である、理解してもらうことや選んでもらうことへの向き合い方へのこだわりがすごく伝わりました。
川田さん 根本的には、ECプラットフォーム構造そのものではなく、リングで決済したときの気持ちよさをどう伝えるかを大事にしています。
EVERINGの場合、いろんな選択肢を選びながら買っていただく商品なので、ECサイトにおいても、シンプルに感覚的にわかりやすく説明できるような構造にしました。
表現の仕方そのものという意味では、Shopifyじゃなきゃいけないというより、EVERINGの特性がShopifyの柔軟性と相性がよかったという形です。
もちろん、まだまだ全然100点ではなくて、自分たちとしてももっと改善していきたい部分はあります。使い心地や気持ちよさを大事にするブランドであることは、変わらず大切にしていきたいですね。
説明しなければ伝わらない商品で、ユーザー体験をどうデザインするか。EVERINGはその問いに、創業以来、挑み続けてきました。
説明のための導線設計、選択肢の提示方法、クリエイティブの最適化。そして、それらを支える柔軟性と機動力を備えたEC基盤。その設計思想の延長線上に、ShopifyによるEC構築があり、ブランドの届け方がありました。
プロダクトの個性に寄り添いながら、表現は柔軟に変わっていく。EVERINGは、テクノロジーの進化とともに体験設計の新たな可能性を指し示しています。
インタビュー後編では、EVERINGが見据えるこれからの展望と、ブランドのあり方について伺います。