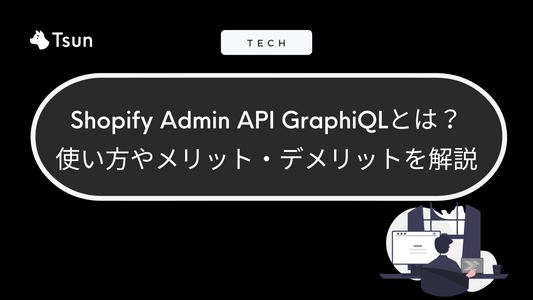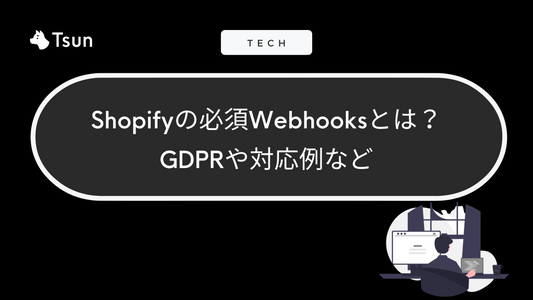Shopify事業者のインタビュー特集。
広島県東広島市に本社を構える「住田屋」は、県内に8店舗を展開する酒販店。地域に根ざした店づくりを大切にしながらも、近年はオンラインストアを中心に全国のファンへと魅力を届けています。
そのオンラインストアの立ち上げと運営を一手に担ってきたのが、オンラインストア店長の廣中ようこさんです。オンラインストアの可能性に気づいた廣中さんは、当時まだ社内に知見のなかったECに自ら取り組み、独自の方法で顧客との関係を築いていきます。
地元の人に長年愛されてきた接客の姿勢を、どうやってオンラインストアでも再現できるか。その問いに向き合い続けてきた廣中さんの歩みとShopifyサイトやSNS戦略を、前編・後編の二部にわたってたどっていきます。

(住田屋オンラインストア店長 廣中ようこさん)
15歳から酒販の現場へ。ゼロから挑んだEC立ち上げストーリー
住田屋オンラインストアの立ち上げ人であり、現在は店長として運営を手がけている廣中ようこさん。地元・広島の酒販店でアルバイトとして働き始めたのは、なんと15歳のときでした。自らの目で現場を見て体を動かしながら、酒販の面白さに惹かれていったといいます。
自社の状況からECの可能性に気づき、店頭での経験を活かしながらゼロから学び住田屋オンラインストアを立ち上げました。その背景には、誰かに言われたからではなく、必要だと感じたからやるという廣中さんのまっすぐな行動力があります。
ーー まずはどういった経緯で酒屋に入られ、今のオンラインストア店長になられたのでしょうか。
廣中ようこさん(以下廣中さん) 酒屋に入ったのは、実は15歳のアルバイトなんですよ。友達から「アルバイトしない?」と誘われて、わけもわからず行った先がたまたま酒屋だったんです。そのままずっとバイトを続けて、22歳ぐらいのときに「この酒屋さん、面白そうだな」と思って、そのまま就職しました。
ーー そこから店長になられたのはいつ頃だったのでしょうか?
廣中さん 就職して2年ぐらい経った頃に実店舗の店長になりました。ただ、若かったので本当に何もできなくて。包装もできないし、お客さんに怒られるし、すごく挫折しました。「このままじゃダメだな」と思って、将来に向けて何か種をまいておかなきゃと。それで、自腹で30万円かけてパソコン教室のアビバに通ったんです。
2年ぐらい通って、最低限パソコンができるようになってきて。店内POPを作ったり、当時は会社にホームページもなかったので、「じゃあ自分で作ってみよう」と。YouTubeなどを見ながら、独学で作りました。
ーー そこから初めてのECに取り組まれたんですね。
廣中さん そうです。ECの決済方法はカード手数料で赤字になるからクレジットカード払いは会社の許可がでずに銀行振込だけ。そんな状態で自社ECを始めたんですけど、まあ売れませんでしたね。3年間で1件も売れませんでした(笑)。
固定費が毎月かかっていたこともあって、「もう続けるのは難しいかもしれません」と伝えたとき、上司にはすごく怒られました。「なぜそこであきらめるんだ」と。でもその言葉があってとても悔しかったから、後に再び「やるしかない」と覚悟が決まりました。
挫折から、ShopifyでEC再挑戦へ
ーー 一度挫折をしてからどのようにしてECに再挑戦されたんですか?
廣中さん ECの再挑戦について会社から何か言われたことは一度もないです。うちは当時7店舗あって、地元ではすごく支持されていたんです。この倉庫の数は酒販業者としては絶対強みだと思って、やっぱり絶対にECを立ち上げようと思っていて。
その当時はホームページも古くなっていたので、ちゃんとやらなきゃとデジタルハリウッドに通いました。ただ、通ってすぐにコードは好きじゃないなと気づきました。でも、クリエイティブを作るのは得意だなと思ってたら、先生に「Shopifyならノーコードでいけるよ」と言われて、これだと。楽天とかも検討したけど、モールに出すと価格が上がってお客様にメリットがないのでやらないと決めましたね。Shopifyでサイトを作ることに迷いはなかったです。
ーー Shopifyでオンラインサイトを立ち上げてから、売上はでたのでしょうか。
廣中さん 初月の売上が3万円。それがもう、忘れられないですね。Shopifyは売れると「チャリン」って音が鳴るんですけど、それが鳴った瞬間、周りの人たちが「えっ!? 売れた!?」って(笑)。

(住田屋オンラインストア)
初月3万円からの快進撃。最初のヒット商品はシャンパンだった
ーー 本格的にECに再挑戦してからは順調に伸びていったのでしょうか?
廣中さん はい、初月が3万円だったんですけど、翌月8万円、その次は15万円と順調に伸びていきました。とにかく一生懸命やってました。失敗してもいいから、とにかく行動しないと何も生まれないって思って。
いろんな施策を試したんですけど、最初に当たったのは、シャンパーニュで、すごく売れたんですよ。当時、コロナの影響でシャンパンが日本に入ってこなくなって、都会のクラブや飲食店では品薄になっていたんです。でも、うちは田舎であまり出ないので在庫がたくさんあった。そのとき、都会と田舎ではタイムラグがあり、チャンスがあることにも気づいたんです。
ーー そのチャンスを掴むために何か特別な営業活動をされたんですか?
廣中さん いえ、最初の1年半くらいは広告費ゼロだったんですよ。だから、こっちから何か発信するってことができなかったんです。つまり、検索したときにうちのサイトが出てくるかどうかだけが勝負でした。たまたま、在庫がゼロのところが多い中でうちにだけ在庫がある、っていう状況で見つけてもらえたんですよ。
ーー いわゆるSEO的な検索対策はされていたのですか?
廣中さん 当時は検索対策をぜんぶ無視してました。あえてやらなかったというより、正直、めんどくさかった(笑)。URLハンドルも作ったまま日本語で出してましたし、商品登録や撮影も全部自分一人でやっていたので、細かいところにこだわって商品を出せないよりも、まずは商品をどんどん出品することを優先して、細かいところは省いていました。
ーー 今社内のなかでECの売上比率はどれくらいなのでしょうか。
廣中さん 比率でいうと、まだまだ実店舗の方が大きいですね。実店舗は一店舗ごとの年商が数億円規模に達する一方で、自社ECはそれに比べるとまだ発展途上の段階です。でも、去年の12月にAmazonを始めて、広告費を使わなくてもそこでもかなり伸びてきていますね。
ーー 広告費ゼロでその初動はすごいですね!
廣中さん 戦い方としては、徹底的に薄利多売です。利幅はとても少ないんですけど、たとえば1億売って粗利が10%でも、1000万は残るじゃないですか。すでに人員も施設もあってリソースは揃っている状態。今の体制で回せるなら、薄利多売でいいと思ってやっています。

(酒屋ならではの品揃えと倉庫機能が強み)
「売上は自分たちでも作れる」女性だけで挑む酒販の現場
現在の住田屋オンラインストアの業務を支えているのは、全員女性で構成されたチーム。発送から対応、すべての現場を女性メンバーで担っているこの体制は、重たい荷物を扱うことも多い酒販業界の中では珍しいスタイルです。背景には、男性中心だった社内カルチャーへの違和感、そして女性だけでも売上は作れるという手応え。
「女性だからこそ気づけること、できることがある」そう語る廣中さんは、じつは元男性。自身が当事者であるからこそ感じてきた偏見や戸惑いへの理解、そしてそれを超えてきた強さがあります。丁寧さと気づきが行き届いた体制の裏には、廣中さん自身のチーム組成に対するこだわりがありました。
ーー 現在、オンラインストアのチームは全員女性とお聞きしています。
廣中さん はい。と言いながら、私は元は男性なんですよ。だから、オチとしては「チームは全員女性でやってます。あ、店長は…」みたいな話で(笑)でも、実際に発送含めて、すべて女性チームで回しています。
ーー 入社当初から、今のような雰囲気の廣中さんだったんですか?
廣中さん いえいえ、最初はサッカー少年でしたよ(笑)。会社で店長になったあとぐらいに変わっていきました。当時は「オカマ店長で成り立つわけがない」と本気で思ってましたし、辞めるしかないと思ってた時期もありました。
ーー そこからどう振り切られていったんでしょう?
廣中さん だんだん、近所のおばちゃんたちが「なんか、あんた綺麗になったね」って言ってくれるようになって。町でも話題になって、「あの人がいる店らしいよ」って見に来てくれたり。そうなってくると、これは個性として出しても大丈夫だ、むしろ武器になるなと思えて。実店舗でも、誰かに会えば必ず「店長、なにやってるの?」って言われます。だったらこの感じをECでもそのまま出していこうと思ったんです。
ーー 女性だけのチームというのは、酒屋という業種では異色なことなのでしょうか?
廣中さん そうですね。お酒は重いので、昔から男がいないと回らないとか、女性はレジ担当で売上は作れないといった風潮があったんですよ。でも、その中で女性たちはずっとコンプレックスを感じていて。だから女性だけで売上を作った時は、本当に嬉しかったです。
オンラインサイトのお客様からは、丁寧だったとレビューで言っていただくことも多くて。チーム内では、たとえば「箱を開けたときにここにおまけがあると見える」とか、「この商品はここが汚れやすいからビニールを巻いておこう」とか、そういう話が自然と出てくるんです。
私が丁寧にしてねとチーム内に言ったわけじゃなくて、勝手にそういう工夫が生まれてくる。男性にお願いしたこともあったんですけど、やっぱりどこか梱包が荒くなってしまって。それで、もう女性だけでやろうとなりました。

(ご自身のキャラクターやアイデンティティを最大の強みと差別化に変えている廣中さん)
ぬくもり感のあるECの作り方
ーー 廣中さんご自身の言葉で「ぬくもりのあるEC」とおっしゃってましたが、廣中さんが考えるECにおけるぬくもり感とはなんでしょう?
廣中さん 人間ですね。相手に人がいると感じられること、それが一番のぬくもりなんじゃないかなと思っています。そのひとつとして、問い合わせの返信の名前は全部、廣中ようこで出しています。メールも、チャットも、公式LINEも、もう全部私です。
だからXでも「ぜんぶ私です!」って言っちゃう(笑)。だって、本当にそうなので。
ーー もともと女性だけの体制を目指していたんですか?
廣中さん いえ、自然とそうなっていったんです。ただ今は「女性かつ楽しいと思ってくれる人」に声をかけています。得意で好きで楽しいと思える人たちとやるのが一番いいですね。これからも女性だけでやった方が、もっといいチームが作れるんじゃないかと思ってます。
ーー 慣習とは異なるチーム編成は、社内ではどういうふうに見られているんでしょうか?
廣中さん 当初は「何を始めたんだろう?」という空気もありましたが、最近では「何かお手伝いできることがあれば」と声をかけてもらえることも増えてきました(笑)。

(店頭のディスプレイにも、販売側の姿が感じられる一工夫あり)
「誰から買うか」で選ばれる店へ。“究極の属人化”という選択
ーー 酒屋はコモディティ商品をセレクトして販売するという形です。「住田屋さん以外でも買えるもの」をあえて住田屋さんで買われている理由は、どこにあるとお考えですか?
廣中さん 23歳の頃からずっとお酒のライバルはなんだろうと考えていたんですが、隣の酒屋じゃないんです。お酒を買う人って「どうなりたいか?」を考えたとき、「ストレス発散したい」とか「ハッピーになりたい」とか、そういうことだと思ったんですね。そうすると、「今週の日曜はお酒を飲むか、それとも遊園地に行くか」みたいな、選択肢の中のひとつにお酒があるということなんです。だから「お酒はエンターテインメントとして戦わないといけない」と思ってて。
おっしゃる通り、どこでも売ってる商品なんですよ。だから、どの商品を売るかじゃなくて、「誰から買えば、もっと幸せになれるか」にこだわっていたんです。で、そこで、私のオカマキャラがちょうど生きてきたんです。
ーー 廣中さんご自身のXアカウントはフォロワー3万人超えと、廣中さんの影響力や販売力も大きいことが伺えます。これは戦略的に狙ってやってこられたんですか?
廣中さん それが全然狙ってなかったんですよ(笑)
自社ECを立ち上げた当時、ウイスキーブームが来ていてそれまで普通に仕入れていたウイスキーが、急に世界的に価格が上がったんですね。そこで私がInstagramでちょっと発信したら、全店舗に問い合わせがたくさん来るようになって。全部先輩の店舗なので、すごく怒られたんですよ。「なんで最初に言わないの?」って。
そこで「ああ、こういうことが起きるんだ」と知りました。でも、これから先いちいち全部報告してられない。住田屋として打ち出すからお客さんから問い合わせが来るのだったら、廣中ようこを全面に出して、私にしか問い合わせが来ないようにしようと思ったんですよ。
それで、X経由でしか施策をしないので問い合わせは全部私にくださいと打ち出したら、私のキャラが相まってXのフォロワーがどんどん伸び出したんです。
ーー なるほど!一般的にショップを成長させるためにはなるべく属人化を避けようとするかと思いますが、むしろ究極的に属人化させていくことで売れてるわけなんですね。
廣中さん そうですね。良かったのは広告費に頼れないってことだったんです。広告費がない中で自分にできることは何かと考えたら、自分が露出することだったり、ご購入いただいた方には必ず丁寧に対応するとか、そういったことしかなかった。でも、それが結果的に良かったのだと思います。だから今も、広告費は月3万円しか使ってないんですよ。
大きな広告予算も、特別な経歴もないところから、自分の言葉と行動だけでゼロからECを立ち上げ、売上を積み上げてきた住田屋オンラインストア店長の廣中ようこさん。
廣中さんの戦い方は、ただ安く売ることではなく、誰からお酒を買えればお客様は幸せかを徹底的に考え抜くこと。そしてお酒というコモディティ商品を、遊園地や映画と同じ“エンターテインメント”の土俵に上げていくことでした。
誰でも売れるものを、誰から買いたいと思わせるか。その問いに対する廣中さんなりの答えが、究極の属人化という戦略です。ブランドの強みは「人」。届け方の核は「発信」。その両方をまっすぐに突き詰めてきた廣中さんの歩みは、いまの住田屋オンラインストアの土台をつくっています。
後編では、X(旧Twitter)を中心としたSNS戦略や、Shopify運営について、さらに深く伺っていきます。