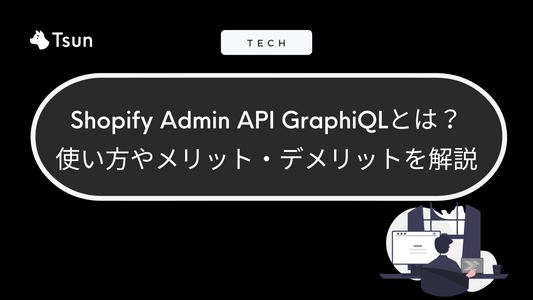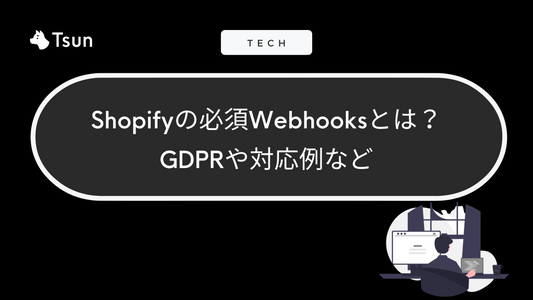Shopify事業者のインタビュー特集。
広島県東広島市に本店を構え8店舗を展開する酒販店「住田屋」。そのオンラインストア運営を一手に担うのが店長の廣中ようこさん。
SNSでは、「言い過ぎない程度に、ちょっと言う」「お酒の話ばかりにならないように意識する」。一見ラフで親しみやすい発信の裏には、酒屋という業態をエンタメの文脈に接続し、楽しいお買い物体験を届けるための、細やかな工夫が詰まっています。
ぬくもりECという言葉は、廣中さんが手探りで積み重ねてこられた日々のコミュニケーションの結晶です。そしてその在り方は、属人化を恐れず自分らしさを前面に出すからこそ実現できるものでもあります。
本後編では、Xを中心としたSNSでの発信戦略、Shopifyを使った運営とこれからについて、さらに深くお話を伺います。

(住田屋オンラインストア店長 廣中ようこさん)
インタビュー前編はこちらからご覧ください。 【ストアインタビュー前編】「誰から買うか」で選ばれる店へ 属人化×エンタメ戦略で挑む酒販EC
属人化を信頼に変えて、選ばれるECをつくる
ーー 今EC業界では、特にAmazonなどは薄利多売の傾向が顕著だと思います。お酒等のコモディティ商品を扱う酒屋では、価格優位性が重要視されやすい印象がありますが、廣中さんはECにおいて、どのような価値を重視されているのでしょうか?
廣中ようこさん(以下廣中さん) そこは店長時代の経験が活きていると思うのですが、お客さまにとってのいちばんのベネフィットは、やっぱり人によるんですよ。金額が重要な方もいれば、そうでない方もいる。たとえば、Amazonより数百円高くても、住田屋のサイトで買った方が安心と思ってくださる方もいて。
うちでは、オンラインで購入された場合、必ず何かしらのおまけをつけているんです。たとえば小さな酒グッズだったり、ちょっとした冊子だったり。開けたときに商品が届いただけじゃないというワクワク感を届けたいなと思っていて。そういったちょっとした嬉しさや、お酒にまつわるストーリーから購入してくれる方も多いんですよね。
どの商品も同じように届けるのではなくて、今売りたいものに応じて伝え方も変えています。
ーー 商品が何百点もある中で、それぞれに思いを込めて届け方を変えるのはすごいことですね。
廣中さん いえいえ、大層なことはしていなくて(笑)。商品登録のときに「あ、これは面白いな」と思ったらちょっと工夫するくらいです。
ーー 今後、オンラインサイトの売上をさらに伸ばしていくために、こだわりたいことやブランディングで気をつけていることはありますか?
廣中さん 特別なこだわりはなく、今のやり方が一番しっくりきてるから続けているというだけですね。もし一緒にやってくれているメンバーが同じような熱量や「お客さまに喜んでもらいたいという気持ちを持ってくれているなら、どんどん前に出てほしいと思ってます。

(ご予約いただいた方への特典など、お客様に喜んでいただくためのさまざまなアイディア)
会話がマーケティングになる時代のSNS戦略
ーー 新商品の販売情報などはメルマガのようなある種クローズドな場ではなく、すべてXで発信されているのですか?
廣中さん そうですね。Xのいちばんいいところは、会話が全部オープンなことだと思うんです。たとえば「このお酒、度数は何度ですか?」と聞かれたら、「15度ですよ」って返すんですけど、そこに「こういう造り方で」「こういうおつまみと合いますよ」って情報を加えるんです。
これって一見すると1対1のやりとりだけど、フォロワーさん全員が見てるから、実は1対複数の接客になってるんですよ。「この前のやりとりを見て、気になって買いました」って方、結構いらっしゃいます。
ーー 廣中さんのXを見ていても、本当にすべてのリプライに丁寧に返してらっしゃる印象があります。あれは意識して戦略としてやってるんでしょうか?
廣中さん 何かを戦略的にやったことって一切ないんですよ。Xを始める前は、SNSはむしろ苦手で。実店舗の店長をしてた頃、インターネット掲示板に「オカマ店長がいる」って書かれてたのを知って、よくわからなかったから自分の名前で全部返事してたんです。そうしたら「本人出てきた!」ってなって。でも、そこに悪口はなかったので全部返していたんです。
そのノリのまんま、Xでも来たら返すっていうのが習慣になっています。メッセージをいただけるのが本当にうれしくて、できるだけお返事しているんですが、最近は少しずつ追いつかなくなってきていて…。でも、全部しっかり読ませていただいています!

(廣中さんの人柄を感じられるXプロフィール)
ーー リアルでの接客スタイルが、そのままSNSにも反映されてるんですね。
廣中さん 店頭でも昔からよく話しかけられてたので、その空気感が出てるのかなと。結局は自分が笑っていたいからやってるんですよ。私、ヘラヘラ笑うのが好きなんですけど、それって周りが笑ってくれないとできないじゃないですか。だから、お客さんにも笑ってほしいんですよね。
ーー ご自身の中で、発信するうえでのルールのようなものはありますか?
廣中さん 絶対にネガティブなことは言わない。それは決めてます。「今日しんどかった」とか「嫌なことがあった」とか、そういうのは出さないようにしています。
私が掲げているのは「みんなで日本中をお酒で笑顔にする」ということなので、自分も、見てる人たちも笑ってほしいんです。そのためにはポジティブであることが何より大事なんですよね。
テクニックではなく普通の会話で、Xを広がる導線に
ーー 今のXの運用は、重要なマーケティング手段になっているという理解でいいでしょうか?
廣中さん 認知を取るという意味では重要視しています。ただ、最近はちょっとずつアルゴリズムの傾きが変わってきてて。リンクを貼ると、以前よりも明らかに拡散されにくくなっています。だから「これ買ってください!」って商品リンクを載せても、インプレッションが全然伸びなくて。
今はなるべくリンクを貼らない、画像をつけるとか、あとは、フォロワーさんとやりとりしてる投稿はやっぱり伸びやすい。
でも、これってテクニックじゃなくて、要は「人と人との普通の会話」が見える形になってるかどうかだと思うんですよ。だからあんまり、アルゴリズムをハックしたいとかは思ってないんです。
ーー その普通の会話を見せられるのが廣中さんの強みなんですね。
廣中さん たとえば普段の生活でシンプルに友達が多いとか、知り合いが多いとか、好かれる人は、もうそのままを出した方がいいと思うんですよ。だって、その姿で好かれてるんだから。
逆に「普段そんなに友達いない」とか「敵が多い人」は、そのまま出しちゃいけなくて、ちょっと違うキャラを演じてみるとか。
ーー それは面白い視点ですね。廣中さんは、SNSで見てるまんまが自分そのものという感じですか?
廣中さん そうですね。だから、冗談や下ネタを言ったりします。今となっては、いろんな会社さんやメーカーさん、真面目な人たちにも見られるようになってるから、やっぱり変なこと言うとリスクはあるなって思った時期もあったんです。
でも、Xを見てて「酒屋さんが今日のお酒のスペックは○○です」って言ってても、面白くないじゃないですか。結局、X開く時はお酒のスペックが知りたいわけじゃなくて、「なんか面白いことないかな〜」って来るわけじゃないですか。酒屋さんがお酒のことばっかりだけの専門家になっちゃうと見られないと思うんですよね。
やっぱり私も、他のジャンルの専門家の人で専門的なことばっかり書いてると、そんなに見なくなっちゃうし。だから私は、普通に思ったことを発信した方が、他の酒屋さんにはできないし、自分のキャラにも合ってるなと思っています。

(お酒のことだけにとどまらず、クスリと笑ってしまうような投稿も)
スピードが検索上位をつくる、住田屋流SEO戦略
ーー 廣中さんがゼロから立ち上げられたShopifyストアですが、Shopifyの良さはどういった点があると思われますか?
廣中さん ひとつは、SEOがすごく強いんです。たとえば「角瓶 ケース」で検索すると、うちがサイトが上位に出てきます。Shopifyで数年しっかり運営していると、Googleからの信用が自然と高まってくるんですよね。あとは、ちょっとした独自性があると上位表示は取りやすいと感じています。たとえば「進撃の巨人 黒ラベル」で検索しても、うちが上位に出ることもあります。
最近のSEOでは、どこよりも先に商品を出すことが重要なんですよ。先に出して、先に購入されれば、それだけで上位に行きやすい。いったん上位表示されたらしばらく検索順位は落ちません。なので、うちは「どこよりも早く出す」っていうのをすごく意識しています。商品が出た瞬間にメルマガやLINEで通知して、最初の数件の注文が入ると、数時間後には検索上位に入ってたりするんです。
ーー お酒は解禁日や販売開始日が一律に決まっていることが多いかと思いますが、そこはどう対策されているのですか?
廣中さん 発売前の情報が出たときは、できるだけスピーディに対応できるようにしています。みんなが仕事を終えている時間でも、私はそのタイミングを活かして準備・公開できるので、そこは自分の強みだと思っています。
もちろん、営業さんと事前にしっかり話し合って、リスクやルールは共有したうえでやっています。規定が明確にあるわけじゃないので、グレーなところは自分の判断で動くんです。だから「誰よりも早く買いたい人」は、住田屋を選んでくれます。
ーー それは他の事業者が真似しようとしても、なかなかできない部分ですね。
廣中さん そう思います。知ってても、やりきれるかどうかは別の話なので。私はそこに全力で時間を使っているから、やれているだけです。

(オンラインサイトには、廣中さんご自身が対応するチャット機能の設置も)
非エンジニアでもできる、ひとりShopify運営
SNSでの発信の工夫だけでなく、住田屋オンラインストアは構築と運用も含めて廣中さんがひとりで担われています。Shopifyというツールを最大限に活かしながら、改善を積み重ねていくその姿勢からは、個人事業者や小規模チームにとってのひとつの理想形が見えてきます。
ーー 初期のストア構築もご自身でされたのでしょうか?
廣中さん 最初は業者にお願いしてたんですけど、思っていたように仕上がらなくて、途中から自分で作り直しました。インパルスという有料テーマを入れて、アプリも必要なものを選んで追加しています。
ーー 機能追加もご自身でアプリを探すなどで対応されているんですか?
廣中さん はい。たとえばこの前「パンくずリスト」を入れたいなと思って。最初はアプリを探してたんですけど、ChatGPTやShopifyのSidekickを使ってコードを少し触ったら結局できちゃったんですよね。Sidekickはすごくいいですよ。ChatGPTだと表面的な答えになることが多いけど、Sidekickはちゃんとコードに突っ込んで「これはできない」とか、具体的に教えてくれるんです。
Shopifyストアに関しては今のところは完全に自分ひとりでやってます。でも、Sidekickがあれば本当に何でもできるんじゃないかって思いますよ。
ーー ありがとうございます。Shopifyが進化していく中で、廣中さんのように柔軟に動きながら、自分の言葉と行動で運営を積み重ねていくストアは、これからますます価値を持っていくように感じました。
大きな予算も人員もない中で、ぬくもり感とスピード感を両立しながら、独自のスタイルでECを築いてきた住田屋オンラインストア。その背景には、廣中さんご自身の”らしさ”を活かしながら、柔軟に挑戦を続けてこられた日々があります。
お酒を売るということだけではなく、人とのコミュニケーションの楽しさを組み込みながら、Shopifyというツールを活用して形作っていく。
住田屋オンラインが目指しているのは、みんなで日本中をお酒で笑顔にするECのかたち。廣中さんの発信と言葉、そして行動のひとつひとつが、その理想を現実にしています。