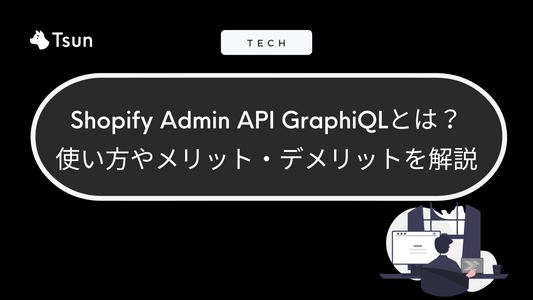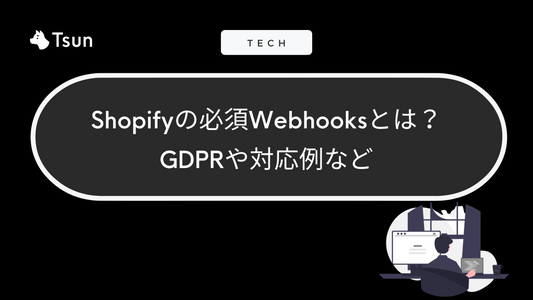福岡の老舗酒販店「住吉酒販」。その2代目として事業を率いる庄島健泰さんに、前編では“伝える酒屋”としての姿勢や、地元密着から始まる接客の本質について伺いました。
本後編では、コロナ禍をきっかけに加速した挑戦と決意、そしてShopifyを活用したEC戦略について深く掘り下げていきます。
どんな言葉で、誰に届けるのか。全国の日本酒好きへ向けて構築してきた伝わる仕組みとは。変化していく時代に合わせた酒屋としての哲学に迫ります。

(住吉酒販有限会社 代表取締役 庄島建泰さん)
インタビュー前編はこちらからご覧ください。
広く売るより、深く届けるECの役割
コロナ禍を経て、店舗での販売に立ち返って見えてきた日本酒と酒屋の本質。誰に、どんな想いで届けるかという問いを持ちながら、住吉酒販が目指すECのかたちは、ただ広く売る場所ではなく、深く届ける仕組みでした。
ーー 最近では、お酒をネットで買うというのもだいぶ一般的になってきました。今後、住吉酒販ではECにどのように力をいれていかれるのでしょうか。
庄島健泰さん(以下庄島さん) うちにとって、ECの可能性で言うと、お酒そのものよりも「酒碗(しゅわん)」の方があるのかなと思ってます。やっぱり、自社でしか扱っていないオリジナル商品だから。
ーー 確かに、唯一無二のオリジナルだからこそ、ECでも価値が伝わりやすい側面はありますよね。
庄島さん お酒って、どうしても運賃の壁があるんですよ。特に関東圏は市場として一番大きいし、優れた酒屋さんがたくさんある。だいたいの銘柄は揃っているので、銘柄勝負をしても意味がない。
そんな中で、あえてうちを選んでくれる方っていうのは、YouTubeを見てくださっていたり、酒碗の世界観に惹かれていたり、僕らのファンなんですよね。送料が高くても、それを越えて買ってくれるのはそういう方たちなんです。
だから、うちのECは広く売るというより、濃いファンに届くための仕組み。ファンの深化ですね。全国展開で勝負するというより、この人から買いたいと思ってくださる方に向けた場所なんです。
ーー ファンの深化、わかりやすくスッとはいってくる言葉ですね。
庄島さん 天酒堂に関しては、今は東京にも店舗があるので、そこでセレクトした商品をECでも扱っているので、よりECとの相性がいいのかもしれませんね。
ただ、やっぱりクール便の送料ってネックですよね。お酒1本に対して2,000円くらい余分にかかることもある。だから、送料以上の価値で勝負するというより、買いたいと思ってくれる人が、ちゃんと買える場所を用意しておくという感覚で運営しています。

(Shopifyで構築された住吉酒販のオンラインストア)
比べられない場所へ行きたい──コロナ禍の転機と覚悟
ーー コロナ禍は多くの事業者にとって分岐点になったと思います。庄島さんにとってはどういう転機だったのでしょうか?
庄島さん コロナ禍は僕にとっては良かったんですよね。もちろん大変だったんですけど、深く強く考えるきっかけになったし、一歩踏み出すためのエネルギーにもなった。もう、10年分を2、3年で駆け抜けたような感覚です。
普通に過ごしていたら、あんな風に一気には変われなかったと思うんです。たとえば事業の撤退の判断もそうですし、そこから「酒碗をちゃんと打ち出していこう」とか、「日本酒をもっと支持される存在にするにはどうすべきか」みたいな問いも、やっぱりコロナがなければ先送りにしていたかもしれません。
それまでは、ありがたいことに右肩上がりで、売上も順調だったんです。どこかで守りに入っていたというか、気づいてはいたけど、着手できていないことがいくつもあった。でも、コロナが来て全部やろうと思えたんです。だから正直、コロナがあって助かったという感覚すらあるんです。
ーー その時期に進めた人も、立ち止まらざるを得なかった人もいらっしゃると思いますが、その差はどこにあると感じていますか?
庄島さん 僕の場合は、やっぱり誰にも比べられたくないという気持ちなんですよね。ずっと昔から。たとえば売上とか取り扱ってる商品とか、他の酒屋さんと比べられるのが本当に嫌で。勝ち負けの問題じゃなくて、比べられてるということ自体がもう耐えられない。
だったら、そもそも比べられない場所に行けばいいというのが僕の原動力なんです。たぶん、負けず嫌いなんでしょうね。でも、勝ちたいというより、比べられる前に違うフィールドに行きたいという気持ちのほうが強い。
ーー コロナ禍という社会的な逆境でこそ、立ち返るものがあったのですね。
庄島さん 当時の状況を振り返ると、酒蔵も本当に苦しい時期でした。飲食店には補助金が出ていたけど、酒蔵にはなかなか届いていなかった。だから、ここで止まってもらっちゃ困るっていう気持ちが、本当に強くありました。
もちろん、僕ひとりで酒蔵を救えるわけじゃない。でも、止まらずに前に進むことで、酒蔵や日本酒の未来に何か繋がるかもしれない。その一心で動いていました。
うちはお酒を造っているわけではない。でも、造り手と飲み手をつなぐ中間にいるからこそ、自分たちにしかできないことがあるはずだと信じて、もうやるしかないと踏み出した。あのタイミングで決断できたことは、今もすごく大きいと思っています。

(住吉酒販のテーマ「酒に笑う人生」)
点と点をつなげるECと、発信の種まき
ーー コロナ禍を経て、いま改めてECに求められる役割や、住吉酒販としての向き合い方をどう捉えていますか?
庄島さん 戦略と呼べるようなほど立派なものではないんですけどね。でもたとえば、SNSやメディアでの発信とECの導線が、もっとスムーズに結びついていけばいいなとは思っています。
今の購買行動では、「検索して一番上に出てきたところで買う」というのがスタンダードじゃないですか。だけど、もしECの中で、実店舗に行ったわけじゃないのに、行ったような気持ちになれるような体験を伝えられたら、それってうちを選んでもらえる大きな理由になると思うんです。
ーー まさに、ECなのに対面で接客されている感覚ですね。
庄島さん 今はLINEのビジネスアカウントなんかでお客様とつながってるんですが、そのつながりがもっと自然にECと接続できるようになればいいなと。じゃあこれ買おうと思ったときに、パッと直感的に購入まで進める未来も描けるんじゃないかと。
そうなったとき、これまでYouTubeだったりSNSだったり積み重ねてきた種まきや発信が、ひとつにつながって力を発揮できる。そう信じてやってる部分があります。だから、戦略というよりも、そうなっていくだろうという前提で、いろんな方向に向かって動いてるという感じですね。
まあ、正直いって、けっこう散らかってるんですけどね。でも、その散らかった点が、最終的にうまく結びついてECにたどり着けばいいなと思ってます。
“伝わるEC”をつくるためのShopifyという選択
ーー 住吉酒販のオンラインストアだけでなく、運営されている新しい酒器 『酒碗』を販売する天酒堂もすべてShopifyで構築されてるんですよね?
庄島さん はい、そうです。天酒堂の方では、今はウェブマーケターの方にも入ってもらっていて、いろんなアップデートや改善を進めているところです。なので僕自身、今は勉強させてもらっている感じですね。
ーー 今後も、Shopifyを活用しながら表現や販売の幅を広げていく構想でしょうか?
庄島さん そうですね。やっぱりShopifyを選んだ理由って、表現の自由度が高いことに尽きるんですよ。商品やメッセージに込めた価値、それをどう見せるかという部分に、すごく柔軟性がある。
これからさらに進化していくプラットフォームだと思っているので、乗れる波にはどんどん乗って、機能も積極的に使っていきたいなと考えています。
ーー 以前は別のサービスをご利用だったとのことですが、Shopifyに移行されたのはいつ頃だったのでしょうか?
庄島さん 前はBASEを使ってました。もう6〜7年前くらいになりますかね。その頃は、LINEと連携したちょっとカスタマイズ寄りのECサイトにしていたんですけど、やっぱり伝えたいことをちゃんと伝えるのが難しかったんです。
細かいディテールの調整がうまくできなかったというか、テンプレートの中でどうしても表現が制限されてしまう部分があって。
当時はデザイン性を重視してBASEを選んだんですけど、実際、当時としては使いやすかったし、良かったと思っています。でもそこから、いろいろ変えていくのが難しくなってきた。決済まわりの自由度だったり、細かな見せ方だったり。やっぱり、全体的に柔軟性があるのはShopifyの方だな、という印象でした。
事業やブランドが変化していくなかで、もっと伝えたいというフェーズに入ったときに、Shopifyならそれをカタチにできると思い移行を決めました。

(新しい酒器「酒碗」)
ブランドが持つべきは、”強いメッセージ”
店舗でもECでも変わらず、自分たちにしか出せない価値を信じて、届けることに全力を注いできた庄島さん。語る言葉の一つひとつには、日本酒業界の未来と酒屋という役割に向き合い続けてきた覚悟があります。
そんな庄島さんが、信念をもって築いてきた住吉酒販や酒碗のECサイト。背景にある言葉の中には、これからECに挑む人にとっても、いま運営を見直そうとしている人にとっても、ブランディングとは何かをあらためて問い直すヒントが詰まっています。
ーー これからECに取り組む方、あるいはブランディングを見直したいという方にとって、大切なこととは何でしょうか?
庄島さん うーん……やっぱり根っこにあるメッセージが強くないと、中身がスカスカになってしまうと思うんですよね。いわゆる経営理念やコンセプト。結局、そこが一番大事だと思っていて。その想いを、ECという場所でどれだけちゃんと表現できるか。そこに尽きると思います。
もちろん、理念が強すぎて、そのまま表に出すとお客様と噛み合わないこともあるとは思うんです。だからこそ、「自分たちは何を届けたいのか」「どんな気持ちでこの商品を扱っているのか」という背景の熱意がなければ、選ばれる理由にはならない。逆にそこが強ければ、世界観も表現も、きっとちゃんと伝わっていくと思っています。
見た目や機能が整っていることも大切ですけど、それって後からどうにでもなる部分だと思うんです。ベースにある想いがなければ、何をどう着飾っても響かないと思うんです。
本質的には、ECも実店舗も、目の前にお客様がいるかいないかの違いだけで、やってることは変わらない。だからこそ、表現の仕方やマーケティングの技術ももちろん大事なんですけど、会社としてブランドとして、何を届けたいのかという中枢の部分がしっかりしていないと、続かないと思いますね。
「この商品が好き」とか「この世界観が好き」と思ってもらえるかどうかは、そういう土台の強さにかかっていると思っています。
問屋の時代から続く商いの精神を引き継ぎながら、届け方そのものに挑み続けてきた住吉酒販。 ECやSNSといった新たな手段を手にしながらも、その根底には常に、「どう届けるか」ではなく、「何を届けたいのか」というまっすぐな問いが流れていました。
目の前のお客様を大切にする姿勢を軸に、ローカルから全国へと丁寧に届ける営み。その一つひとつが、変化の時代における酒屋のあり方を示しているように感じます。
比べられない場所に行くという言葉の背景には、静かで力強い意思が息づいていました。