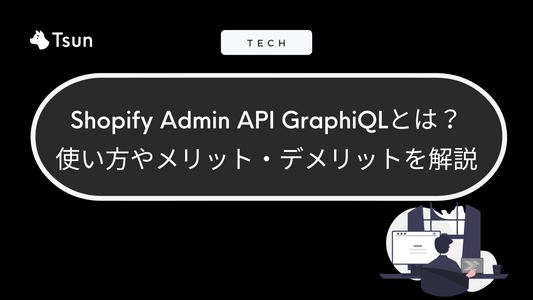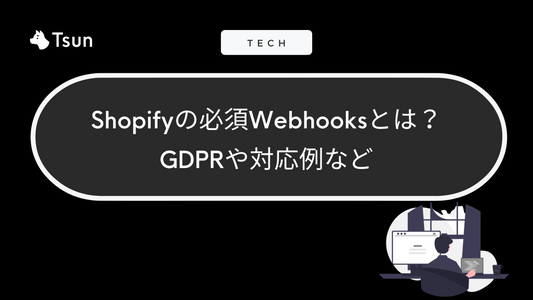福岡で古くから土地のお客様に寄り添う酒屋「住吉酒販」。地元に根ざした誠実な商いを大切にしながらも、東京ミッドタウン日比谷への出店やYouTubeでの発信など、地域と革新を行き来しながら、独自の道を切り拓いてきました。
この住吉酒販を率いるのが、代表・庄島健泰さん。魚屋・飲食業を経て酒屋の家業へと戻ってきた庄島さんは、コロナ禍をきっかけに日本酒とは何か、酒屋とは何かをあらためて問い直し、芸術性が高く機能的にも優れた酒器「酒碗(しゅわん)」など新しいブランド開発も手掛けています。
時代の変化に流されるのではなく、酒屋の役割の根本を見つめ形を変えていく。そんな庄島さんと住吉酒販のこれまでの歩みについて伺いました。

(住吉酒販有限会社 代表取締役 庄島建泰さん)
業務用問屋の時代から、地酒とともに歩む現在地へ
―― いまのような住吉酒販さんのスタイルに至るまで、どのような歴史があったのでしょうか?
庄島健泰さん(以下庄島さん) もともと本家は、福岡県西部の糸島という地域にある酒屋問屋なんです。住吉酒販の前身となる問屋で創業は大正3年。100年以上、商いを続けてきた会社です。
昭和60年頃までは、かなり順調にやっていたと思います。あの頃は本当にみんなお酒をよく飲んでいたし、免許制で市場が守られていたこともあって。でも90年代に入って、販売免許の規制緩和が始まると、状況は大きく変わっていきました。量販店やコンビニでも、どこでも手に入る時代になった。全国的に、酒屋問屋という業態はどんどん斜陽になっていきましたね。
―― そんな激動の時代の中で、お父様が「住吉酒販」を立ち上げられたんですね。
庄島さん 父は本家の次男だったので、いわば分家として福岡市内に出てきたんです。最初は飲食店向けの配達がメインで、業務用の営業が中心でした。いまのような地酒専門店というイメージまでは父の代で変わっていったのですが、あくまでtoB向けの業務用酒販店でしたね。
―― 庄島さんが家業に戻られてからはどのように変わっていったのでしょうか。
庄島さん 僕は16年前に家業に戻ってきたんですけど、業務用の中間流通業だけでは、世の中からこの先必要とされなくなっていくだろうと感じてました。
ちょうどその頃から、自宅でお酒を買って楽しむっていう文化が出てきて、今でいうと四合瓶(720mlの瓶)が一般的になりはじめたくらいなんですよ。それまでは一升瓶で飲食店に卸すか、本当にヘビーユーザーが家で飲んでるかっていう。
日本酒の味わいもどんどん多様化して、新しいスタイルの酒が次々に出てきた時代でした。だからもう最初から、BtoCを強化しようと思っていたんです。

(福岡県福岡市にある住吉酒販博多本店)
”商品を届ける”から“価値を届ける”酒屋を目指す
庄島さん 酒屋に戻る前は、東京で飲食店や、こだわりのある魚屋で働いてたんですよ。酒を問屋から仕入れる立場だったので、酒屋という存在を“逆サイド”から見ていたわけです。だからこそ、ただ注文を受けて商品を届けるだけでは、いずれ必要とされなくなるだろうという感覚が強くありましたね。
だから、自社にしかできない価値をお客様に届ける、そういうスタイルの酒屋を目指そうと思ったんです。
―― 最初からオフラインとECを掛け合わせようとは考えていたんですか?
庄島さん 酒屋に戻った当初は、ECにはまったく手をつけられなかったですね。まずは福岡市内の目の前のお客様に直接伝える手段しか選べなかったというか、そこを大事にしようと思っていたんです。
取り扱う酒も、最初は地元・九州のものだけでした。地元の酒を、地元で伝えるという共感の連鎖をつくるような感覚でしたね。そうした積み重ねの中で、だんだんとお客様が増えていって、取り扱う蔵元も九州だけでなく全国へと広がっていったんです。
コロナで問い直した、日本酒と酒屋の“本当の価値”
東京ミッドタウン日比谷への出店を経て、拡大路線を歩んでいた住吉酒販。そんな矢先に起こったのが2020年のコロナ禍でした。人が集う場所としての酒屋のあり方が問われる中で、庄島さんは日本酒そのものの存在価値、そして酒屋の本質と向き合うことになります。
庄島さん ちょうどコロナ禍の2年前に、東京ミッドタウン日比谷がオープンするときに住吉酒販として出店したんですよ。三井不動産から声をかけてもらって。地方の専門店が東京で勝負するって、当時はあまりなかったのでやっぱり嬉しかったですね。
当時はまだECもやってなかったし、ほんとに肉弾戦というか、現場で伝えるしかなかった。でも、なにか自分の中で燃えなかったんです。店を出したっていうことだけで終わってるような感覚があったんですね。常連さんは増えていくけど、この先どう展開したらいいんだろうって、どこか自分に物足りなさを感じてたんですよね。
―― そこに、コロナ禍がやってきたと。
庄島さん 一旦リセットしようと思いました。そのとき改めて考えたのが、酒屋って何だろうということ。コロナ禍では、禁酒令のようなものまで出されましたよね。アルコールは全部悪、みたいな扱いで。日本酒も、いろんな種類のお酒と一緒くたにされて、ひとくくりに悪者にされた。
でも、日本酒って御神酒なんですよ。2000年以上、日本の象徴として伝わってきたものなのに、未曾有の出来事がきた瞬間に悪者にされてしまった。そのことに、すごく憤りを感じましたね。
そのときに日本酒とは何か、酒屋とは何かっていうのを根本から考え直したときに、 やっぱり目の前のお客様に貢献することが僕らの喜びだったわけですね。直接届けることに意味があって、それを大義としてたわけです。

(2018年にオープンした住吉酒販 東京ミッドタウン日比谷店)
接客の延長線上にあるYouTubeという場
“悪”として扱われた日本酒への憤りから、本来の価値を伝えるという原点に立ち返った庄島さん。福岡という土地に根ざしながら、日本中へ思いを届ける手段として選んだのがYouTubeでした。発信と接客を重ね合わせるような動画シリーズは、700本を超える今もなお更新が続けられています。
庄島さん 日本酒の未来に、前向きな変化を起こしたかったんです。自分の中で、酒や酒業界に対して恩返しをしたいという気持ちが、コロナ禍を経て強くなっていきました。
福岡で、目の前のお客様に直接届けるという感覚はずっと大事にしつつ、もっと日本酒の魅力をちゃんと伝えられる手段をつくろうと。日本中の人に、自分たちの言葉で伝えようと。その手段のひとつがYouTubeだったんです。
―― Youtubeは5年前からコンスタントに発信されて、すでに700本以上の動画をアップされています。すごい継続力ですね。
庄島さん はじめる前から最低でも1,000本は続けようと決めて始めました。コロナはいつか絶対に終わると思ってたし、当時はいろんな人が動画を始めてましたけど、正直続かないだろうなとも思ってたんです。だったら、自分は1,000回続けられるスタイルでやろうって。
―― 動画内では毎回テーマをくじ引きで決めていらっしゃるんですよね。
庄島さん あれって要はオンライン接客なんですよ。お客さんから質問をもらって、それに応えるようにして酒を紹介していく。コロナで人が動けなくなったときに、仮想来店のようなかたちをつくれないかと考えて生まれたんです。あれがもし、「今日はこの商品をご紹介します」みたいな形式だったら、たぶん続けられなかったと思いますね。
商売って、どれだけ商品がよくても、お客さんが来なかったら止まってしまう。でも、逆にお客さんが来てくれれば、経営は続けられる。くじ引きで質問を引いて、それに応える形式なら、質問の数だけ永遠にコンテンツが生まれるわけですからね。だから、あのスタイルにしたんです。
―― まさに、酒屋とお客さん双方向のオンライン酒屋ですね。
庄島さん 伝えたかったのは「酒屋って、こんなにいろんなことに対応できるんだよ」っていうこと。どんな質問でも、ちゃんとお酒を選んで、そのお酒について語ることができる。そういう存在なんだよ、っていうことを知ってほしかったんです。
―― 蔵元さんもご自身の蔵のお酒についてはすごく詳しいですけど、やっぱりそれは自社のお酒だからなんですよね。そう考えると、総合的にお酒に詳しい存在っていうと、酒屋さんなんだなと改めて思いました。
庄島さん そうなんですよ。いろんな蔵のお酒を扱いながら、それぞれに合った提案ができる。そういう視点をもつのが酒屋だと思ってます。
結局、僕らがいるのは世の中でも1%以下のすごく小さな市場なんですよね。だから、SNSやYouTubeで発信していても、正直そんなにバズってるとは思ってない。でも、だからこそ「自分にしかできないこと」をちゃんと表現して、ファンの方たちと深くつながっていく。ECでも、YouTubeでも、SNSでも、向いている先は全部同じなんです。
そこをもっと掛け合わせて、より深く、より広く、日本酒の魅力を伝えていけたらと思ってます。

(庄島さんがさまざまな角度で日本酒を案内するYoutubeチャンネル「酒大将SAKETAISHO」)
ただ売るのではなく、想いを届けるECとShopifyの親和性
酒そのものだけでなく、その飲み方や伝え方にまで目を向ける庄島さん。日本酒をより深く楽しむために生まれたオリジナル酒器ブランド「酒碗」は、その象徴的な取り組みのひとつでした。
庄島さん そもそも日本酒ってワイングラスで飲まれることが多くなってきましたよね。でも僕は、それが本当にいい状態なのかな?って思ったんですよ。いわば借り物の器を使っているということでもあるじゃないですか。
昔ながらのぐい呑みは、それはそれで魅力的なんだけど、江戸の終わりから大正あたりにつくられたもので当時のお酒に合わせた器なんです。今の日本酒は、造りの技術も味わいも、すごく進化してる。だったら、それにちゃんと最適化された器が必要だろうと考えたんですよね。
―― そこで生まれたのが、「酒碗」だったんですね。
庄島さん 現代の日本酒に合う、新しい飲み方の器を作ろうと。それで陶芸作家さんと一緒に「酒碗」を立ち上げて、ギャラリーもつくりました。今では、全国のレストランや旅館など、いろんな飲食店さんにも取り扱っていただいています。
―― 飲み方そのものを提案するという姿勢が、そのままECの見せ方にも反映されているように感じます。
庄島さん だからこそ、うちのECはShopifyで構築してるんですよ。単に商品を並べるだけじゃなくて、僕たちの考えていることや、届けたいメッセージを一緒にのせられる場がほしかった。
以前はテンプレート型のカートを使っていた時期もあったんです。でも、この文章をちゃんと載せたいと思っても、フォーマットが決まっていて自由度がなかった。ものは売れるけど、自分たちらしさが伝えられなかったんです。
僕は、ただ売れればいいとは思っていなくて。僕らの伝えたい背景や考え方に共感してもらって、それで納得して買ってもらう。その方が、絶対にいい関係がつくれると思ってるんです。メッセージを主役にできるEC。それが、僕らにとっての理想の売り方なんですよね。

(現代の日本酒に最適化した酒器「酒碗」)
酒蔵が語る時代に、酒屋が担うのは“最初のきっかけ”
―― 住吉酒販は、酒蔵のようないわゆる作り手ではなく、セレクトショップ的な立場だと思います。庄島さんご自身、酒蔵が直販するのと酒屋で販売することでは、どんな違いがあると感じていますか?
庄島さん 15年くらい前は、自宅で日本酒を楽しむ文化が今ほど一般的じゃなかった時代にはSNSもまだ全然広がってなかったんです。だから当時の酒屋の役割って、作り手の思いを代弁して伝えることだったんですよ。業界全体でも、それが酒屋の仕事だと言われていました。
でも僕自身は、本人から直接聞くのが一番リアルだろうって思ってたんです。やっぱり、作り手の言葉をそのまま聞くほうが、心に響くと感じてたんですよね。
それがこの15年で、どんどん現実になってきた。今のヘビーユーザーは、ちゃんと蔵のSNSを見てるし、蔵が自分の言葉で直接発信してる。自分で語る時代になってきたなと。
そうなると、僕ら酒屋がやるべきことはそこじゃないんですよね。すでに熱心なお酒好きに向けて伝えるのは、酒蔵ができる。でも、まだそんなに日本酒に興味がない人に「最初のきっかけ」をつくる。市場の入り口を広げるというか、関心を持つ人を少しずつ増やしていく。そのきっかけづくりこそが、今の酒屋に求められることだと思ってるんです。
―― 作り手が自分で語ることができる今だからこそ、最初の一歩をつくる存在としての役割が重要になってきたと。
庄島さん 昔は、作り手と酒屋がものすごく近くて、酒蔵が「うちが認めないと売らないよ」みたいなスタンスだったこともあって。そういう時代を経て、今でもECに出さないでっていう酒蔵もけっこういますし、本数が限られている銘柄については、そういう感覚が残っています。でも僕は、そこだけにとどまっていたらつまらないと思うんです。
―― なるほど。届け方まで、ある種決められてしまっているような構造なんですね。
庄島さん 若いころから、音楽とかアートとか、ものづくりに対する憧れがあって。だから、ただ商品を届けるだけじゃなくて、「どんな言葉で届けるか」「どういう感動のシーンを演出するか」までこだわりたい。自分にしかできない市場のあり方を提案したいんです。
今では、住吉酒販でも天酒堂でも、オリジナルのアイテムを作ってもらってるんですけど、そういう中で、自分たちにしかできない役割ってあると思ってます。単なる中間流通じゃなくて、僕らだからこそできる提案をしていきたいですね。

(福岡県福岡市の住吉酒販博多本店 店内)
「この店で買いたい」と思われる酒屋をつくるために
―― いま、地酒専門店も増えてきていますが、他店との差別化など、庄島さんはブランディングでどんなことを大切にされていますか?
庄島さん 今の地酒専門店って、パッと写真で見ただけだと、どこも同じように見えると思うんです。酒瓶がずらっと並んでいて、「ああ、有名な銘柄が揃ってるな」っていう印象で終わってしまう。
東京のすごく実力のある酒屋さんのスタイルを、地方で真似してるようなお店も多くて。もちろん、それが悪いというわけじゃないけど、でも正直つまんないなって思っちゃうんですよね。
―― 並んだ銘柄の強さは伝わっても、その店ならではの空気までは見えてこないんですね。
庄島さん だからこそ、実店舗では福岡でしかできない酒屋をつくりたいと思っているんです。同じようにECでも、住吉酒販や天酒堂というブランドがパッと見て伝わるような、カラーやトーンがあるべきだと思っていて。SNSも含めて、見た瞬間に「あ、これだ」って感じてもらえるような世界観、空気感をきちんと作りたいですね。
そのうえで、お店に入ってきてくれたお客様には、僕が本当に信じている商品をちゃんと伝えて届けていく。そういうスタンスでやっています。
どこでも買える酒ではなくて、「この場所、この人から買いたい」と思ってもらえるような、体験や空気感を大事にしたいなと思ってます。
問屋の時代から続く商いを引き継ぎながら、「届け方」にこだわる酒屋へと変化を遂げてきた住吉酒販。コロナ禍を経て、酒屋としての存在意義を改めて見つめ直し、YouTubeやEC、オリジナル商品など多様な手法を通じて伝える酒屋の姿を形づくってきました。
地域に根ざしながら、全国へと思想を届けていく原動力には、商品だけではなく体験や空気感を届けたいという静かで強い思いがあります。
後編では、庄島さんが今語る「福岡でしかできない酒屋」のかたちと、これからの展望についてさらに掘り下げていきます。