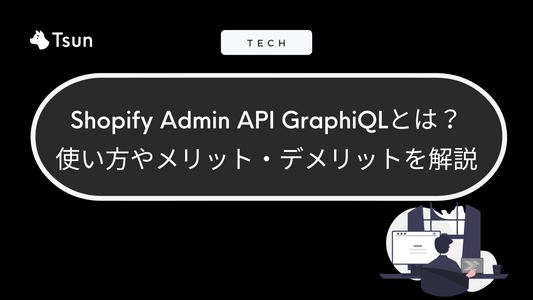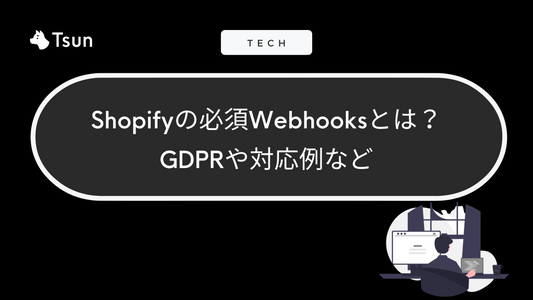「機能性の高いECカートを使いたい」「サポートが手厚いECカートを利用したい」という理由から、makeshopが気になっている方も多いでしょう。makeshopは、600種を超える標準機能を備え、カスタマーサポートやECアドバイザーなどサポートも手厚いことが魅力です。
本記事では、makeshopの概要から、利用のメリット・デメリットまで詳しく解説します。主な機能や利用にかかる料金、実際の導入事例などもあわせて紹介するので、makeshopの詳細が知りたい方はぜひ最後までごらんください。
makeshop(メイクショップ)とは

画像出典:makeshop
makeshopは、GMOメイクショップ株式会社が提供するECサイト構築サービスです。さまざまな業態・商材のEC事業に対応しており、利用ショップ売上高13年連続No.1を獲得しています。
利用できる機能は651種類。固定費の支払いだけで、ショップの状況に合わせて機能をカスタマイズできます。カスタマーサポートやECアドバイザー、コンサルティングなどサポートの手厚さも評価されています。
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
makeshopのメリット
ここからは、makeshopを利用するメリットを解説します。
651種類もの機能を利用できる
makeshopには、651種類もの機能が標準機能としてそろっています。
ショップのデザインを編集できる機能はもちろん、集客の基本であるSEO機能、リピート獲得や売上拡大につながる販促機能までECサイト運営に欠かせない機能を標準搭載しています。
ほかのECカートでは有料オプションとなっていたり、外部サービスとの連携が必要であったりする機能も追加料金なしで利用可能です。
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
デザインテンプレートやデザイン編集により理想のサイトを構築できる

画像出典:makeshop
makeshopには、おしゃれで使い勝手の良いデザインテンプレートが多数用意されています。テンプレートは、すべて無料で利用可能です。そのため、販売する商品やブランドのイメージに合うテンプレートを利用し、簡単にショップデザインを設計できます。
よりブランドイメージに合うサイトへカスタマイズしたい場合には、管理画面内でデザインを編集することも可能。HTML・CSS・Javascriptなどを直接編集し、自由にデザインを変更できます。
専門知識はないけどおしゃれなサイトにしたい方はもちろん、細かい部分までカスタマイズして理想のサイトを構築したいという方にもぴったりなサービスです。
独自の集客機能で費用対効果の高い集客を実現できる
makeshopは、費用対効果の高い集客を実現できる独自の集客機能も魅力のひとつ。
たとえば、アイテムポストと呼ばれる機能では、Yahoo!ショッピングや価格.comなどの大手ECカートにも商品を掲載できます。ECモールの顧客にアプローチできるため、より多くの新規顧客を獲得できるでしょう。
MakeRepeaterという機能では、ショップの顧客や売上を分析し、リピーター育成に向けた具体的な施策を自動で提案してもらえます。購買行動に沿ったメールを配信したり、配信後の開封率・クリック率・購買率などを一覧で確認できたりするため、効果的なメールマーケティングが可能です。
このほかにも、makeshopには自動運用広告やCRMなどさまざまな集客機能があります。CRM以外の機能はすべて無料で利用できるため、低コストで効果の高い集客を実現できます。
カスタマーサポートやコンサルティング、運用代行まで手厚いサポートを受けられる

画像出典:makeshop
makeshopには、操作方法の説明から、売上拡大などのショップの課題解決に向けた相談対応、ECサイト運営に必要な業務の代行まで、幅広いサポートを用意しています。
カスタマーサポートでは、電話サポート・チャットボット・よくある質問・makeshopマガジンなどを提供しており、操作方法や機能などに関する疑問をすぐに確認できます。
ショップ開設後はECアドバイザーがつき、必要な設定サポートや売上拡大に向けた提案などを行うため、EC運営が初めての方も安心です。
ショップの売上拡大に向けてプロのコンサルタントから徹底的なアドバイスを受けられるコンサルティングや、ショップ開設~物流までECサイト運営に必要な業務を任せられる運用代行サポートも提供しています。
これらにより、ECサイト運営における疑問や悩みを迅速に解決できるでしょう。
makeshopのデメリット
makeshopは、多数の機能を提供したり、手厚いサポートを受けられたりするなど、さまざまなメリットが得られる一方で、デメリットもいくつかあります。
ここからは、makeshopの利用におけるデメリットを解説します。
固定費が高め
makeshopにはプレミアムプランとエンタープライズプランの2つのプランがあります。
プレミアムプランの初期費用は11,000円、月額費用は13,750円です。エンタープライズプランの初期費用は11,000円、月額費用は55,000円になります。
他のECカートの中には、初期費用・月額費用がともに0円のものや、月額数千円で利用できるプランを提供しているものも少なくありません。そのため、makeshopは固定費がやや高めである点がデメリットと言えるでしょう。
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
デザインカスタマイズにはHTMLなど専門的な知識が必要
makeshopにはおしゃれなデザインテンプレートが多数用意されており、簡単にショップを構築できます。
一方で、「ブランドイメージに合うサイトにしたい」「取り扱い商品が映えるサイトにしたい」といった場合には、HTMLやCSS、Javascriptをカスタマイズする必要が出てくることもあります。専門的な知識を持っていない場合には、makeshopで理想通りのサイトデザインを実現するのは困難になるでしょう。
ほかのECカートには、直感的な操作でデザインをカスタマイズできるものもあるため、デザインカスタマイズの難易度の高さはデメリットといえます。
makeshopの主な機能
makeshopのプレミアムプランで利用できる主な標準機能を紹介します。
| デザイン機能 | オリジナルデザイン編集 デザインテンプレート HTML補助ツール HTMLエディター機能 デザインセットの入出力 トップページレイアウト変更 マルチフォーム機能 フリーページ カレンダー機能 人気ランキング機能 在庫マトリクス表示機能 商品グループ設定機能 |
|---|---|
| 商品管理機能 | AIアシスト 複数の商品画像登録 商品データのダウンロード・アップロード 商品表示期間設定 税率の0%設定機能 商品バリエーション 価格・ポイントの一括修正機能 |
| 会員管理機能 | 年齢認証 一元管理ツール対応 会員管理機能 会員情報メモ機能 会員グループの自動振り分け機能 会員データのダウンロード・アップロード メルマガ会員のインポート 買い物と同時に簡単会員登録 配送完了ステップメール |
| 在庫管理機能 | 一元管理ツール対応 在庫アラートメール機能 在庫マトリクス表示機能 商品バリエーション |
| 配送機能 | 商品ごとへの配送設定 複数のお届け先へ配送 配送希望日時設定 配送料の詳細な設定 海外配送可否 配送業者送り状連携 伝票番号一括登録 |
| 販促機能 | 海外販売 クーポン機能 まとめ買い割引機能 販売予告機能 再入荷お知らせメール機能 名入れ機能 商品レビュー機能 人気ランキング機能 商品表示期間設定 割引期間設定 会員管理機能 メルマガ配信機能 最近見た商品のレコメンド機能 「あと〇円で送料無料」表示機能 ラッピング・のし・ギフト対応機能 注文完了画面バナー表示機能 かご落ちメール |
| 集客機能 | SEO設定機能 再入荷お知らせメール機能 アフィリエイト連携 リターゲティング広告 アイテムポスト LINEブランドカタログ連携 Yahoo!ショッピング連携 Instagramショッピング連携 YouTubeショッピング連携 Googleショッピング広告連携 |
| 分析機能 | Googleサーチコンソール登録機能 Googleタグマネージャー対応 GoogleAnalytics4対応 売上分析機能 |
上記のほかにも、決済機能やCRM機能など便利な機能がそろっています。また、追加料金を支払うことで利用できるオプション機能や、要望に合わせてカスタマイズできる機能もあります。
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
makeshopに連携できる機能
makeshopには、以下のような連携機能があります。
| YouTubeショッピング連携 | YouTube動画で商品販売できる機能 |
|---|---|
| Googleショッピング広告連携 | 関連したキーワードが検索されたときに商品画像を検索結果に表示する機能 |
| Instagramショッピング連携 | Instagramに投稿した写真に商品タグをつけて写真・動画からショッピングサイトに遷移し商品購入できる機能 |
| Yahoo!ショッピング連携 | Yahoo!ショッピングに出品できる機能 |
| LINEブランドカタログ連携 | ショップ情報・商品データをLINEブランドカタログに掲載できる機能 |
| 海外販売 | 海外に販売できる機能 |
| アイテムポスト | 管理画面から簡単に大手サイトに出品できる機能 |
| リターゲティング広告 | 購買意欲の高い訪問者にリターゲティング広告を表示する機能 |
| アフィリエイト連携 | 37つのアフィリエイトサービスに対応し、直接的に接点がないユーザーに認知を拡大できる機能 |
| イプシロン配送サービス | お得な配送料金サービスを利用できる機能 |
| GoogleAnalytics4対応 | 管理画面内でIDを登録しGA4を設定できる機能 |
| WordPress連携 | WordPressで作成したサイトをmakeshopサイトのドメインを以下に組み込める機能 |
| API連携 | 外部サービスとの連携・アプリ開発ができる機能 |
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
これらの連携機能を利用することで、より多くの顧客獲得や売上拡大を目指せます。
makeshopの利用にかかる料金
makeshopの利用にかかる料金を詳しく解説します。
プラン料金
makeshopには、プレミアムプランとエンタープライズプランの2つの料金プランがあります。各プランの料金は、以下の通りです。
| 料金プラン | プレミアムプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|
| 初期費用 | 11,000円 | 11,000円 |
| 月額費用 | 13,750円 | 55,000円 |
| 売上手数料 | 無料 | 無料 |
| SSL | 13,200円/年 | 無料 |
| 商品登録数 | 10,000点 | 50,000点 |
| 副管理者数 | 5人 | 10人 |
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
初期費用はどちらも同じですが、プレミアムプランのほうが月額費用を安く抑えられます。ただし、プレミアムプランはエンタープライズプランに比べて商品登録数や副管理者数の上限が低いなど制限が厳しくなっています。ショップの成長段階に合わせて、プランを選ぶことが大切です。
決済手数料
makeshopでは、クレジットカード決済、AmazonPay、Paidyやatoneなどの後払い決済を利用できます。決済方法ごとの手数料は、以下の通りです。
| 料金プラン | プレミアムプラン | エンタープライズプラン |
|---|---|---|
| クレジットカード決済 | 3.19%~ | 3.14%~ |
| Amazon Pay | 3.90% | 3.90% |
| Paidy | 3.50% | 3.50% |
| atone翌月後払い | 3.50% | 3.50% |
※本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
makeshopの決済手数料は、3.19~3.5%です。ほかのECカートでは4.0%以上かかるケースもあるため、makeshopの決済手数料は安いといえます。ただ、コンビニ決済やキャリア決済などには対応していません。
上記以外の決済方法も取り扱えるようにしたい場合には、外部サービスとの連携を検討しましょう。
オプション利用料
makeshopには、標準機能のほかにもBtoBに特化したサイト構築・運営ができる「BtoBオプション」や、入荷前の新商品の予約注文を受けられる「予約販売機能」など、より理想のショップに近づけるためのオプション機能が用意されています。
ここでは、主なオプション機能の利用料金を紹介します。
| コスト | 初期費用 | 月額・年額費用 |
|---|---|---|
| BtoBオプション | プレミアムプラン:110,000~440,000円 エンタープライズプラン:無料 |
0円 |
| 定期購入機能 | ペイメントゲートウェイ:330,000円 イプシロン・プレミアムプラン:110,000円 |
66,000円/年 |
| WordPress連携オプション | 110,000円 | 0円 |
| 予約販売機能 | 0円 | 66,000円 |
| イーレコメンド | 66,000円 | 132,000円/年 |
| ケータリング・デリバリーオプション | プレミアムプラン:330,000円 エンタープライズプラン:0円 |
0円 |
| サイト内検索オプション | 66,000円 | 132,000円/年 |
| シークレットショップ機能 | プレミアムプラン:330,000円 エンタープライズプラン:0円 |
0円 |
| 店舗受け取り機能 | 385,000円 ※1 | 0円 |
| BtoB向けECモールオプション | 3,300,000円 ※1 | 55,000円/月 |
| WEB受発注システム | 3,300,000円 ※1 | 55,000円/月 |
| 代理店フィー管理システム | 3,300,000円 ※1 | 55,000円/月 |
| オムニチャネル | 要見積もり ※1 | 要見積もり |
| Kintone連携オプション | 要お見積り ※1 | 要お見積り |
※1 導入はエンタープライズプランのみ
※2 本記載は2025年6月時点の情報を元にしています
利用料金は、オプションによって大きく異なります。なかには300万円を超えるオプションもあるため、予算の範囲内で無理なく利用できるかどうかよく確認しましょう。
makeshopの導入事例
実際にmakeshopを利用したショップの事例を紹介します。
わたなべの茶本舗

画像出典:三重大製茶株式会社 わたなべの茶本舗
「わたなべの茶本舗」はモール型サイトからmakeshopに切り替えました。これにより、商品ごとに異なるオプションを細かく設定したり、商品のサイズや個数によって配送料を設定できたりするなど、モール型ではできないことを次々に実現しています。
注文・入金処理に使用していた社内ソフトと連携できるようになり、注文管理・入金管理の作業負担軽減にもつながっています。
あなご亭オンラインショップ

画像出典:あなご亭オンラインショップ
あなご商品を販売している「あなご亭オンラインショップ」は、デザインの自由度と充実のサポートにより、makeshopでのサイト構築を決定。
質問をすればやり方や代替案を提示してくれるmakeshopの手厚いカスタマーサポートにより、やりたいことをスムーズに実現しています。
マルヒロオンラインストア

画像出典:マルヒロオンラインストア
マルヒロオンラインストアは、長崎県の工芸品「波佐見焼」の食器・インテリア雑貨を企画している陶磁器メーカー・マルヒロの商品を販売するショップです。
makeshopの海外販売を利用することで、限られたリソースのなかでも安心して海外に向けた販売を始められています。
makeshopの始め方
makeshopの始め方は、いたって簡単。以下の手順を踏めば、makeshopでのEC運営を始められます。
- 15日間の無料体験に申し込む
- アカウントを設定する
- サイトを構築して運営を始める
- 本契約を行う
15日間の無料体験中もサイト運営できるため、操作感や機能面などを本契約前にしっかり確認できます。無料期間中に作成したショップは、本契約後も使用可能。本契約に進む際、再度ショップを作り直す必要がないことも嬉しいポイントです。
makeshopは600種超の豊富な機能とサポートの手厚さが魅力!
makeshopは、さまざまな業態・商材に対応できるECサイト構築サービスです。固定費の支払いをするだけで、600を超える豊富な機能を利用できるのが魅力です!
操作方法や機能などに関する疑問を解決できるカスタマーサポートや、売上拡大に向けた提案をしてくれるECアドバイザーなど、手厚いサポートも整っています。
ただし、多機能で手厚いサポートがある分、固定費は他のECカートに比べて高め。また、デザインを独自にカスタマイズするためにはHTMLなどの専門知識がなければ難しいのもネックなポイントです。
makeshopが気になっている方は、まず無料体験で機能や操作感などを確認してみましょう。