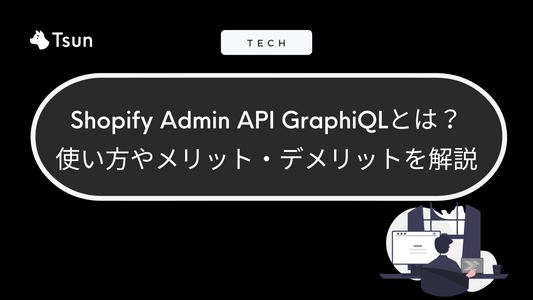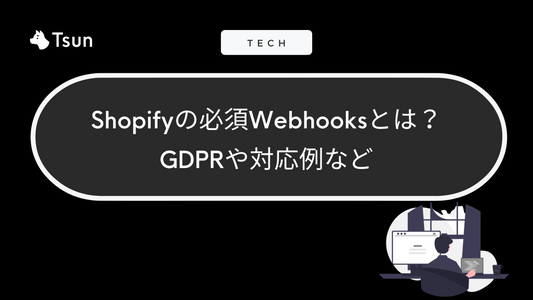Shopifyで越境ECを始めようとしている方の中には、関税について不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
「関税って誰が払うの?」
「税額はどのように決まるの?」
「Shopifyでの関税の設定方法を知りたい」
この記事を読むことで上記の疑問やニーズが解決します。
関税は越境ECにおいて避けて通れませんが、その仕組みは複雑で、正しく対応しないとトラブルに発展する可能性もあります。
今回紹介する内容を参考に、Shopifyで適切な関税設定を行い、安心して海外販売を進めていきましょう。
※本記事に記載の情報は2025年6月時点の情報を元にしています
Shopifyの関税設定でおさえておくべき3つのポイント
具体的な設定方法に入る前に、Shopifyで関税設定を行う際に知っておくべき3つの重要なポイントを確認しましょう。
ポイント1:関税とは?海外へ商品を販売する際に発生する税金
関税とは、ひとことで言えば「商品を国の境界線を越えて輸出入する際に、輸入側の国が課す税金」のことです。自国の産業を保護したり、国の財源を確保したりする目的で設けられています。
越境ECにおいて、日本のストアから海外の顧客へ商品を発送する場合、その商品が顧客の国に到着した時点で「輸入品」として扱われ、現地の税関によって関税が課される可能性があります。
なお、関税の他に、国によっては「輸入消費税」や「付加価値税(VAT)」といった各種税金が合わせて請求されることもあるので、覚えておきましょう。
関税は原則として商品を輸入する側、つまり海外の顧客が支払う義務を負います。
ポイント2:関税は誰が支払う?「DDU(購入者負担)」と「DDP(ストア負担)」の違い
関税を誰がどのタイミングで支払うかによって、大きく2つに分かれます。「DDU (Delivered Duty Unpaid)」と「DDP(Delivered Duty Paid)」です。これは越境ECの運営方針を決める上で非常に重要なポイントです。
| DDU | DDP | |
|---|---|---|
| 支払い者 | 購入者(顧客) | 販売者(ストア) |
| メリット | ・ストア側の手間が少ない ・コスト計算がシンプル ・越境EC初心者でも始めやすい |
・顧客は安心して購入できる ・カゴ落ち率が改善する |
| デメリット | ・カゴ落ちの原因になることがある ・受け取り拒否のリスクがある |
・ストア側に運用の手間とコストがかかる |
DDUとDDPのどちらを選ぶべきかは、自社の状況に合わせて慎重に検討しましょう。
ポイント3:税額はどう決まる?「HSコード」と非課税枠「デミニマス」
関税額は「(商品の価格+送料+保険料)× 関税率」という式を基本に計算されます。この「関税率」を特定するために重要なのが「HSコード」です。
HSコードは、あらゆる商品を国際的に分類するための番号で、この番号によって商品の関税率が決まります。商品を発送する際、国際郵便のラベルやインボイスに正確なHSコードを記載する必要があります。HSコードは税関のウェブサイトなどで調べることが可能です。
もう一つ知っておきたいのが「デミニマス(De Minimis)」です。これは「少額の輸入品に対する免税制度」のことで、課税対象額が一定の金額(デミニマス値)を下回る場合、関税が免除されます。例えば、アメリカのデミニマス値は800米ドル、オーストラリアは1,000豪ドルです。この非課税枠を把握しておくと、どの価格帯の商品が関税の影響を受けやすいか判断するのに役立ちます。ただし、国や商品によっては適用されない場合もあるため注意が必要です。
また、最終的な支払総額には、関税のほかに自由貿易協定(FTA・EPA)による関税の優遇、VAT(付加価値税)や輸入消費税、酒税、環境税、通関事務手数料なども含まれる場合があります。
Shopifyで関税を設定する方法|3つの運用パターンを比較解説
前の章で解説した関税の支払いに関するパターンを、さらに細分化すると以下の3パターンになります。
- パターン1(DDU):購入者が商品到着時に関税を支払う
- パターン2(DDP-①):商品購入時に関税を徴収し、ストアが支払う
- パターン3(DDP-②):関税としては購入者からは徴収せず、ストアが負担する
それぞれの運用・設定方法について解説します。
パターン1(DDU):購入者が商品到着時に関税を支払う
この方式は最もシンプルで、多くのストアがまず採用する方法です。Shopifyで特別な関税設定は不要で、通常どおり送料を設定して商品を発送すればOKです。
関税やその他の輸入税は、現地の税関や配送業者が購入者に直接請求します。
ただし、購入者が関税の存在を知らないと、クレームや受け取り拒否の原因になるため、事前の案内が非常に重要です。
詳しい対策方法は「【Shopify】購入前に伝えておきたい関税の注意点」の章で解説します。
パターン2(DDP-①):商品購入時に関税を徴収し、ストアが支払う
購入者が商品を受け取る際に、関税の支払いが不要となるDDPは、顧客の購買体験を向上させます。2025年5月のアップデートにより、Shopifyのすべてのプランにおいて、標準機能で関税の徴収を設定できるようになりました。これにより、商品購入時に関税を徴収しておき、ストアが発送時に関税を支払うことで、顧客は商品受け取り時に関税を支払う必要がなくなります。
このパターンではShopifyでの設定が必要なので、手順を解説します。
管理画面より、「設定」 > 「関税と税金」の順に選択。「関税および輸入税」の項目にて、「チェックアウト時に関税および輸入税を徴収します。」の横にある「設定する」をクリックします。

画像出典:Shopify管理画面
関税を徴収するマーケットにチェックを入れ、「完了」をクリックします。

ShopifyがAvalaraという関税計算サービスと連携します。この方法では、0.5%の取引手数料がかかります。問題なければ、「保存」をクリック。

これで関税の徴収設定が完了しました。

デフォルトでは関税と輸入税が項目として表示されます。非表示に変更したい場合にはMarketsで変更してください。

その他、DDPで運用にするには以下の点が必要です。
- Shopify Paymentsを有効化
- 商品ごとにHSコードと原産国を設定
- FedExやDHL、UPSなどのDDP配送に対応している配送会社を使用
HSコードと原産国は商品ページで設定可能です。

HSコードの登録内容や、DDPラベルの記載内容に不備があると、トラブルになりかねません。注意して設定をしましょう。
パターン3(DDP-②):関税としては購入者からは徴収せず、ストアが負担する
関税を顧客からは徴収せず、ストアが負担する方法です。「関税込価格」として明記し、追加費用なしをウリにしたい場合などで有効です。
ただし、基本的には、関税分の料金を商品代金に上乗せする形になるため、商品価格が他の商品と比べて、高額に見えてしまう点に注意してください。
この方法では、1の方法と同様にShopifyに特別な設定は必要ありません。
関税が商品価格に含まれていることを、商品ページやFAQなどに明記しておくと、購入者の安心感につながります。
Shopifyの関税対応はどれがおすすめ?
3つのパターンを紹介しましたが、「結局、自分のストアはどの方法を選べばいいの?」と迷う方も多いでしょう。この章では、ストアの成長段階に応じたおすすめの選択肢を紹介します。
これから始めるならDDU(購入者負担)がおすすめ
まだ越境ECを始めたばかり、またはテスト的に運用している段階であれば、まずは「DDU(購入者負担)」方式から始めるのがよいでしょう。
理由はシンプルで、ストア側のリスクや手間が少なく、運用コストを抑えられるからです。DDP方式では取引手数料が発生し、関税の事前計算やDDP対応配送の準備も必要となるため、初期段階では負担が大きくなりがちです。また、設定ミスがあると、トラブルの原因にもなりかねません。
まずはDDUで運用を始め、海外にもファンが増え始めた段階で、特定の国やエリアに絞ってDDPを導入するのが、堅実なステップアップ方法です。
売上が伸びてきたらDDP(ストア負担)でカゴ落ちを防ぐ
越境ECの運用に慣れ、さらに売上を伸ばしていきたいフェーズに入ったら、「DDP(ストア負担)」への切り替えを検討しましょう。
DDUでは、購入者は「受け取り時にいくら追加で支払うのか分からない」という不安を感じやすく、これが購入直前での離脱、いわゆる「カゴ落ち」につながることも少なくありません。DDPを導入すれば、購入時点で支払総額が確定するため、購入者にとっては安心感があり、カゴ落ち率の低下やコンバージョン率の向上が期待できます。
特に競合が多い市場では、価格のわかりやすさや透明性が大きな差別化要因となります。安心して購入できるストアは、顧客満足度も高くなり、継続的に選ばれる存在へと成長していけるでしょう。
購入前に伝えておきたい関税の注意点
「関税がかかるなんて知らなかった!」という購入者のトラブルを防ぐには、購入前の段階で関税に関する情報を明確に伝えておくことが重要です。Shopifyでは、以下のようなページへの記載が有効です。
- ポリシーページ(配送ポリシーや返品ポリシー)
- 商品ページの説明文
- チェックアウト画面
Shopifyの管理画面で「設定」 > 「ポリシー」を開くと、各ポリシーページを作成・編集できます。

画像出典:Shopify管理画面
これらのページを設定しておくと、チェックアウト画面の下部にリンクとして自動的に表示され、購入者が内容を確認できるようになります。

さらに、ポップアップバナーやお知らせバーなどを活用して、関税に関する注意喚起をより目立つ形で表示すれば、ストアの信頼性向上にもつながるでしょう。
以下に、記載例を紹介します。
※海外からのご注文には、現地の関税や輸入税が別途かかる場合があります。これらの費用はお客様のご負担となりますので、あらかじめご了承ください。
Shopifyで関税トラブルを防ぐには、「丁寧な事前案内」がもっとも有効な対策です。購入者が自然に目にする場所に、わかりやすく掲載することを心がけましょう。
自社に合った関税対応で、越境ECを成功させよう
この記事では、Shopifyで越境ECを行う際に重要となる関税の基本知識や、主な設定パターンについて解説しました。
関税への対応次第で、顧客体験やストアの収益に大きな影響が出ることもあります。まずは手間の少ないDDUから始め、注文数が増えてきた国や地域にはDDPを導入するなど、段階的に対応していくのが現実的です。
Shopifyストアの成長段階に応じて、自社に最適な関税対応を選び、スムーズな越境EC運営を目指しましょう。
これからShopifyで越境ECを始めたい方は、以下の記事もご参考にしてください。