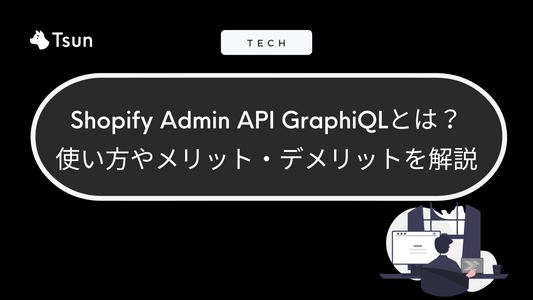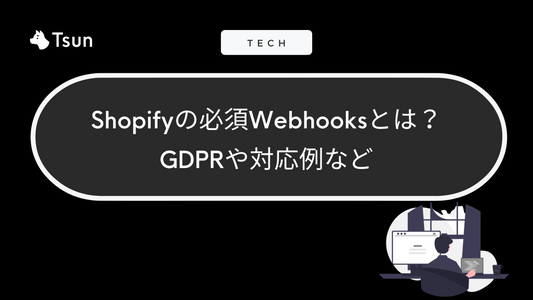Shopifyでストア構築を検討している方にとって、構築にかかる費用は気になりますよね。
「Shopifyの構築方法は?」
「Shopifyの構築にはどのくらいの費用がかかるのだろう」
「費用削減の方法が知りたい」
この記事では、Shopify構築の方法や費用相場、費用削減のポイントなどを解説します。ストア構築を検討している方はぜひ参考にしてください。
Shopify構築の3つの方法
Shopifyを構築するには、主に以下3つの方法があります。
- 1.制作会社に依頼する
- 2.フリーランスに依頼する
- 3.自分・自社で構築する
それぞれのメリット・デメリットを解説します。
制作会社に依頼する
制作会社にはECサイト構築に関する専門家やWebデザイナーなどが在籍しており、経験やノウハウを元にサポートが得られます。サイトの品質(デザインや機能)が保証され、チームによる多角的な提案やアフターサポートも充実している点が多いことがメリットです。
また自社の細かなニーズや、構築以外のマーケティングなどの要望にも対応してもらうことができる場合も多くあります。プロジェクトの管理も適切に行われ、安心して任せることができるでしょう。
デメリットは構築費用が高くなりがちで、納期も比較的長くなってしまいます。
フリーランスに依頼する
フリーランス(個人)に依頼する場合、制作会社と比べて低コストで済む点が一番のメリットです。また制作会社よりも柔軟な対応が期待できます。制作者と直接コミュニケーションを取れるため、スピーディーな意思決定もできるでしょう。
一方で、フリーランスによって品質にばらつきがあり、自社の希望するデザインや機能を実現できない可能性がある点がデメリットです。専門分野以外の対応はできない場合が多く、複数のフリーランスに依頼することになり、コストがかかることもあります。プロジェクト管理は自身で行う必要があるため、自社の稼働もそれなりに必要です。
自分・自社で構築する
Shopifyはデザインテンプレートが豊富で、基本的なECサイトをノーコードで構築することが可能です。
自分・自社で構築する場合の最大のメリットは、構築の委託費用が不要な点です。ある程度のITに関する知識やスキルがある場合、修正や変更の意思決定を迅速に行うことも可能です。
ただし、よりプロフェッショナルなサイトの構築を希望する場合、専門的なノウハウが求められます。また、高いデザイン性や機能性を実現しようとする場合、技術的な学習も必要になってきます。これらの学習コストはデメリットといえるでしょう。またトラブルが発生した場合の対応など、結果的にコストが大きくなる可能性もあります。
下記のブログ記事では、Shopifyの会員登録からストア開設までの流れを紹介しています。自分・自社での構築を検討されている場合はご参考にしてください。
Shopifyの始め方(構築方法)|会員登録からストア開設(立ち上げ)までの流れ
それぞれの方法のメリット・デメリットを踏まえた上で、自社のリソースや予算と相談して決定すると良いでしょう。次の章で構築費用の相場を紹介します。
Shopify構築費用の相場
前章で紹介した3つの構築方法について、それぞれの費用相場を解説します。
制作会社に依頼する場合の費用相場
制作会社に依頼する場合の費用相場は、大きく3パターンに分けられます。
100万円未満:最小限の機能を備えたECサイト
Shopifyのデフォルト機能を中心に、最小限の機能やページ構成で構築した場合、費用相場は50〜100万円です。
最小限と言っても、商品管理、注文管理、顧客管理、ストア分析、キャンペーン・クーポン発行、などECサイト運営に必要な機能は備わっています。またShopifyのテーマ(デザインテンプレート)はおしゃれで操作性も高いため、制作費を抑えながらも見栄えの良いECサイトを構築することが可能です。
ただし、独自性の高いデザインやカスタマイズ機能、越境EC対応などを依頼する場合には、予算内に収まらない可能性が高くなります。
基本的なEC機能で十分な場合や、まずは最小限の機能でスタートしたい場合におすすめです。
100万円〜:デザイン性、機能性が高いECサイト
独自性の高いデザインを表現したい場合や、カスタマイズ機能に富んだECサイトを構築する場合の費用相場は100〜500万円です。
この予算帯であれば、Shopifyの既存テーマでは表現しきれない自社の世界観をコーディングで表現できるでしょう。またプログラミングによる機能カスタマイズも可能になります。さまざまなアプリを用いたり、システムとの連携をすることで、高度なマーケティング、実店舗やモールとの連携、越境EC対応など自社に必要なEC機能も用意できます。
デザイン性や機能性の高いサイトを作りたい、複数のECプラットフォームで運営している、越境ECをやりたい、という事業者はこの予算感を目安にしてください。
500万円〜:大規模やフルカスタマイズのECサイト
大規模なECサイトを作りたい場合や、自社専用にテーマや機能を開発したい場合の予算は500万円以上です。
大規模ECサイトの場合、機能が強化された最上位プランの「Shopify Plus」を利用するとよいでしょう。企業が利用するERPなどの基幹システムと連携する場合には、1,000万円を超えることもあります。
フリーランスに構築を依頼する場合の費用相場
フリーランスに構築を依頼する場合、費用相場は20〜50万円です。経験豊富なフリーランスやチームを組んでいるフリーランスであれば、後述のShopify構築に付随する業務にも対応してくれるでしょう。
費用を抑えたければ、クラウドソーシングサイトやスキルマーケットを活用する方法もあります。実績が欲しい駆け出しデザイナーであれば、数万円〜10万円程度で対応してくれる方もいます。
予算が少ない方や、一部の業務だけを依頼したい方に向いています。
自分・自社で構築する場合の費用相場
自分・自社で制作する場合、構築に関する費用は0円です。ただし、クオリティの担保がないこと、学習教材の購入や人件費が発生する可能性があることを忘れてはいけません。
特にデザインやコーディングのスキルがない場合には、学習期間だけでも3カ月以上はかかる可能性もあります。スクールなどに通う場合には数十万円がかかります。
Shopify構築の費用項目
Shopifyを構築する際に費用がかかる作業を紹介します。実際にかかる費用は、内容や発注先によって大きく異なります。
サイト設計・デザイン
Shopifyはテーマと呼ばれるデザインテンプレートを用いてサイトを構築します。そのため、ゼロからコーディングをしてサイトを作る必要はありません。
構築はテーマに基づいてサイト設計を行い、各ページのデザインカスタマイズをしていきます。基本的なデザインカスタマイズはノーコードで作成できるため、専門的な知識がない方でも作成可能です。
テーマ開発
テーマ開発はプログラミング言語などを用いて、テーマに独自のデザインや機能を実装することです。テーマの開発には、HTML・CSS・Javascript・JSONなどの知識と合わせて、Shopify独自のテンプレート言語「Liquid」を用います。
ページ作成
ECサイトは主にTOP、カテゴリ、商品、カート、チェックアウト、問い合わせ、ポリシーなどのページで構成されます。
ブランドによっては、サービス紹介、会社概要、ブランドヒストリー、ブログなどのページを追加したい場合もあるでしょう。これらのページを追加作成する場合には、1ページ◯円という形式が多いです。
決済システム導入
ShopifyはクレジットカードやQRコード決済、代引きなどさまざまな決済方法を利用可能です。決済方法を利用する際には、Shopifyに決済システムを導入する必要があります。
Shopifyが提供する決済システム「Shopifyペイメント」を有効にすれば、主要クレジットカート、APPLE PAY、GOOGLE PAY、Shop Payが利用できます。それ以外の決済方法を利用するには、別の決済システム導入が必要になり費用がかかる場合もあります。
アプリの導入と設定
Shopifyにはストアの機能を拡張するアプリが8,000種類以上も存在します。テーマにない機能も、このアプリで実装することが可能です。
多数のアプリの中から自社のニーズに合ったアプリを選定してもらったり、導入と設定をしてもらったりする作業にも費用がかかります。アプリによって設定工数が異なりますので、導入・設定費用も異なるでしょう。
下記のブログ記事では、おすすめのShopifyアプリを紹介しています。ご参考にしてください。
送料設定
Shopifyは発送先地域や合計注文金額、合計重量などを元に柔軟な送料設定が可能です。特に越境ECを行う場合、配送先の国や地域が多いほど設定作業は大変になり、委託する場合もあります。
下記のブログ記事では、Shopifyの送料設定の方法を紹介しています。参考にしてください。
マーケット設定|越境ECの場合
海外向けにECを運営する「越境EC」を行う場合、マーケットの設定を行います。「マーケット」は一つ以上の国や地域を一つのマーケット(市場)としてとらえ、価格や言語などの設定をします。
送料設定も関連し、初心者には難しく感じることも多いでしょうから、委託することがおすすめです。
モールやシステムとの連携
Shopifyと平行してAmazonや楽天市場などのECモールで商品を販売する場合、在庫や物流などを連携し、一元管理することがおすすめです。また倉庫や配送などを委託している場合、それらとの連携もしたほうが良いでしょう。
これらは在庫管理システムや倉庫管理システムを導入することで連携できます。また売上データを管理するために、会計システムの導入もおすすめです。
分析ツールの導入
Shopifyストアの売り上げやアクセス数などを分析するツールとして、Shopifyにはストア分析機能がありますが、ストア分析機能では収集できないデータもあります。
本格的なEC運営をする場合、Googleアナリティクスやヒートマップツールなどの分析ツールの導入がおすすめです。
Shopifyの独自アプリの開発
ストアに必要な機能がShopifyアプリストアで見つけられなかった場合、独自アプリを開発して導入することも可能です。
アプリの開発にはプログラミングなどの専門知識や経験が必要になるため、アプリ開発会社に依頼しましょう。
構築費用のオプション項目
構築には直接関係はありませんが、ECサイト運営で必要になる項目です。制作会社によっては、構築と合わせて対応している場合もあります。
ささげ業務
ささげ業務は「撮影」「採寸」「原稿」の頭文字を取った業界用語です。
顧客が商品を直接手に取れないECサイトでは、商品画像や動画の品質は極めて重要です。また商品のサイズを正確に測り、掲載しておくことも必要になります。さらに顧客が「この商品を買いたい」と思えるような文章も欠かせません。
ささげ業務は売り上げに大きく影響するため、高い品質を心がけましょう。必要に応じて、専門家への依頼を検討してください。
商品登録
大量の商品を扱うECサイトでは商品の登録作業も一苦労です。この商品登録作業を代行してくれる依頼先も多くあります。
一般的には商品数 × ◯円という形で提供されています。ShopifyではCSVファイルを用いた一括登録も可能ですが、操作に不安な方は依頼すると良いでしょう。
下記のブログ記事では、Shopifyでの商品登録方法を紹介しています。ご参考にしてください。
画像制作
ECサイトでは写真以外にもさまざまな画像が必要になります。ブランドのシンボルになる「ロゴ」は特に重要な画像です。
他にもバナーやアイキャッチ、ファビコンなど、さまざまなシーンで画像が必要になることでしょう。画像制作やイラスト制作の専門家に依頼することがおすすめです。
広告・マーケティング支援
ECサイトを公開しただけでは顧客は訪れてくれません。Web広告を打ったり、SNSを活用したり、メルマガを配信したり、広告・マーケティング活動をしていく必要があります。
自社に知見やリソースがない場合、料金を払って委託するのも効果的です。
Shopifyの利用料金
ここまで構築に関する費用項目を紹介しましたが、Shopifyを利用する際の料金についても解説します。
Shopifyのプラン料金
Shopifyは月額利用料を支払うサブスクリプション型です。プランごとの料金は以下の通りです。
| 料金プラン | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 月払い | 4,850円/月 | 13,500円/月 | 58,500円/月 | - |
| 年払い | 3,650円/月 | 10,100円/月 | 44,000円/月 | 2,300ドル/月 |
※2025年4月時点
年払いの料金は、年間料金を月割した金額を掲載しています。
下記のブログ記事では、Shopifyの各料金プランを徹底比較しています。プラン選びの参考にしてください。
決済手数料
Shopifyストアで商品が購入されるたびに決済手数料がかかります。プランごとの決済手数料は以下の通りです。
| 料金プラン | Basic | Grow | Advanced | Plus |
|---|---|---|---|---|
| カード手数料 | 3.55%+0円 | 3.4%+0円 | 3.25%+0円 | 2.9%+0円 |
※2025年4月時点
※Shopifyペイメントによる国内販売のクレジットカード決済手数料です。
ドメイン費用
インターネット上に公開されるECサイトでは、ドメインが必要になります。Shopifyでは無料のドメインが提供されますが、本格的なECサイト運営には独自ドメインの取得がおすすめです。
独自ドメインにかかる費用はドメイン名の人気度や種類によって異なりますが、年間1,000〜5,000円程度です。(2024年12月時点)
有料テーマ購入費用
ストアデザインの元になるテーマには、無料テーマと有料テーマの2種類があります。有料テーマの方が機能性に優れ、デザイン性も高いです。有料テーマは買い切りで100〜400ドル程度です。(2024年12月時点)
下記のブログ記事では、Shopify テーマの種類を紹介しています。テーマ選びの参考にしてください。
有料アプリ利用料
Shopifyの機能拡張をするアプリには有料のものもあります。多くは月額数〜数十ドル程度で、毎月料金を支払うサブスクリプション型です。
Shopifyの費用削減のポイント
ここまでShopifyの構築から運営にかかる費用項目を紹介しました。これらを総合して冒頭で紹介した費用相場の金額になります。
この章では費用削減につながるポイントを紹介します。
自社で可能な作業は内製化
Shopifyの構築をする際、自社にWebデザイナーがいる場合には内製化が可能です。また撮影作業や原稿作成なども自社に人材がいれば内製化できます。
他にもアプリの導入や決済システム導入、送料設定なども、時間はかかりますが内製化可能です。
予算と相談して、自社でできることは自社で行うようにすると節約できます。また、今後の修正も見据えて、自社でノウハウを貯めておくことも重要です。
優先度をつけた段階的な開発
テーマ開発やアプリ開発などは特に費用が高くなりがちです。しかし、自社独自の世界観を表現したかったり、自社に必要な機能を実装したかったりすることもあるでしょう。
そのような場合には優先度をつけた段階的な開発がおすすめです。例えばTOPページのみテーマ開発を行ったり、費用対効果の高い機能のみを開発したりし、十分な利益が確保できてから追加の開発を行います。このようにすることで、初期費用を抑えることが可能です。
Shopifyプランの年間契約による割引
構築費用を捻出するためにShopifyの利用料金を節約する方法もあります。
Shopifyの利用料金を月払いではなく、年間契約による一括払いにすることで、料金を安く抑えることが可能です。1年間使用した際の月払いと年払いの差額は以下の通りです。
| 料金プラン | Basic | Grow | Advanced |
|---|---|---|---|
| 月払い | 58,200円/年 | 162,000円/年 | 702,000円/年 |
| 年払い | 43,800円/年 | 121,200円/年 | 528,000円/年 |
| 差額 | 14,400円 | 40,800円 | 174,000円 |
※2025年4月時点
無料テーマや無料アプリの活用
Shopifyの無料テーマは、十分に良質なデザインです。また無料アプリにも十分な機能をもっているものが多く存在します。
始めは無料テーマや無料アプリを活用していき、利益が上がってきたら有料テーマや有料アプリに乗り換えていくという方法もおすすめです。
Shopifyの構築費用を理解し、自社に最適な構築方法をみつけよう!
この記事では、Shopifyの構築方法とその費用相場、費用項目、費用削減のポイントについて解説をしました。
Shopify構築における費用の全体像がイメージできたのではないでしょうか。
自社の予算やリソースによって、取れる選択肢が変わります。自社に最適な方法を見つけ、Shopifyストアの構築を成功させてください。