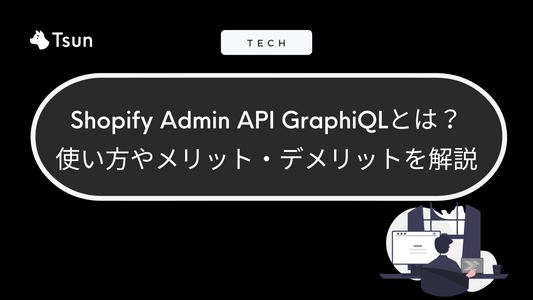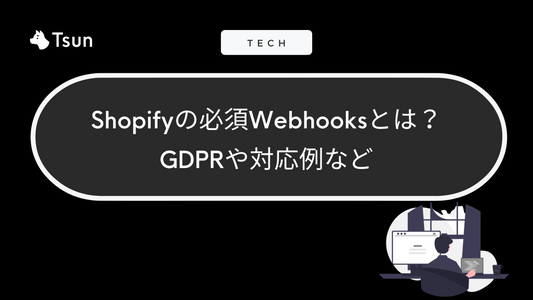「在庫を持たずに、信頼できるブランドの商品を自分のストアで販売できたら...」
「ブランドの販路をもっと広げたいけど、自社のリソースが限られていてできない」
このような悩みを抱える小売ストアとサプライヤーをつなげる仕組みが、Shopifyが提供する「Shopify Collective」です。
Shopify Collectiveは今まで日本のストアでは利用できませんでしたが、2025年夏より日本でも利用できるようになりました。
この記事では、Shopify Collectiveの仕組みや利用するための条件、利用するメリット、注意点などをわかりやすく解説します。
これからShopifyを始める方にも、すでにストアを運営している方にも役立つ内容なので、ぜひ参考にしてみてください。
Shopify Collectiveとは?

画像出典:Shopify
Shopify Collectiveとは、Shopify公式が提供するShopifyストア同士をつなげる仕組みで、アプリを通じて利用できます。あるブランドが販売している商品を、別のストアが自分のお店の商品として取り扱えるようになります。これにより、小売ストアは新しい商品ラインナップを在庫リスクなしで追加でき、供給するブランド側は新しい販売チャネルを獲得できます。
単なる仕入れや委託販売の関係ではなく、Shopifyという共通のプラットフォームを介して、スムーズかつ安全に取引できる点が特徴です。
ドロップシッピングや無在庫販売との違い
Shopify Collectiveは、「在庫を持たずに販売できる」という点でドロップシッピングや無在庫販売と似ています。ただし、いくつかの違いがあります。
取引相手の信頼性
一般的なドロップシッピングは海外の卸業者やマーケットプレイスから商品を仕入れるケースが多く、品質や納期にばらつきがあります。
一方、Shopify Collectiveでは既にShopifyで販売実績を持つブランドが供給元となるため、安心感が高いのが特徴です。
ブランドの透明性
ドロップシッピングでは仕入先を隠して「自社商品」として売ることもありますが、Shopify Collectiveは供給元のブランド名が明示されます。顧客にとって「どのブランドの商品か」がわかるため、信頼を損ねにくい点が強みです。
限定されたエコシステム
ドロップシッピングは主に外部サービスと連携しますが、Shopify CollectiveはShopifyストア同士だけで成り立つ、限定されたエコシステムです。そのため、決済や注文管理もすべてShopifyの中で完結します。
このような特徴から、ドロップシッピングや無在庫販売とは似て非なるものと言えるでしょう。
Shopify Collectiveの基本的な仕組み
Shopify Collectiveには、利用する立場に応じて2つの役割があります。
小売ストア(リテーラー)
他のブランドの商品を自分のストアで販売できます。商品の登録は簡単で、注文が入ると供給元が直接お客様へ商品を発送してくれるため、在庫を抱える必要がありません。
供給ブランド(サプライヤー)
自分の商品を他のShopifyストアで販売してもらえます。注文が入った場合は、自社から出荷を行い、リテーラーへは卸価格での売上が計上されます。これにより、新しい市場や顧客層に自社商品を広めることが可能になります。
このように、Shopify Collectiveは小売と供給の両側にメリットをもたらす仕組みとなっています。そして、Shopifyストアオーナーは条件を満たせば、リテーラーとサプライヤーのどちらにもなれます。
Shopify Collectiveはアプリを通じて簡単に連携することができ、アプリの利用料は無料です。
Shopify Collectiveの利用条件

画像出典:Shopify Collective|Shopifyアプリストア
Shopify Collectiveは誰でもすぐに使えるわけではなく、一定の条件を満たしたストアだけが利用可能です。利用できる主な条件は以下の通りです。
- 有料プランを契約している
- Shopify Paymentsが有効になっている
- 地域の要件を満たしている
- 通貨が対応している
開発ストアや休止中のストア(Pause & Buildプラン)では利用できません。なお、日本および日本円はShopify Collectiveに対応しています。
加えて、小売ストアとサプライヤーが連携するには、以下の2点をクリアする必要があります。
- 小売ストアとサプライヤーが同じ国にある
- 小売ストアとサプライヤーが同じ通貨を使用している
つまり日本の小売ストアは、基本的に日本のサプライヤーと提携することになります。その他、Shopify Collectiveアプリの利用条件の詳細については、公式ヘルプページで確認してみてください。
なお、開発中のストアや休止中のストアでもアプリのインストールは可能で、どのようなサプライヤーが商品を提供しているかを確認できます。気になる方はアプリをダウンロードしてみましょう。

画像出典:Shopify管理画面
小売ストアがShopify Collectiveを利用するメリット5選
小売ストアがShopify Collectiveを利用するメリットを5つ紹介します。
在庫を持たずに商品を拡充できる
通常、新しい商品を仕入れて販売するには在庫を抱えるリスクがあります。しかしShopify Collectiveを利用すれば、在庫を自分で持つ必要がありません。
供給元のブランドが直接商品を発送してくれるため、資金繰りに余裕がなくても安心して品揃えを増やすことができます。
人気ブランドの商品を取り扱えることで顧客からの信頼を得やすい
無名の商品を販売する場合と比べ、すでに実績や認知度のあるブランドの商品を扱えるのは大きな強みです。顧客は「信頼できるブランドの商品がここでも買える」と感じ、購入につながりやすくなります。特に新しいストアでは、販売する商品の信頼性が集客やリピートに直結します。
売れるかどうかわからない商品をテスト販売できる
新しいジャンルの商品を取り入れるとき、「本当に売れるのか?」という不安はつきものです。Shopify Collectiveを使えば、在庫を抱えずに商品を掲載できるため、まずは小規模にテスト販売を行い、売れ行きを見ながら商品ラインナップを調整できます。失敗してもリスクが小さいのは大きな安心材料です。
仕入れロットが不要で、運営リスクが低い
一般的な卸売では「最低○個から仕入れ」といった条件があることも多いですが、Shopify Collectiveでは1点から販売可能です。小規模なショップでも気軽に取り入れることができ、資金や在庫スペースの制約を気にせず新しい商品を追加できます。
Shopify内で注文から決済まで完結できる
商品登録、在庫の同期、注文の処理、支払いまで、すべてShopifyの仕組みの中で完結します。外部システムを使ったり、複雑な連携をしたりする必要がないため、ストア運営に集中できます。効率的な運営を求める方にとって、大きな利点となるでしょう。
サプライヤーがShopify Collectiveを利用するメリット5選
続いて、サプライヤーがShopify Collectiveを利用するメリットも5つ紹介します。
新しい販路を低コストで獲得できる
通常、新しい販売チャネルを開拓するには広告費や営業活動が必要です。しかしShopify Collectiveを使えば、自社商品を他のストアで取り扱ってもらうだけで販路が広がります。追加コストを抑えながら売上を伸ばせるのは、大きな魅力です。
自社の集客に頼らず新規顧客に商品を届けられる
小売パートナーが販売してくれることで、これまでリーチできなかった顧客層にも商品を届けられます。たとえば、自社はベビー用品ブランドで、小売パートナーがライフスタイル雑貨を販売していれば、全く新しい顧客層に商品を知ってもらえる可能性が広がります。
卸売のような複雑な契約なしで、手軽に販売提携できる
従来の卸売では、契約書の取り交わしや最低ロット数などが必要になることもあります。Shopify Collectiveは、Shopify上で商品や価格を設定するだけで提携が始められるため、手続きがシンプルです。スピーディに販売先を増やしたいブランドにとって使いやすい仕組みです。
ブランド認知度の向上につながる
他のストアで自社の商品が販売されることで、自然とブランドの露出が増えます。新しい市場や異なる顧客層に商品を見てもらえるため、直接の売上だけでなく、ブランド自体の認知度を高める効果も期待できるでしょう。
Shopify内で売上管理や入金処理が完結する
取引の売り上げや入金もShopifyの仕組みを通じて処理されます。外部システムを使わなくても売上管理ができるため、経理や会計の手間も減り、効率的に事業を運営できます。
Shopify Collectiveを利用して商品を販売する手順
ここでは主に条件を満たしている小売ストアが、Shopify Collectiveを利用して商品を販売する手順を簡単に紹介します。基本の販売手順は以下の通りです。
- Shopify Collectiveアプリをダウンロードする
- 取り扱いたい商品・サプライヤーを探す
- サプライヤーに「アクセス権をリクエストする」でリクエストを送る
- サプライヤーから承認されると取り扱い可能になる
リクエストは必ず承認されるわけではありません。サプライヤー側も、ストアのコンセプトや信頼性などを確認して承認を行います。
気になった方は、まずShopify Collectiveアプリをダウンロードしてみましょう。

画像出典:Shopify Collective|Shopifyアプリストア
Shopify Collectiveを利用する際の注意点
Shopify Collectiveは便利な仕組みですが、利用にあたっては知っておくべきポイントがあります。導入前に理解しておくことで、トラブルを防ぎ、スムーズな運営につながるでしょう。
商品価格の設定はサプライヤーが行う
Shopify Collectiveの商品価格はサプライヤーが設定し、自動的に自社ストアへ同期される固定価格です。小売ストア側で直接変更することはできません。サプライヤーが価格を変更すると、その内容は自動でストアにも反映されます。もし自社の価格戦略と合わない場合は、サプライヤーに直接相談する必要があります。
配送や返品対応はサプライヤー依存になる
商品の発送や返品対応はサプライヤーが行うため、小売側は対応をコントロールできません。配送スピードや返品ポリシーが顧客満足度に直結するので、信頼できるサプライヤーを選ぶことが不可欠です。
デジタル製品やギフトカード製品はサポートしていない
Shopify Collectiveで取り扱えるのは、物理的な商品に限られます。デジタルコンテンツやダウンロード商品、ギフトカードといったデジタル製品は対象外です。
Shopify Collectiveを活用してストア / ブランドのさらなる成長を目指そう
この記事ではShopify Collectiveについて、概要や利用の条件、利用メリットや注意点などを解説しました。
Shopify Collectiveは、小売ストアにもサプライヤーにも多大なメリットがある仕組みです。うまく活用すれば、ストアやブランドを大きく成長させるきっかけとなるでしょう。一方で、利用には注意点もあり、自社にぴったりのパートナーを見つけることが重要です。
今回の内容を参考に、Shopify Collectiveが自社の戦略に合うかどうかを検討し、合うようであればぜひ挑戦してみてください。