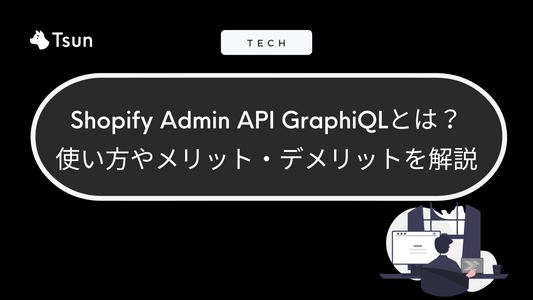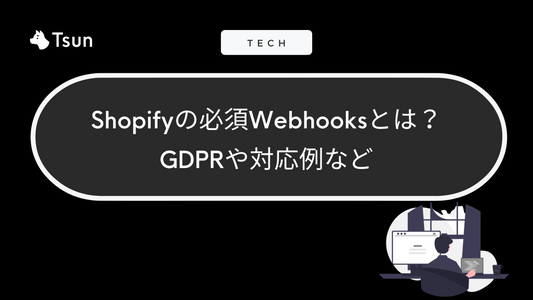自社サイトの他にECモールへの出店を検討している事業者の方々は必見!
自社の売上を伸ばしたいと考えたとき、販路拡大のために自社サイト以外にも集客力のあるECモールへの出店を考えるショップオーナーも多いでしょう。それぞれのECモールには異なる特徴があり、出店を成功させるためにはしっかりとした事前リサーチと準備が必要です。
本記事では、ECモールへの出店について実際の知見を交えて詳しく解説します。出店の目的別におすすめのモールや特徴も紹介します!
ECモール出店前に確認必須の3つのポイント
ひとことにECモールといっても、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングといった主要3大ECモールから、Qoo10・aupayマーケット・ANAモールといった、やや規模が小さいECモールまでさまざまあります。どのECモールもそれぞれの特徴が大きく異なるため、それぞれの違いを知った上で出店先を判断する必要があります。
ここでは、ECモールへ出店する前に確認するべき3つのポイントを紹介します。
1.ECモールへ出店するメリット・デメリット・注意点を知る
まずはECモール出店のメリット・デメリットを確認しましょう。追加でかかるランニングコストや出荷オペレーションなど、実際の業務のシミュレーションを具体的に行うことで、ECモールに本当に出店すべきかどうかの判断の助けになります。場合によっては、ECモール出店の費用対効果が合わない恐れもあります。
また、法令上は問題ないことでも、ECモールのレギュレーションにより、自社サイトではできるけどECモールではできないこともたくさんあります。そういった情報も事前に把握しておきましょう。
2.出店を検討しているECモールの特徴を知る
同じ”ECモール”でも、Amazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングではそれぞれの売上規模も訪れるユーザー層もランニングコストも異なります。細かい点でいえば、使える広告・販促ツールの種類、モール内検索アルゴリズム、商品登録の方法なども異なっています。
そのため、まずは出店を検討しているECモールの特徴を知り、何ができて何ができないのかをしっかりと研究しましょう。
主要ECモールの特徴について、詳しく知りたい方はこちらの記事をご覧ください。
3.ECモールに出店する目的を定める
たくさんあるECモールの中から自社に合うモールに出店するためには、出店する目的を明確に定めることが大切です。
目的を明確にせずに出店すると、ECモールではやりたかったことができないことに後で気づいたり、いざ出店してみてもただ漫然とランニングコストだけがかかってしまったりと思わぬ失敗をしてしまう恐れがあります。
事前に目的を明確にしておくことで、ECモールに出店するべきか、あるいはどのECモールに出店するべきかを判断しやすくなります。
ECモール出店の注意点は?
ECモールへの出店は、プラットフォーム自体が持つ高い認知度のおかげで出店店舗の認知度やブランド力が低くてもある程度の集客が見込めるという大きなメリットがあります。一方で、事前に把握しておくべき注意点が2つあります。
1.ランニングコストがかかる
ひとつは、出店手数料・販売手数料・決済手数料といったランニングコストが大きいという点です。
出店するECモールや、ショップの売上規模によってかかる費用の割合や内訳は異なりますが、多くのケースにおいて売上に対して10%前後の費用がかかると考えておいた方が良いでしょう。
2.実施できる施策の幅が狭い
もうひとつは、自社サイトでの販売と比較して、実施できる施策の幅が狭くなるという点です。
ECモールの商品ページの型はパターンが決まっており、自社サイトのように自由な作り込みができません。また、個別にステップメールやアップセル同梱物を送るようなCRM施策もしづらく、ECモールのレギュレーション上、自社サイトへ誘導するような施策もほぼできない点にも注意が必要です。
Amazon・楽天・Yahoo!の3大ECモールの特徴
販路を拡大して売上を伸ばすことを考えたとき、多くの場合でAmazon・楽天市場・Yahoo!ショッピングといった主要3大ECモールへの出店を検討するのではないでしょうか。どのモールに出店すべきかを考える前に、まずは各ECモールの特徴を理解しておきましょう。
Amazonの特徴
Amazonはマーケットプレイス型のモールで、複数の店舗がひとつの商品ページに出品する形態です。対して楽天やYahoo!ショッピングは、各ストアそれぞれがストアページを持って商品を販売していくテナント型の販売形態をとっています。
Amazonでは、低価格で配送速度が速い店舗が注文を獲得しやすい構造になっているのが大きな特徴です。
最短3営業日で出店審査が完了
Amazonは必要な情報が揃い審査がスムーズに進めば、最短3営業日程度で審査が完了し、おおよそ3〜4週間程度で出品できるくらい速やかに出店ができます。ただし、情報が揃わずに審査期間が伸びるケースもあるので、余裕を持ったスケジュールを設定してくと良いでしょう。
なお、出店手続きに関するサポートは楽天やYahoo!ショッピングに比べて手薄なため、煩雑な事務手続きが苦手な場合は代行業者に依頼するのも良いでしょう。
配送代行サービスが利用できる
もうひとつの大きな特徴は、配送代行サービスであるFBA(Fulfillment by Amazon)が利用できるところです。FBAは配送関連業務をAmazonに委託する有料サービスです。これによりストアは、商品の在庫保管や梱包・出荷作業、返品対応といった配送に関わる一連の業務をAmazonに任せることができます。
楽天市場の特徴
楽天の大きな特徴は、楽天カードを始めとする楽天グループのサービスを利用している楽天経済圏のユーザーを取り込んでいるところにあります。これにより、楽天は他のECモールと比べて高い集客力を実現可能にしています。
出店審査に時間がかかる
楽天は他のECモールに比べて出店審査やストアの運営ガイドラインが非常に厳しく、出店が完了するまでに時間がかかるのも特徴です。手続き開始から無事に出品ができるようになるまでに、おおよそ3〜4ヶ月程度は見込んでおいた方が良いでしょう。
また、楽天は他のECモールと比べてもレギュレーションがかなり厳しいため、無事に出店してからも出品や販促活動において制約を受けることが比較的多い点にも留意が必要です。
配送代行サービスが利用できる
もうひとつの特徴は、配送代行サービスである楽天スーパーロジスティクス(RSL)が利用できるところです。RSLは配送関連業務を楽天に委託する有料サービスです。これによりストアは、商品の在庫保管や梱包・出荷作業、返品対応といった配送に関わる一連の業務を楽天に任せることができます。
Yahoo!ショッピングの特徴
Yahoo!ショッピングの最大の特徴は、モール出店に際する初期費用と月額固定費がかからないことです。楽天では出店手数料と月額固定費が、Amazonは大口出品の場合月額固定費がかかるのに対して、Yahoo!ショッピングは売上が発生しない限り費用が発生しません。そのため、開店資金のないショップオーナーでも出店できるのが大きな特徴です。
ただし、出店手数料と月額固定費が無料な分、販促費や広告費・媒体費が他ECモールと比べて大きくなる点には注意が必要です。
自社サイトへ誘導できる唯一のモール
集客力の観点ではAmazonや楽天と比べて劣っていますが、paypayポイントユーザーやYahoo!JAPANからの流入が見込める点は特徴といえます。また、Yahoo!ショッピングでは店舗内のページに外部リンクを設置することができるため、主要3大ECモールの中ではモール内から自社サイトへ誘導できる唯一のECモールといえるでしょう。
目的別|自社サイトの次に出店するECモールの選び方
ECモールへの出店を成功させるためには、何のために出店するのか目的を明確に定めることが大切です。出店目的とECモールの特徴を照らし合わせて、実現したいことができるのかを事前に確認しましょう。
ここでは、目的別に適したECモールの選び方について解説します。
ブランドの世界観を伝えたい:楽天市場
ブランドの世界観を伝えることを重視したい場合は、楽天市場をおすすめします。
楽天は、主要3大ECモールの中では最も商品ページやストアトップページの作り込みがしやすいECモールです。商品ページの表示形式のテンプレートが複数あり、他のECモールと比べてカスタマイズ性が高くLPテイストのページ作りがしやすいため、ブランドの世界観・ストーリーを伝えながら販売したいショップオーナーには最適です。
また、楽天GOLDという機能を使用することで、デザイン性の高いストアトップページを作ることができることも楽天の特徴です。
一方、AmazonやYahoo!ショッピングはブランドの世界観を表現するのには適しません。Amazonにも商品ページでブランドの世界観を表現できる「Aプラスコンテンツ」という機能がありますが、楽天と比べてカスタマイズ性が低い点がマイナスポイントです。
Yahoo!ショッピングも商品説明欄にてLPのようなデザインを組むことができますが、Yahoo!ショッピングの商品説明欄はデフォルトで折り畳まれて一部しか表示されない仕様になっています。そのため、商品への興味がある人でないと見てもらえず、ブランドの世界観を伝えることを目的とする場合は不向きといえるでしょう。
売上拡大を重視したい:楽天市場かAmazon
売上を伸ばすことを重視したい場合は、楽天市場かAmazonをおすすめします。
楽天もAmazonもモール自体の認知度が高く売上規模も大きく、集客力の大きいECモールといえます。売上拡大を目的にする場合は、より多くのユーザーが集まるプラットフォームに出店しましょう。
広告の観点で見ても、楽天はRPP広告、Amazonはスポンサー広告といった検索キーワードに応じた露出をする検索連動型の広告が利用できるため、ブランド認知が低い状態でも売上を伸ばす可能性があるECモールといえます。
なお、海外への販路拡大を検討している場合は、 Amazon FBAを活用することで海外配送ができるためAmazonに軍配が上がります。
一方、Yahoo!ショッピングは、モール自体の売上規模が主要3大ECモールの中で最も少なく、楽天市場の約25%程度のため、集客力の観点でいえば主要3大ECモールの中では劣ります。出店時の初期費用がかからないという大きなメリットはありますが、売上拡大を目的とする場合は第一選択としてはあがらないでしょう。
楽天とAmazonのどちらが良い?
楽天とAmazonのどちらにすれば良いか迷ったときは、最安値で出品できるなど価格優位性があるならAmazon、ないのであれば楽天という選び方が良いでしょう。
Amazonはひとつの商品に対して複数の店舗がカートボタンを奪い合う仕様になっていて、より販売価格が安く、より配送速度が速い店舗が売れる仕組みになっています。そのため、価格競争に勝てる店舗でないと売上を伸ばすことが難しいことが特徴です。
楽天は他店舗と同じ商品を出品していても、検索結果には店舗ごとの商品ページが表示されるため、最安値でなくともAmazonよりアクセス数が取りやすい傾向にあります。
したがって、他社製品を入荷して販売するケースや自社製品であっても他社に卸しているケースでは楽天が向いており、価格競争に確実に勝てるケースではAmazonに出店する方が向いています。
競合の情報を得たい:楽天市場かYahoo!ショッピング
ただ販路を拡大するのではなく、競合店舗・競合商品の情報を得て自社サイトのマーケティング戦略にも活かしたいと考えている場合は、楽天かYahoo!ショッピングがおすすめです。
楽天とYahoo!ショッピングの特徴として、売上規模が一定の金額を超えるとモールの担当コンサルタントがつきます。コンサルタントは、店舗の売上拡大につながるのであれば、競合店舗・競合商品と比べて何が劣っていて何が優っているのかを分析してくれる上に、競合商品がどのようにして売上を伸ばしていったのかを教えてくれることもあります。
ベンチマークとしている店舗や商品が楽天・Yahoo!ショッピングに出品している場合は、モールのコンサルタントを通じて情報を得られる可能性があるため、出店を検討するのも良いでしょう。
なお、楽天もYahoo!ショッピングも、一人のコンサルタントが担当する店舗は数十から多くて数百にまでのぼるため、売上規模が小さい店舗はサポート優先度が下がりやすく、売上規模が大きい店舗ほどサポートが手厚くなる傾向があります。特に昨対比の売上が200%以上出せている場合や、月商が1,000万円を超える場合はサポートが手厚くなる傾向があります。楽天の場合は、月商1億円を超えるとマネジャークラスのコンサルタントがつく可能性が高くなるので、より幅広い情報を得ることができます。
Amazonの場合は、売上規模が月商数千万円以上のような大型店舗にならないとマーケティングに関するアドバイスをしてくれるようなコンサルタントが付きにくいため、競合店舗・競合商品の情報を得ることを目的とした出店はおすすめできません。
フルフィルメントサービスを使いたい:Amazonか楽天市場
倉庫機能や配送代行などのフルフィルメントサービスを使いたい場合は、Amazonか楽天に出店することをおすすめします。
AmazonにはFBA(Fulfillment by Amazon)という、商品の保管からピッキング、梱包、発送、返品対応といったフルフィルメント業務を委託できるサービスがあります。売上を拡大したいけど保管場所がなく、倉庫を借りる予算もないといったショップオーナーは、FBAの利用を目的としてAmazonに出店するのも良いでしょう。
FBAは、Amazonセラーセントラルに出品できているなら、販売開始の日付をかなり先にするなど少し特殊な設定をすれば、Amazonで販売していなくても利用できるため、自社サイトでのみ販売したい商品も保管できるところはメリットのひとつです。また、カスタマーサポート対応もしてもらえる点も大きなメリットです。
楽天も楽天スーパーロジスティクス(RSL)という、AmazonのFBAと似たフルフィルメントサービスを展開しています。サービスの大枠はFBAと同じですが、RSLではカスタマーサポート対応はしてもらえない点で異なります。
ただし、Amazon FBAもRSLも、果物や野菜といった生鮮食品や冷凍食品などの期限管理や温度管理が必要な商品の取り扱いには注意が必要です。
なお、Yahoo!ショッピングもヤマト運輸と連携したフルフィルメントサービスを導入していましたが、2025年2月20日をもってサービスが終了となったため、倉庫機能を活用したい場合は非推奨のECモールとなります。
Amazon FBAと楽天スーパーロジスティクス(RSL)の違い
Amazon FBAとRSLはいずれもフルフィルメント業務を委託できるサービスですが、それぞれカバー領域が若干異なるため、目的や取り扱い商品によってどちらのサービスを利用するかを使いわけましょう。具体的な違いは以下の通りです。
| サービス名 | Amazon FBA | RSL |
|---|---|---|
| 配送料金 | Amazon向けの出荷と他ECモール向けの出荷で異なる | 楽天向けの出荷も他ECモール向けの出荷も料金は同じ |
| 消費期限管理 | 対応 | 有料オプションにて対応可 |
| 海外への出荷 | 対応 | 有料オプションにて対応可 |
| カスタマーサポート | 対応 | 非対応 |
| 配送速度:通常配送 | 明確な期日設定なし | 遅くても翌日中に出荷 |
| 配送速度:翌日配送 | 注文確定日から3日以内での商品のお届け | 当日15:30までの注文で最短翌日お届け |
| 配送速度:当日配送 | 一部エリアでのみ対応 | 非対応 |
自社サイトと合わせてECモール出店を検討!
ECモールへの出店は、自社サイトとは異なる集客力や販売機会を得られる一方で、ランニングコストやレギュレーションの制約もあるため、慎重に選ぶことが大切です。
商品や業種にもよりますが、ブランドの世界観を重視するなら楽天市場、価格競争力があるならAmazon、固定費を抑えて出店したいならYahoo!ショッピングをおすすめします。各モールの特徴を理解し、自社の戦略に合った販路拡大を進めましょう!