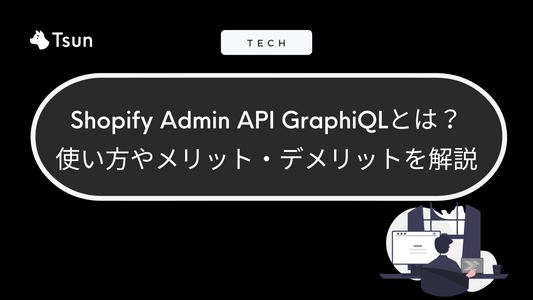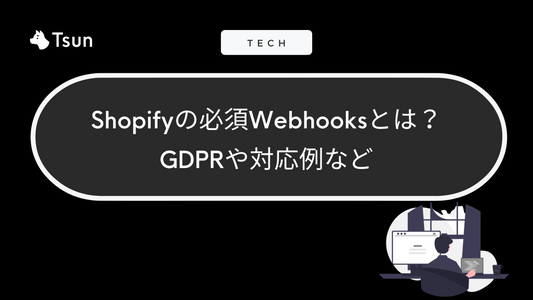「自分で育てた野菜をネット販売してみたい!」と思ったことはありませんか?近年、個人でも手軽に野菜を販売できる環境が整い、多くの人がネット販売に挑戦しています。
しかし、「どの方法がいいのかわからない」「本当に売れるの?」といった不安を抱える方も多いはず。実際、ネット販売にはメリットもありますが、集客や在庫管理などの課題もあります。
この記事では、個人が野菜のネット販売を始める方法や注意点、成功するためのポイントを詳しく解説します。さらに、実際にネット販売で成功している農家の事例も紹介するので、ぜひ参考にしてください!
野菜のネット販売が個人にオススメな3つの理由
コロナ禍をきっかけにEC市場が拡大し、消費者が新鮮な野菜をオンラインで購入する機会が増えました。また、直売所に足を運ばずに野菜を手に入れられる便利さから、ネット販売の需要は今後も高まり続けるでしょう。
では、なぜ個人でも野菜のネット販売がオススメなのか? ここでは、3つの理由を紹介します。
理由1. 余剰野菜や規格外品を有効活用できる
野菜のネット販売は、これまで廃棄していた野菜を収益につなげる絶好のチャンスです。
市場や直売所では「形が不揃い」「キズがある」といった理由で売れない野菜も、ネットならその価値を理解してくれる人に直接届けられます。
また、生育過程で間引いた野菜や、収穫期の終わりに余った野菜も販売対象です。このような取り組みは、フードロス削減にも貢献でき、社会的な課題の解決につながります。
理由2. 価格を自由に設定し利益率を確保できる
市場価格に縛られず、自分で価格を決められるのもネット販売の魅力のひとつです。
直売所や市場では、価格競争の影響を受けやすく、思ったように利益が出ないこともあるでしょう。しかしネット販売では、こだわりの栽培方法や品質の高さをしっかり伝えることで、適正な価格で販売できます。
さらに、ブランディングを進めることで高単価販売にもつながります。「無農薬」「有機栽培」など、付加価値を打ち出せば、より良い条件で販売できるでしょう。
もちろん、ただ高い値段をつければいいわけではなく、消費者が納得できる価格設定が大切。そのためにも、商品の魅力をしっかり伝える工夫が求められます。
理由3. 全国の人に野菜を届けられる!
ネット販売の最大の魅力は、全国どこにでも販路を広げられる点です。
直売所などの対面販売では、地域の顧客に限定されてしまいますが、ネット販売を活用すれば、全国各地に自分の野菜を届けられるようになります。
例えば、沖縄の島野菜を北海道の消費者に販売したり、過疎地域の特産野菜を都市部の高級レストラン向けに販売したりすることで、新たな市場を開拓することができます。
定期購入やリピーターを獲得すれば、安定した売上につながる可能性もあるのです。
知っておこう!個人で野菜をネット販売する際の3つの注意点
野菜のネット販売には多くのメリットがありますが、「お店を開設したのに売れない」「思った以上に作業が大変」「売れ残りが発生してしまった」など、実際に始めてから困ることも少なくありません。ここでは、個人で野菜をネット販売する際に気をつけるべき3つのポイントを紹介します。
デメリット1. 自分で集客をする必要がある
ネット販売は実店舗とは異なり、お店を構えたからといって自然に顧客が集まるわけではありません。そのため、積極的に集客活動を行うことが必要です。
例えば、Instagramに野菜の写真や栽培風景を投稿することで、商品の魅力を伝えられます。また、ターゲットを絞ったWeb広告を活用すれば、関心を持つ人に的確にアプローチできます。
ただし、集客には時間と労力がかかるため、継続的な努力が必要です。
デメリット2. 野菜の管理や配送の手間が増える
個人でのネット販売は、受注から発送までの一連の作業をすべて自分で行う必要があるため、手間がかかります。
また、梱包、発送作業、顧客対応など、販売以外にもさまざまな業務が発生します。特に繁忙期には注文が集中し、作業量が増えることもあるため、効率的な業務フローを考えましょう。
デメリット3. 売れ残りのリスクを考える必要がある
野菜は生鮮食品のため、売れ残ると廃棄につながるリスクがあります。
需要を正確に予測するのは難しく、天候による収穫量の変動など、不確定要素も多くあります。そのため、適切な在庫管理が欠かせません。
売れ残りを防ぐための工夫として、予約販売を取り入れる方法があります。また、加工品として販売することで、消費期限を延ばす工夫も効果的です。さらに、フードバンクへ寄付することで、食品ロス削減にも貢献できます。
個人で野菜を販売する4つの方法
野菜のネット販売を始めたいけれど、「どの方法がいいのかわからない」「どこで売るのが成功しやすいの?」と悩んでいる人も多いのではないでしょうか。
ここからは個人で野菜を販売する場所として活用できるプラットフォームを4つご紹介します。
方法1. モール型ネットショップで手軽に販売!

画像出典:楽天市場
Amazonや楽天市場などの大手ECモールを利用する方法です。
すでに多くの消費者が利用しているため、集客しやすいのが魅力です。また、決済や配送システムが整っているため、初心者でもスムーズに販売を始められます。
一方で、出店料や手数料が高めな点や、競争が激しく価格競争に巻き込まれやすい点には注意が必要です。特に、同じような野菜を販売する出品者が多い場合、差別化が求められます。
方法2. 野菜専門の販売サイトで売る!

画像参考:食べチョク
食べチョクやポケットマルシェなどの農産物専門の販売サイトを活用する方法です。
こうしたサイトには、農家から直接購入したいと考える消費者が集まるため、こだわりを持つ顧客に向けて販売しやすいのが特徴です。
また、生産者のストーリーや農法を伝えられるため、単なる商品の売買ではなく、ファンづくりにもつながります。
ただし、大手ECモールに比べると知名度が低いため、出品後も自分で情報発信を行い、顧客とのコミュニケーションを大切にすることが成功のポイントです。
農産物専門の販売サイト例
| サイト名 | 特徴 |
|---|---|
| 食べチョク | 全国の農家や漁師が出店できる国内No.1の産直通販サイト。認知度・利用率が高く、100万人以上のユーザーにアプローチできます。販売手数料は8〜18%で、送料の割引も受けられるためコストを抑えた販売が可能です。 |
| ポケットマルシェ | 生産者と消費者が直接つながるCtoC型のプラットフォーム。スマホ1つで出品から管理まで完結し、送料も個人取引より安く抑えられます。手数料は売上の23%。 |
| 農家直売どっとこむ | 長野大同青果株式会社が運営するプラットフォーム。青果仲卸業者としてのノウハウを活かし、適正な価格での販売をサポートしています。生産者の負担を軽減しつつ、全国への販路拡大を目指せます。 |
方法3. 自分のネットショップを作って自由に販売!

画像出典:Shopify
ShopifyやBASEを活用して、自分だけのネットショップを開設する方法もあります。
自社サイトなら、販売手数料を抑えられるうえ、デザインや販売方法を自由に決められるのがメリットです。ブランドの世界観を表現しやすく、自分のこだわりを伝える場として活用できます。
ただし、集客を自分で行う必要があり、運営にはある程度の知識も求められます。SEO対策やSNSの活用など、販売促進のための工夫が重要になります。
下記のブログ記事ではShopifyのアカウント登録からストア開設までの流れをご紹介しています。ぜひご参考にしてください。
方法4. フリマアプリを使う

画像出典:mercari
メルカリなどのフリマアプリで野菜を販売する最大の魅力は、手軽に出品でき、すぐに販売を開始できる点です。購入者とのやりとりもしやすく、価格交渉ができるため、柔軟な販売ができます。また、少量の野菜や余った食材でも気軽に出品できるのもメリットの一つです。
要確認!野菜ネット販売で守るべき3つの法律
ネットで野菜を販売しようと思ったら、事前に知っておくべきルールがあります。
知らずに販売を始めてしまうと、法律違反になることもあるため、しっかり確認しておきましょう。今回は、野菜を販売する上で特に重要な3つの法律「食品表示法」「特定商取引法」「食品衛生法」について解説します。
ポイント1. 食品表示法:正しい表示で安全な取引を!
野菜を販売する際は、消費者に正確な情報を伝えることが義務付けられています。食品表示法に基づき、次の項目を記載する必要があります。
<表示すべき項目>
- 名称
- 原産地
消費者が安心して購入できるように、正しい情報を明記しましょう。なお、食品表示に関する詳細は食品表示.comをご覧ください。
ポイント2. 特定商取引法に基づく表記:信頼を得るための販売ルール!
販売者と消費者の間でトラブルを防ぐためのルールとして特定商取引法に基づく表記が義務付けられています。
個人でネットショップを開設する場合は、必ず表記しなければなりません。
<表示すべき項目>
- 販売業者の氏名(または法人名)
- 住所
- 電話番号
- 販売価格
- 代金の支払い方法
- 商品の引渡し時期
- 返品・キャンセルの条件
ポイント3. 食品衛生法:安全な食品を提供しよう!
食品衛生法は食品の安全性を確保するための法律です。野菜を加工して販売する場合は、食品衛生法に該当します。個人で生鮮野菜を販売するケースでは食品衛生法には該当しません。
しかし、生鮮野菜で食中毒を起こさないためにも農林水産省のガイドラインをチェックしておくことを推奨します。
1.温度管理と殺菌 生野菜は低温で流通する際に、意図しない微生物が増殖する可能性があるため、適切な温度管理と殺菌処理が必要です。特に、カット野菜などを販売する場合は、冷蔵管理を徹底し、消費者に安全な状態で届けなければなりません。
2.営業届出制度(2021年改正) 食品衛生法の改正により、野菜や果物を販売する事業者は保健所への届出が義務化されました。ネット販売をする際も、保健所への届出が必要となるため、事前に管轄の保健所に相談しておくことが推奨されます。
3.衛生管理の注意点(特に生食用野菜) 生で食べる野菜を販売する場合、次のような衛生管理が必須です。
- 水の管理:洗浄に使用する水は衛生的であることを確認する
- 家畜ふん堆肥の適切な管理:土壌や肥料による微生物汚染を防ぐ
- 作業者の手洗いの徹底:収穫・梱包時の衛生管理を徹底し、汚染リスクを低減
-
微生物による危害の低減 生鮮野菜は微生物による食品安全上のリスクが伴います。そのため、農林水産省が策定した「生鮮野菜の微生物リスク低減ガイドライン」に基づき、適切な管理を行うことが求められます。例えば、収穫後の洗浄や温度管理の徹底が、微生物の増殖を防ぐために重要な対策となります。
-
農産物の加工に関する規定 農家や生産者団体が行う農産物の簡易な加工(例:カット野菜、乾燥野菜、ジュース作りなど)も、食品衛生法の適用対象となります。
詳しくは農林水産省のページをご覧ください。
野菜ネット販売の事例
ここではShopifyを使って野菜のネット販売をおこなっている農園をご紹介します。ぜひショップ作りの参考にしてください。
あかね農園

画像参照:あかね農園
あかね農園は、社会福祉法人あかねが運営する農園です。介護施設や保育園を運営する中で、「本当に体に良い食品を届けたい」という想いから、2011年に自家農園をスタートしました。「本当に体に良い食品」を提供するため、農薬や化学肥料を使用しない農法を採用。小さな子どもから高齢者まで安心して食べられる野菜を提供しています。
曽我農園

画像参照:曽我農園
曽我農園(SOGA FARM)は、新潟県新潟市北区濁川地域でトマト栽培を行うフルーツトマト専門の農家です。「日本一おいしいトマトをつくりたい」という想いのもと、選んだのは希少なファースト系品種。一般的なトマトよりも栽培が難しく、手間がかかる品種ですが、赤くて小ぶりながらも濃厚な甘みと深い味わいが特徴です。さらに、曽我農園が生み出した「越冬トマト」は、通常のトマトの旬とは異なり、寒暖差の激しい冬から春にかけて育ちます。テレビやSNSで取り上げられるなど評価は高く、野菜ソムリエサミットで大賞を受賞。生産量は限られるものの、その希少価値と味わいで多くのファンを魅了しています。
ネット販売で販路拡大!あなたの野菜を全国に届けよう
野菜をネットで販売する方法は、以下の4つです。
- Amazonや楽天市場といった大手ECモールを利用する
- 食べチョクやポケットマルシェといった専門販売サイトを利用する
- ShopifyやBASEといったECプラットフォームを活用して自社サイト作る
- メルカリなどのフリマアプリで野菜を販売する
また、安全な販売のためには、食品表示法や特定商取引法などの法律を守ることが大切です。ネット販売を始める際は、自分の野菜の特徴を見極め、どの方法が適しているかを考えながら進めていきましょう。