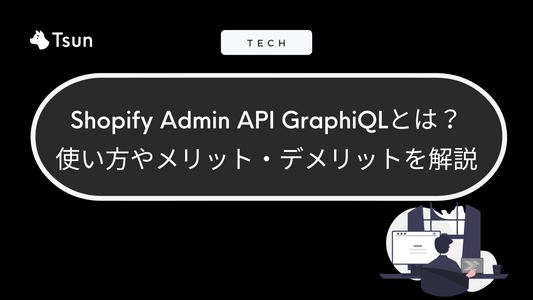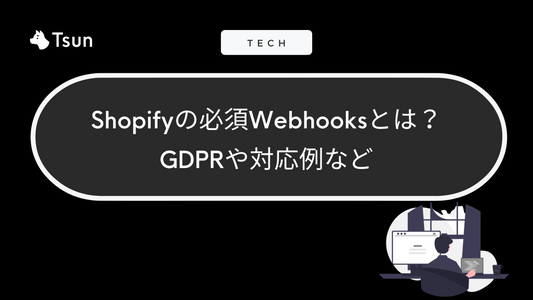Shopify事業者のインタビュー特集。「書くこと」の価値を再発見させてくれる文房具ブランド、Kakimori(カキモリ)。その世界観や店舗づくりには、文房具業界の常識にとらわれない独自の視点が息づいています。
今回のインタビューでは、Kakimoriを運営する株式会社ほたかの代表取締役 広瀬琢磨さんに、創業背景からEC活用の現在、そして越境展開への挑戦まで、じっくりとお話を伺いました。

(株式会社ほたか 代表取締役 広瀬琢磨さん Photo by Miki Chujo)
「とりあえずやってみた」webショップの失敗
ーー 広瀬さん、本日はよろしくお願いします。まずは、今のKakimoriに至るまでの経緯をお伺いできますでしょうか。
広瀬さん もともと祖父が群馬の高崎で文房具店をやっていて、私は三代目にあたります。私は当時、外資系の医療機器メーカーに勤めていて、家業は父がやっていました。そんな中、会社が東京の文具・事務用品の販売店である株式会社ほたかを買収することになり声がかかって、前の仕事を辞めたい気持ちもあり軽い気持ちではいったのがスタートです。26歳のときでした。
当時の会社は、官公庁向けの御用聞き型営業。営業が毎日出向いて注文をとって、紙で伝票を回してという流れでしたが、これはダメだなとすぐに感じました。
アスクルやたのめーるといったオンラインやカタログ通販が急激に普及して業界自体が劇的に変わっていったんですよね。ほとんどの購買がウェブとかカタログ通販に切り替わって、従来のメーカー→問屋→小売という流通3段階のモデルが一気に崩れました。その流れに対応しようとしたものの、やはり間に合わなかった。社内の平均年齢も50歳を超えていましたし、いろいろ手を尽くしたけれど、買収した会社の業績は全然変えられなかったのが最初の2〜3年でした。
そうして、BtoCならまだいけるかもしれないと思い、ネットショップとして「ステーショナリーステーション」という、いま思うとかなりダサい名前の店を立ち上げました。(笑)ですが、それも大失敗でした。
ーー ネットショップの失敗の理由はどこにあったのでしょうか。
広瀬さん BtoCに参入したタイミングは悪くなかったのですが、オリジナリティがまったくなかったんです。ネットショップも、唯一の若手スタッフと「やってみようか」と勢いで始めたもので、すべてが中途半端でした。在庫リスクを避けるために自分たちで在庫を持たず、どこかのカタログに載っている商品写真をそのまま転載して注文が入ってから仕入れる、みたいなやり方でした。どこでも手に入る商品をただ並べただけのサイトで、売れるはずがなかった。
「SEO対策30万円で必ず上位表示されますよ」と言われて、信じてしまったりして。いろいろ騙されながら、お金をどんどん使ってしまった苦い思い出もあります。当時の売上も月3,000円とかその程度でしたね。
―― 今のKakimoriの世界観からは想像がつかないですね。
広瀬さん 振り返ると、「自分が何を売りたいか」「どんな価値を提供したいか」がまったくなかったですね。とにかく“Webに載せれば何とかなるだろう”という甘い考えでした。その後、webショップは半年くらいで完全閉鎖しました。
オンラインでできない価値提供への舵切り
広瀬さん いわゆる「書く楽しさ」に特化した店舗をつくって、リアルで勝負する方向に大きく舵を切ったのはそこからです。
BtoBはもともと厳しく、BtoCも片手間で始めたような形だったので、上手くいかない。だからこそ、もう一度やるなら、オンラインでできないことをやろうと思ったんです。
僕自身、デジタルで代替できるものはどんどんデジタル化すべきだと思っていて、そんな中でも残る価値、「手書きで書く」価値は大切にしたかった。手紙もそうですし、僕の場合はアイディアを手で書き出すということを大学時代や社会人になってからもずっと大切にしていました。そうした書くことに特化した文房具屋があったらいいな、と思ったんです。
当時はまだ20代だったので、その時の自分の感覚に合うようなお店がほしかった。筆記具専門店のようなショーケースがあって、スーツ姿の人が万年筆を試しながら話すような、敷居の高い雰囲気にはあまり興味が持てませんでした。
もっと「書く楽しさ」にフォーカスしたお店が作れないか。そう考えて始めたのが、Kakimoriでした。

(蔵前のKakimori店舗)
広瀬さん Kakimoriを2010年にオープンして、当初は完全にアナログ。SNSもすごく遅れていて、始めたのは2016年くらいだったと思います。Twitter(現X)は少し早かったかもしれませんが、Instagramはかなり遅かった。Webページは外部のアートディレクターとしっかり作っていましたが、ECやWebマーケティングには弱い会社だったと自覚しています。
ただ、ありがたいことに店舗に取材をたくさんいただくようになり、アナログなメディア経由でお客さんがどんどん増えていった。その結果、実店舗がキャパオーバーになりはじめ、「リピート購入がWebでできたらいいのに」という声も増えてきた。
そこでようやく、2018年にShopifyでECサイトを立ち上げました。
2018年、Shopify黎明期の導入の決断。EC再始動が始まる
ーー 2018年当時は、まだShopifyが今ほど認知されていない状況かと思いますが、かなり早い段階で選択されたんですね。
広瀬さん Kakimoriでは2015年から台湾などでイベントをしたり、インバウンド対応もしていたので、ゆくゆくは越境ECに挑戦したいと考えていました。ブランディングも進めていたし、しっかりしたECサイトを作りたいという意識があったので、当時はBASEやSTORESなどもありましたが、Shopifyを選びました。
当時のタイミングでShopifyを選んだのは良かったなと思っています。
Shopifyは北米では有名だったけど、日本ではまだまだ認知度が低い状態だったので、Shopifyの人自体がKakimoriの事を認識してくれて記事にしてくれたりとか。サポート体制も、その当時は電話すればすぐ繋がったとか。
その後2、3年かけて少しずつノウハウやコンテンツを貯めていった中でコロナ禍が来て、お店に海外からお客様が誰も来なくなった。そこで、今まで貯めてきたノウハウやコンテンツをECに反映し、思いっきりWebに力をいれはじめて、今のベースの流れになったかたちですね。
それまでは基本的に店舗主導で、ECは「決まったお客さんのリピート用」という位置づけで、品揃えもシンプルなものでした。あくまで補完的な位置づけ。でも今は、売上比で言えば3対1くらいですが、ECがどんどん伸びてきています。

(英語版のKakimoriサイト)
広瀬さん 越境ECに関しては、はじめは戦略的にというより、「将来的にやりたいな」くらいの思いだったんですが、その時期には国内からの注文に集中していたものの、少しずつ海外からの需要も増えていって。実際に越境ECを本格的に始めたのは、コロナ禍のことです。
ーー 越境ECでの戦略はどのように立てたのでしょうか。
広瀬さん 海外展開は、最初からヨーロッパと北米にターゲットを絞っていました。台湾やアジアでイベントをしたこともありましたが、アジア圏ではKakimoriのような情緒性やストーリーテリング系の商品はややわかりづらいところもあって、難しさも感じていたんです。
実際、台湾でイベントをやったときは最初はすごく盛り上がったんですが、そのあと一過性で終わってしまった感じがあって。裾野が広くて長く続けられる市場に向き合おうと、ヨーロッパとアメリカに絞っていきました。
結果的に今では、70ヶ国以上に商品が出ていて、卸先だけでも20カ国以上あります。当初はヨーロッパの方がマーケットが大きいと思っていましたが、アメリカで一番売れています。越境ECを始める際、地域を絞ってマーケティングをするという視点は今でも意識しています。
「日本製だから買う」ではなく、自然と伝わる日本らしさを
ーー 世界で受け入れられている理由として、Kakimoriというブランドが受け入れられているのか、それとも日本の文房具というカテゴリ自体に注目が集まっているのでしょうか。
広瀬さん デジタル化が起きている中で、“アナログ回帰”の世界的な流れが大きいと感じています。たとえばレコードが再評価されたり、フィルムカメラが売れているとか。「デジタルの時代だからこそアナログの価値が見直されている」という動きが、文房具にも来ていると思うんです。
世界の中でも成熟国の方がそこが堅調なのかなと思いますが、アジア圏でも少しずつ広がっていて売上が伸びているのが現在の状況です。

(Photo by Shoji Onuma)
ーー あえてメイド・イン・ジャパンを打ち出しているわけではないんですね。
広瀬さん KakimoriのWebサイトはパッケージや店の写真のトーン、言葉選びも含めて、過度に日本を打ち出すわけではないけれど、見ればわかるような、じんわり感じられるような日本らしさ、そこを意識しています。
ただ、日本製だから買うというよりは、「好きだと思ったら、あとで調べたら日本製だった」くらいの距離感を大事にしています。お客様の多くは、購入前にそこまで意識しているわけではなく、あとから「これ日本製なんだ」と知って、むしろ納得してくれるような流れが自然だと思います。
Kakimoriの実店舗やウェブがもつ世界観。国内外から支持をうけるKakimoriは、決して一足飛びに成功したわけではなく、さまざまな挫折や挑戦があってつくられてきたお話を伺いました。 後編では、実店舗とオンラインのバランスをどう取っているのか、Shopifyを活用してどのようにKakimoriらしさをオンラインで再現しているのか、その工夫と葛藤に迫ります。
後編では、【"らしさ"を届けるKakimoriが描く、リアルとECのこれから】について詳しくお伺いします。