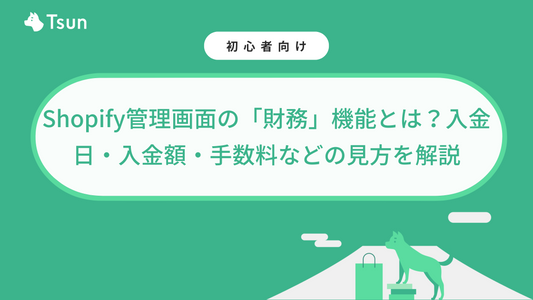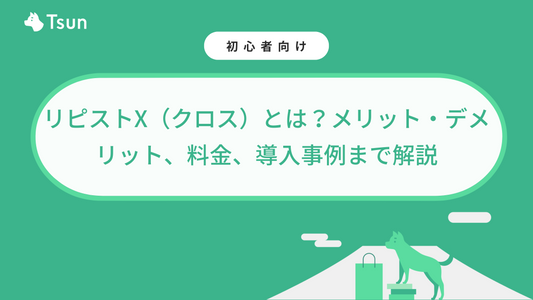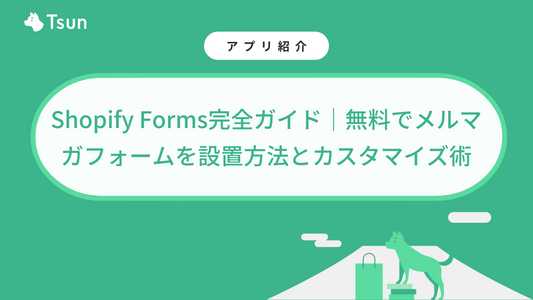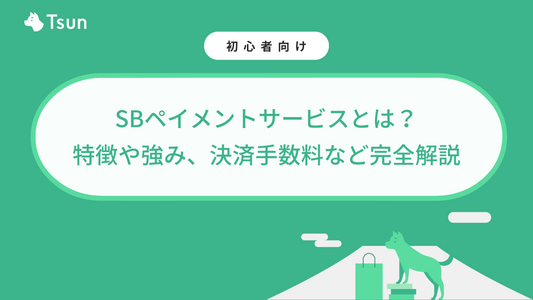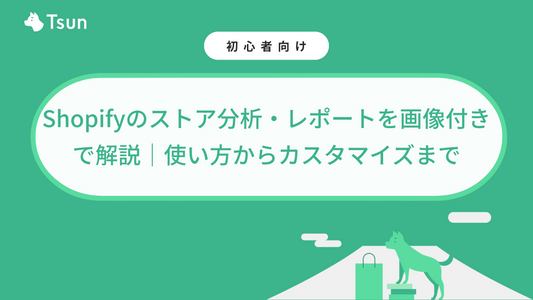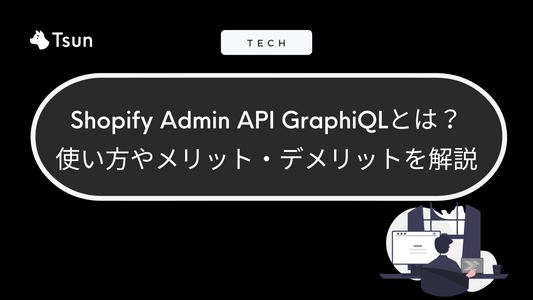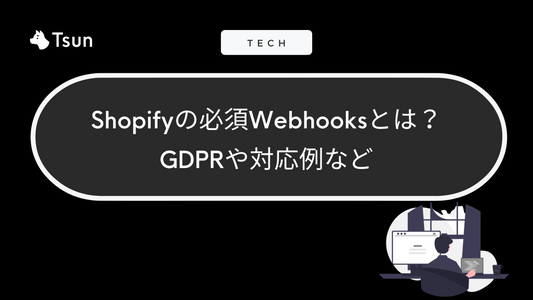2025年3月1日に、調味料の新しいDtoCブランド『里SEASONing』がローンチされました。企画運営は、調味料業界に特化した業務支援事業を展開する株式会社Rainbow Taste。オウンドメディア『調味料.jp』の運営など、地域に根づく「ご当地調味料」にスポットライトをあてて調味料業界を多角的に広げるべく、さまざまな事業を立ち上げているスタートアップです。
代表取締役の寺門里紗さんに調味料にかける思い、事業の立ち上げからメディアとECをわける事業戦略、今後のビジョンをお伺いしました。

株式会社Rainbow Taste 代表取締役 寺門里紗 さん
調味料の困りごとをすべて解決したい
ーー まずは、株式会社Rainbow Tasteさんの現在の事業について教えてください。
寺門 里紗さん(以下寺門さん) メインの事業は調味料製造者様向けの業務支援です。製造者さんの経営課題をお伺いし、解決策を提案して実行までサポートする仕事ですね。最近は商品開発や販促支援など、業務範囲が広がっています。
また、調味料特化のオウンドメディア『調味料.jp』の運営、そして3月1日にDtoCブランド『里SEASONing』をリリースしました。
ーー メディアからECまで、調味料に関して多岐にわたる事業ですね。
寺門さん 最初は「自分に何ができるのかわからない」状態でした。だから、まずは製造者さんの話を直接聞いて、困りごとを理解することから始めたんです。
最初は正式なサービスというよりも、目の前の課題を一緒に考え、試行錯誤するような形でしたね。そこから少しずつ支援内容が具体化し、事業として成り立っていきました。
製造者さんにいろいろとお話を聞く中で、「PRの場がない」「販売の機会が少ない」といった声を聞くことが多かったんです。無ければ自社で作ってみよう、と始めたのがWebメディア『調味料.jp』 です。ここでは、製造者さんの想いや商品情報を発信し、読者のみなさまと繋がる場を提供しています。
メディアを立ち上げた後、販売の場を探されている製造者さんの声を聞き、販売の場所を提供したいという思いで『里SEASONing』を立ち上げ、ご当地調味料の販売を開始しました。
ーー 業務支援 → メディア → 販売という流れが自然に生まれたんですね。
寺門さん はい。業務支援をしている中で「こんなサービスが必要だな」と感じたものを事業化していきました。あくまでも核となるのは製造者様のご支援で、その延長線上で新規事業が生まれている形ですね。

「旅の思い出を味に刻む」調味料を仕事に
ーー 寺門さんが起業を志した経緯をお伺いできますか?
寺門さん 大学卒業後は、一般企業で会社員として働いていました。一番長く関わったのは婚活業界で、マッチングアプリや結婚相談所、婚活パーティーの運営会社に勤めていました。主にバックオフィス業務を担当し、メインが秘書職だったんですけど、役員の方のサポートをする中で経営って面白いなというか、自分が達成したい目標のために起業しているのがすごくかっこいいなと感じるようになったんです。
単に「何かやりたい!」というよりも、経営そのものへの興味が高まっていきましたね。
ーー やりたいことからではなく、経営自体への興味から起業に向かわれたんですね。
最初は漠然と「20代のうちに何かチャレンジしたい」と思っていました。ただ、その頃は具体的に何をやるかが見えていなかったんです。その後、いくつかの企業を経験したあとに、やっぱり調味料が好きなことに立ち返って、何か自分で調味料をライフワークにできないかと。起業という手段で調味料を仕事にしてみようと思ったんです。
ーー 調味料を仕事にするくらい好きになったきっかけはなんですか?
寺門さん 実は父がスパイス好きで、家にはずらっとスパイスが並んでいました。幼い頃から調味料を使って味の変化を楽しむことが日常だったんです。
社会人になってからは、国内出張や旅行の機会が増えたんですが、仕事やスケジュールの都合で、じっくり観光を楽しむ時間が取れなかったんです。そんな中で「旅先で調味料を買う」という習慣が生まれたんです。現地の調味料を持ち帰れば、自宅でその土地の味を再現できるし、旅の思い出を味として残せるんですよね。
気づけば、調味料のコレクションが増え、写真を撮ったり感想をメモしたりするようになりました。それが、現在の事業のアイデアへと繋がっていったんです。

寺門さんが食べてきた調味料の記録リスト。膨大な量に調味料への熱意を感じます。
ECサイトと切り離したオウンドメディア戦略
ーー Rainbow Tasteさんは、ECストアの前にオウンドメディアを運営されていることがとても特徴的です。
寺門さん 一般的には、ECサイトにメディア機能を追加するケースが多いですが、弊社ではあえてメディアと販売をわける形を取っています。
メディアでは、調味料に関するストーリーや製造者の想いを発信し、顧客とのエンゲージメントを高めることにフォーカスしています。
将来的な事業計画でいうと、メディアに関してはコミュニティの機能などの付加価値をつけていきながら、最終的には調味料のプラットフォームにしていきたいという構想があります。そのベースがWebメディアです。そのため、ECストアの中のメディアではなく、独立したひとつのメディアとしてずっと機能させたいと考えています。
ーー 調味料のプラットフォームは面白いですね!
寺門さん 将来的には、Webのメディアの方にもEC販売の機能を設けて、そこで製造者さんに直接販売をしていただく構想を掲げています。
現在は、メディアとECの間に明確な導線を設け、適切なタイミングで商品購入へ誘導する仕組みを作っています。例えば、記事内に関連商品へのリンクを設置したり、調味料のレシピ紹介ページから直接購入ページへ遷移が可能にしたり。SNSと連携して、メディア記事をシェアしながら商品認知を拡大できたりするように、などですね。
DtoCブランド『里SEASONing』の立ち上げ
ーー 3月にリリースされた『里SEASONing』は会社の中でどのような事業なのでしょうか?
寺門さん 今回立ち上げたDtoCブランドの『里SEASONing』は、直営ブランドのような位置付けにしています。あくまでも直営で立ち上げたブランドで、ブランド力を持って推進をしていくというような建て付けにしていきたいので、メディアとは切り離して考えています。
『里SEASONing』はもともと業務支援事業の中で浮かび上がった「販売の機会が少ない」という課題解決に向けた事業ですが、単に販売をサポートするだけでなく、自社ブランドを立ち上げ販路のモデルケースを作ることにしたんです。
現在は、全国の製造者様と直接契約し、卸業者を介さない直販モデルを採用しています。これにより製造者様の利益率を確保しながら、ユーザーのみなさまに適正価格で届けることができる仕組みをとっています。

ショップ間の流動性の高さがShopifyを選んだ決め手
ーー ECサイトの立ち上げにShopifyを選んだ理由を教えてください。
寺門さん ゼロからスクラッチ開発するのはコストも時間もかかるためスピーディーに立ち上げたかったので、Shopifyを選びました。自社ブランドの販売サイトに特化させていくのに向いていることも理由のひとつです。
BASEやShopifyで作られているブランドをユーザーで利用していたときのことですが、Shop Payなどの決済方法は他のショップで入力した情報が別のショップでも使えるんです。すごく便利な機能だなと立ち上げ前から思っていまして、いちユーザーとして興味がありました。
ーー 決済機能に目をつけるのはプロのユーザーさんですね(笑)
寺門さん 私自身、お菓子や美容やいろんなDtoCサービスを使うのが好きなんです。ショップ間の流動性が高いところは、ユーザーとしてすごく便利だと感じていました。
ーー Shopifyストアの構築で、スクラッチ開発した部分はありますか?
寺門さん 現状ではスクラッチが4割、既存機能が6割くらいの割合ですね。
ただ、最終的な仕様はまだ確定していなくて、今後の運用状況を見ながら調整していく予定です。特に細かい機能についてはスクラッチ開発で対応している部分も多いですが、なるべくShopifyアプリを活用する方針です。
ロジとの連携がスムーズなのもShopifyならでは
寺門さん Shopifyを選択した理由のもうひとつに、配送機能を物流会社に委託することを決めていたことがあります。当初から在庫を抱えることを想定していたので、ECプラットフォームを決める前に先に物流会社を選定していました。すでに試験的に販売している調味料があって、在庫管理と発送を効率化する必要があったんです。
そこで、流動性が高く他のサービスとの連携がスムーズなプラットフォームを探した結果、Shopifyが最適だと判断しました。
ーー 物流委託先として「OPENLOGI」を選ばれていますが、その理由はなんですか?
寺門さん OPENLOGIはShopifyとの自動連携が可能なので、ほぼすべての工程を自動化できる点がとてもよかったです。最初の設定こそ多少の手間はかかりましたが、一度連携してしまえば、受注から発送までがスムーズに進むので、今ではほぼ自動で運用できています。
アプリ活用で育てていくShopifyサイト
ーー 現在使用しているShopifyアプリの中で、お気に入りのものを教えてください。
寺門さん まだ試行錯誤中ではありますが、特に便利だと感じているアプリは、まずはKOMOJUです。導入後の利便性には驚きました。特に、手間なく多様な決済手段を導入できる点が非常に助かっています。
以前、別の会社でECサイトの開発に関わったことがあるのですが、その際は決済システムの構築が非常に大変だった んです。でも、ShopifyとKOMOJUの組み合わせなら、ボタン一つで決済の仕組みが整うので、手軽さに感動しました。
あとはShopify Bundlesです。『里SEASONing』では、単品の調味料を複数組み合わせて1セットとするセット販売を基本としているのですが、このバンドル販売を簡単に実装できるアプリです。オプションを柔軟に追加できるので、ユーザーにとっても購入しやすいUIになっていると思います。
そしてOPENLOGIですね。物流の最適化には欠かせないアプリです。注文データと連携して自動で発送処理が進むので、人的リソースを大幅に削減できました。
もともと、物流まわりの業務は手間がかかる部分なので、「いかに自動化するか?」が重要でした。Shopifyとの連携を考えると、オープンロジは最適な選択肢だったと思います。

自社ブランドサイト『里SEASONing』でインストールしているアプリ
マーケティングの幅を広げるShopify
── 今、ECサイトの運営で課題に感じている点はありますか?
寺門さん 一番の課題はマーケティングの強化ですね。認知度を上げるための施策はまだまだ試行錯誤の段階で、特にShopify内でできるマーケティング機能をもっと活用していきたいと考えています。
また、メディア「調味料.jp」との連携もより強化していく予定です。ECサイト単体での集客には限界があるので、コンテンツを活用したマーケティングに力を入れ、ユーザーを「知る → 試す → 買う」の流れに誘導する仕組みを作っていきたいですね。
Shopifyは拡張性が高いので、DtoCブランドとしての成長に合わせて利用しやすいです。例えば、現在はShopify Bundlesを使ってセット販売を強化しつつ、段階的にサブスクリプション型の販売モデルも導入予定です。
メディアとの連携を深めることで、コンテンツドリブンのECという形に進化させたいですね。
── 今後のShopifyに期待することはありますか?
寺門さん 今後は、より柔軟なマーケティング機能が強化されると嬉しいですね。
たとえば、メディアと連携したキャンペーン機能とか、より簡単にパーソナライズされたプロモーションが設定できる機能が増えるとEC運営の幅も広がると思います。
調味料業界をECとメディアで変えていく
ーー 今後の事業展開について教えてください。
寺門さん 短期的には、DtoCブランド『里SEASONing』の認知度向上に注力し、ブランドとしての価値を確立させることが最優先です。その後、Webメディア「調味料.jp」をより多くの製造者に活用してもらえる場にしていきたいと考えています。
あくまでも弊社が提供したいのは、製造者さんへのソリューション提供です。最終的には業務支援の事業に戻ってくるというか、そこに軸足を置ける状態にまた戻るのが健全な状態だと思っているので、それは忘れずにやっていきたいですね。
会社としてまずは事業基盤をしっかり固めた上で、最終的には「調味料プラットフォーム」として業界全体に貢献できる存在を目指しています。
ーー 最後に、寺門さんご自身のビジョンを教えてください。
寺門さん 個人的には、「ご当地調味料の魅力をもっと広めたい」という想いが強いです。いろんな地域の調味料を知ってもらい、普段の食卓に取り入れてもらうことが私のライフワークですね。
「ご当地調味料」という独自の視点を調味料業界の可能性を広げるべく、多方面から挑戦を続ける寺門さん。ご自身の経験や情熱を活かし、新たな市場を切り拓く姿勢が印象的でした。貴重な事業戦略のお話、ありがとうございました!